
電脳社会を音楽で表現した小山田圭吾の3年間 ー『攻殻機動隊』とCorneliusの相互作用ー #01
文・浅原聡士郎正宗の原作漫画をベースに、映像化シリーズ第3弾として始動した『攻殻機動隊ARISE』。公安9課メンバーのキャラクターデザインが変更されるなど、大胆な試みで『攻殻機動隊』の新しい魅力を掘り起こした作品に、音楽で彩りを添えたのがCorneliusこと小山田圭吾だ。主題歌やエンディング曲だけでなく、約3年間にわたって劇中のさまざまなシーンで使われる曲を書き下ろしで提供。
聴き手の想像力を刺激する音はいかにして作られたのか。“アニソン”を巡る記憶と自身のこだわりについて、小山田圭吾に話を聞いた。
#01 『攻殻機動隊』とブッダマシーンの親和性
——『攻殻機動隊ARISE』に作家曲として関わる前から小山田さんはSFアニメが好きだったのでしょうか?
小山田圭吾(以下:小山田) 子どもの頃は『宇宙戦艦ヤマト』や『銀河鉄道999』が大好きでしたが、それ以降のテレビアニメには深くハマっていたわけではありません。僕たちの世代だと、小学生の頃に『機動戦士ガンダム』のブームが始まったのかな。ガンプラが流行っていたので僕も手を出してみたんだけど、2〜3個作ったら飽きちゃった(笑)。その後、『攻殻機動隊』の漫画や映画も注目を集めるようになって、もちろん存在は知っていたけれど、音楽制作のオファーをいただいた時点ではちゃんと見たことがなかったんです。
——初めて触れた『攻殻機動隊』はどの作品でしたか?
小山田 まずは当時の最新作だったテレビシリーズの『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』をチェックした覚えがあります。視聴してみたら、想像以上におもしろくて。サイバーパンクやハードSFの世界観がしっかりと作り込まれているし、大人が楽しめるエンターテインメント作品に仕上がっている。刑事ドラマの要素もあり、1話20分程度だから話のテンポも良くて、作品の世界にすんなりと入り込むことができました。その後に劇場版の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』をチェックして、僕が子どもの頃に見ていたようなアニメとは一線を画すクオリティの高さに驚きましたね。だから、そこから新たに制作される『攻殻機動隊ARISE』の音楽を手がけられるのは光栄な機会でした。
——その後、『ARISE』シリーズと長期的に並走されていくわけですが、まずは『攻殻機動隊ARISE border:1 Ghost Pain』のオープニングテーマから制作を始めたのでしょうか?
小山田 そうですね。たくさんの曲を作りましたが、最初に着手した『Ghost In The Shell Arise』は自分の中で思い入れが強い一曲。打ち合わせの段階で、『攻殻機動隊ARISE』はサイボーグの素子が「自分は何者なのか?」と自問自答する物語だと聞いていたんですよ。“魂の実存”が作品のキーワードだと。そういう要素をヒントにしつつ、僕としては最初から電子音が合いそうな予感がしていて。機械っぽい、グリッチ的な音を多用しながら、そこに人間が奏でる生楽器の音が共存している音楽を作れたらおもしろそうだと思っていました。
——まだ脚本が仕上がっていない段階で音楽を作り始めたんですね。
小山田 作品の概要だけ聞いて作り始めましたが、内容を知りすぎていないからこそ自由に表現できた部分もあるので、僕にとっては好都合だったかもしれません。でも『Ghost In The Shell Arise』は自分なりにアニメの主題歌であることを意識していたので、素子を演じる(坂本)真綾さんの声で作品のタイトルを入れることにしたんです。『マジンガーZ』にしろ『ルパン三世』にしろ、僕が子どもの頃に見ていたアニメって、主題歌の歌詞に作品のタイトルや主人公の前が入っていたから。最近のアニメを見ていると、とりあえず人気アーティストの新曲があてがわれているんだけど、あんまり作品の世界観にマッチしていないケースもあるじゃないですか。そうなるのは嫌でしたね。
——『ルパン三世』の主題歌はルパンの名前を連呼していますが、『Ghost In The Shell Arise』も“ゴースト”という言葉をリフレインしていますよね。
小山田 そうそう。ラテンのリズムで「ルパンールパンールパンー」って連呼している、あの感じが念頭にありました。潔くタイトルを歌っているから最高にわかりやすいし、あの曲は今でも自分の中でアニソンの最高峰だと思っています。そして、せっかく歌ってもらうなら声は主人公に任せたほうがいい。それこそ『レッツゴー!! ライダーキック』を藤岡弘さんが歌っている感覚で真綾さんに入っていただきたかったんです。藤岡さんは歌手ではなかったけれど、真綾さんは歌が上手なので不安はありませんでした(笑)。ただ、当時はまだアニメのアフレコが始まっていなくて、彼女の中で素子の演技プランが固まっていない状況だったんですよ。だから長いセリフを歌ってもらうことは避けつつ、コーラスのような感覚で基本的にはワンセンテンスだけ読み上げてもらって、その声を駆使して曲を作り上げました。
——劇中で使われる音楽は、最初に作った主題歌に導かれるように生まれていったのでしょうか?
小山田 そうですね。『Ghost In The Shell Arise』には僕が使いたかった音を一通りならべていて、その音色やフレーズを他の曲にも広げていった感覚です。全体の音色に統一感を持たせることで、ひとつの世界観を構築する。そこがサントラの仕事では重要なポイントになると思っていたので。
——『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の川井憲次さんや、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』の菅野よう子さんなど、大御所作曲家によって紡がれてきた音楽の歴史は意識しましたか?
小山田 もちろんチェックしましたし、皆さんが手掛けた音楽の高いクオリティに驚きましたが、それを参考にするべきだとは思いませんでした。かといって、あえて変えようとしたわけでもなく、自分らしくやればいいのかな、と。『攻殻機動隊ARISE』は新しいシリーズですし、監督も変わって、素子のビジュアルも声優さんも変わるタイミングで呼んでもらったので、僕も過去のことはあまり気にせず自由にやれたかもしれません。
——コアなファンだけが知っているレアアイテムだと思いますが、小山田さんのお気に入りである『Ghost In The Shell Arise』は、2013年に発売されたブッダマシーン(唱佛機)にも搭載されていますよね。
小山田 当時、ブッダマシーンを作ることが僕の中で夢だったのですが、それを『攻殻機動隊ARISE』の関係者の方に伝えたらあっさり叶えてくれました(笑)。ちょうどCD以外でも注目を集めるようなフィジカルの商品を出したかったみたいで。ブッダマシーンは搭載されている曲をリフレインするシンプルな機械で、本来はお経を流すために使われたものが、BGM再生機みたいな感じで世界的に流行っていたんです。僕は「GHOST IN THE MACHINE」という商品名で、マシーンの中に魂が入っているようなコンセプトで作りました。僕の趣味から生まれたアイテムですが、『攻殻機動隊』の世界観にハマったような気がします。
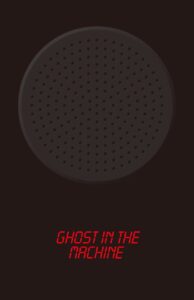
——真っ黒のボディにデジタルの文字が浮かび上がるようなブッダマシーンのデザインは、オリジナル・サウンドトラック『攻殻機動隊ARISE O.S.T.』のジャケットを踏襲しているのでしょうか?
小山田 そうですね。遡ると、1981年にポリスが『Ghost In The Machine』というアルバムを出していて、それが黒地に赤のデジタル文字が描かれているジャケットでした。それを僕らはオマージュしたわけです。ポリスは60年代に出版された同名小説の『Ghost In The Machine』に影響を受けたと聞いたことがありますが、たしか、それは『攻殻機動隊』も同じですよね。サントラのジャケットの話に戻すと、僕の中でサイバーパンクを表現するなら映画『トロン』のようなワイヤーフレームがわかりやすいと思って、それを紙で再現するために試行錯誤しました。結果、赤い紙を黒で塗りつぶして、裁断面だけが赤くなるような方式にしたんですよ。普通のミュージシャンの新譜だったら予算の都合でNGが出たかもしれませんが、幸運にも『攻殻機動隊』に関わる方々はフィティッシュなモノづくりに共感してくれる人ばかりだったので(笑)。ミュージックビデオもクオリティが高い作品が作れましたし、すごく嬉しかったです。
#02 2014年、METAFIVE本格始動の裏側 につづく
小山田圭吾 KEIGO OYAMADA
1969年1月27日生まれ。東京都出身。1991年のFlipper’s Guitar解散後、1993年からCornelius(コーネリアス)名義で音楽活動を開始。アルバム『THE FIRST QUESTION AWARD』や『69/96』が大ヒットを記録し、当時の渋谷系ムーブメントを牽引する存在に。2006年、映像集「Sensurround + B-sides」が、アメリカ「第51回グラミー賞」最優秀サラウンド・サウンド・アルバム賞にノミネートされた。現在、国内外多数のアーティストとのコラボレーションやリミックス、プロデュースなど幅広いフィールドで活動中。

