
《攻殻機動隊》を斜めから読み解こうとするうえで、田崎英明の過去の著作群は、あたかもそのために書かれたのではないかと錯覚するほどに、またとない手引きとなっている。
事実としては、田崎が過去の著作で《攻殻機動隊》について直接的に言及したためしは、ほぼない。けれども、ジェンダー/セクシュアリティの研究者として、サディズムとマゾヒズム、能動と受動、暴力と愛、自己と他者、個体と共同体などの二項対立のあわいに立ち、それらをまったく意表を突くような仕方で調停させてきた田崎の思想は、《攻殻機動隊》が提示する作品世界の最もラディカルな部分とも、深く、淫らに、共鳴している。
以前、田崎は自身にとってセクシュアリティが理論的に意味をもつ理由について、こう述べていた。「それが、苦痛を快楽に変え、また、憎しみを愛に変えることで、ひとにサヴァイヴァルを可能にするからであり、さらにいえば、個体化と共同性とが、まさにそこにおいて形成される場だからである」。
はたして今回、私たちのサヴァイヴァルの可能性──個体化と共同性が形成される場の探究へと再び向かった田崎が、一縷の望みを懸けて厄介な探究の共犯者として選んだのは、ハードボイルドな公安9課においては異彩を放つキュートさによって、S.A.Cシリーズのマスコット的存在としての地位を不動にしている、あの彷徨える蒼き思考戦車──「タチコマ」──である。
目次
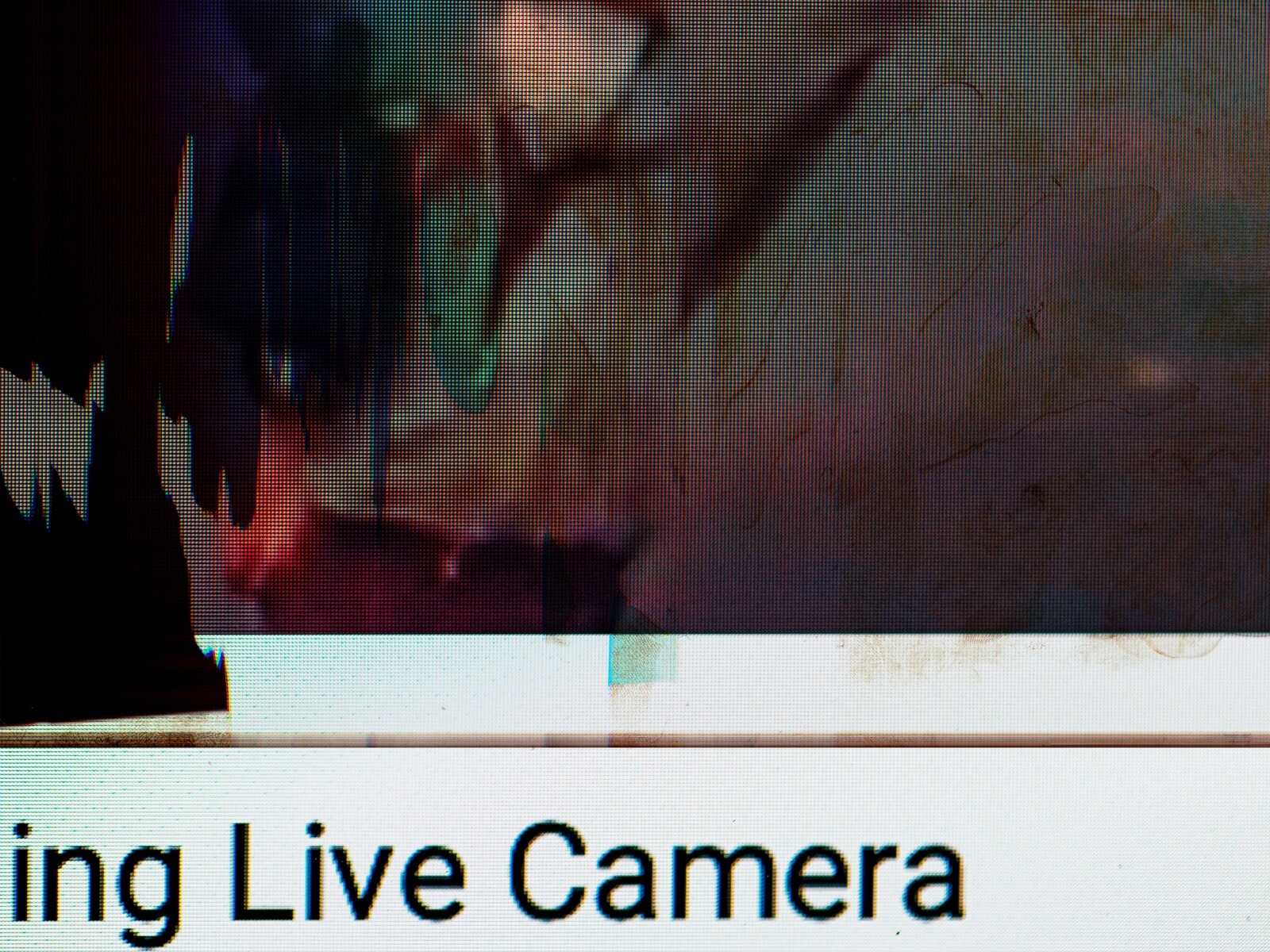
タチコマたちの物語
神山健治監督のTVアニメ・シリーズ『攻殻機動隊 Stand Alone Complex』(第1、第2シーズン、以下『S.A.C.』)はタチコマたちの物語である。
物語の終結部で、タチコマたちの自己犠牲がカタストロフを回避するという決定的に重要な役割を果たすのは間違いない。このことは、メインストリームに属する登場人物を生かすために周縁的な属性のものが死ぬという(マーベル原作の《アヴェンジャーズ》シリーズで言えばブラック・ウィドウのような)物語のヴァリアントではあるし、また、映画『ブレードランナー』(1982年)でレプリカントのリーダー、ルトガー・ハウアーが、死の間際、これまでレプリカントたちを情け容赦なく「破壊」してきたバウンティハンターのハリソン・フォードを助けたこと(知性において創造者たる人間を凌駕したばかりではなく、人間とレプリカントの唯一の弁別特性であったはずの共感能力でも人間を凌いだ)の再演とも言える。
だがそれよりも重要なのは、タチコマたちが「個と集合性」というこのシリーズのテーマを体現している点だ。哲学者のスタンリー・カヴェルはTVのメディウムスペシフィシティを「シリーズ性(seriality)」、つまり、続きものであること、「次回に続く(to be continued…)」に見出したが、『S.A.C.』というシリーズにおいて形式上も内容においてもこのシリーズ性を体現するのが、タチコマたちなのだ。
士郎正宗原作の世界では、すべてのものが接続されてはいても「個人」や「国家」などのボーダーは消えていない。この「シリーズ性」の意味するところを《攻殻機動隊》シリーズで最も律儀に探究しようとしたのが『S.A.C.』であると言えるだろう。
テクノロジーと身体図式
ベルナール・スティグレールの技術論としての哲学は、『S.A.C.』を理解するための重要な手がかりを与えてくれる。
スティグレールの主要な参照項である考古学者のアンドレ・ルロワ=グーランが夙に指摘したように、現生人類の特徴は記憶の外部化にこそある。現生人類は様々な道具というかたちで記憶を、過去を自らの身体の外部に保存してきた。
身体は過去と現在との時間的インターフェースであり、(その個体自身の経験であれ、先行する世代から継承した遺伝的なものであれ)記憶と環境とのネゴシエーションのメディアである。そして、人類に特徴的なのは、身体の外部に保存された記憶を、自分の身体を通して読み出さなければならないということだ。言語であれ、その他の様々な道具であれ、その使い方に習熟しなければならない。道具の使い方を習得するときには、私たちはその道具の「使われていた」という過去に対してシンクロしなければならない。そして、その過去はもちろん私の過去ではない。私ではない誰か、誰でもあり誰でもない誰か(フランス語で言えばon)の過去、「私の現在」としては生きることができない過去とシンクロし、徐々にそこから離脱して「現在」へと浮上しなければならない。つまり、「誰か」から「私」への人称の転換が、道具の使用への習熟というかたちで、言い換えれば、環境に対する道具連関の適切な配置(あるいはその失敗)というかたちで起こる。
この習熟の時間性こそが私たちの身体性の根幹をなす。(「身体をもつ/身体である」という両義性を含めて)私たちが身体的存在であるということは、(データやソフトウェアをダウンロードしてインストールするように)道具連関ないし道具使用のコンテクストへと瞬時にシンクロしてしまうのではなく、その同時性からの隔たりという意味でのディアクロニーが不可避であることを意味する。そして、シンクロニーからの隔たりとしてのディアクロニーこそが「私」の生成過程である。道具を掴む手や音声を発する声帯、あるいは表情など、「私」の特異性(singularity)はここにこそ宿る。それは私固有の時間性の生成、言ってみれば、私が自分自身に私の時間を与えるのである。個体と集合性の根底にあるのは、このシンクロニー/ディアクロニーの共存=差異化であり、また、個の時間性と集合的な歴史性とが分節化されるのも、この時間の自己贈与においてである。「私に時間を与えているのはたしかに私だ」という感覚、「この(生きられた)時間はたしかに私のものだ」という感覚が、スティグレールが言う「本源的ナルシシズム(primordial narcissism)」の内実をなす。
だが、ここで忘れてはならないのは、このシンクロニー/ディアクロニーの過程は身体とその外部記憶である道具との関係で生じるということだ。つまりこれは、純粋に「心的」な出来事ではなく、「私」と道具連関とを媒介する身体図式を前提にしていなければならない。よく「自動車を運転しているときは自分の身体の幅が車の大きさまで拡張され、触覚はタイヤにまで延長されている」と言われるように、身体図式は皮膚境界面を超えて外に(時には内に)拡張(縮小)され、変形される。今日、多くの人がスマホを通じてネットに常時接続されている。私たちの身体図式がどうなっているのか、じつのところ誰もよくわかっていない。それにもかかわらず、私たちは相変わらず、これまでの人型をした身体イメージに囚われたままだ。
今日の身体図式のあり方(とその身体イメージからの乖離)の解明は、私の理解する限りでは、極めて喫緊の課題であるにもかかわらず、理論的な取り組みはまだまだ進んでいないし、そもそも適切な問いの立て方とはどのようなものかも詳らかではない。だが、表現の世界では先駆的にこの問いに取り組んできた者たちがいる。デイヴィッド・クローネンバーグは『ビデオドローム』『スキャナーズ』『ザ・フライ』『イグジステンズ』『コスモポリス』といった諸作品を通してこの問いを形象化してきた。アニメで言えば、《エヴァンゲリオン》シリーズに「人の形を保つべきか否か」という問いが見られるものの、やはり、常時接続された身体の問題をそれとして取り扱う作品としては、神山健治の『S.A.C.』の出現まで待たなければならなかった。
神山『S.A.C.』に先行する押井守『Ghost In The Shell/攻殻機動隊』(以下、『GITS』)と『イノセンス』では、二項対立の軸を「情報/物質」という形相/質料図式のヴァリアントに設定し、「身体(人の形)を捨てる(=ネットへの同一化)/人の形を捨てない=身体のまま留まる」の対比の中で動く物語となっている。そして、その物語を駆動させているのは「身体的である=現在/非身体的である=未来」という時間性の想定だろう。だがこれでは、すでに起きている本源的ナルシシズムの貧困に深く関わる、身体図式の変容に対して問いを立てることができない。
それに対して『S.A.C.』の神山健治が問題にするのは、「身体か、ネットか」の二者択一ではない。「私」と道具連関を媒介する身体図式の時間性の変容にこそ関心が向けられる(これはその後の『東のエデン』がヴァーチャルリアリティではなく拡張現実を、そして他方で労働する身体を扱うことになった理由でもあるだろう)。

メガマシンと本源的ナルシシズムの行方
自らの時間を与える力能、要するに道具連関への習熟の時間性は何よりも身体に属する。これが厄介の元だ。身体がそこへと自らを入りこませる道具たちは連関をなしている。さっと手を伸ばして掴めばいい単品のハンマーとは限らない。スパナやドライバーなどの工具が載った小さな台と、一定の速度で流れるベルトコンベアかもしれない。つまり、それは機械体系でもありうるのだ。そして、その機械体系には、私以外の身体も組み込まれているかもしれない。
機械について考える際には、ルイス・マンフォードが『機械の神話』で論じた「メガマシン」を参照するに越したことはない。マンフォードは、産業革命期の機械化を、人類が初めて経験した未曾有の出来事とは考えていない。すでに古代の王権が人間をその部品とする巨大な機械をつくり上げていたのだと言う。ただし、金属でできた枠組みや歯車など無いので、現代の私たちからするとその存在に気づきにくい「見えない機械」なのだが。メガマシンは、王をそのモーター(この場合はアリストテレス的な第一動者)とし、細々と機能分化させた部品(細かく職能が区別された人間たちからなる分業体制)から組み立てられている。しばしば軍事機械や灌漑機械、あるいはその他の土木工事(ピラミッド建設とか)機械としてイメージされるが、必ずしも機能的に限定されたものと考える必要はないので、一括りに「メガマシン」と呼ばれる。
古代のメガマシンも近代の産業革命期の機械も人間の筋肉の延長であり、生身の人間一人ではなしえないことを可能にする。そして、その機械体系の部品としての人間は、求められる機能を果たすためにも「誰か」から「私」への転換を果たし、機械を滑らかに動かさなければならない。そうして労働する「私」という身体は、機械の中に埋め込まれつつ、自分の時間を生きることになる。
ところが、機械体系のジョイントをなす「私」はメガマシンにとって余計者でもある。この「私」、つまり、主体は機械体系への同意を覆すこともできるからだ。メガマシンあるいは産業革命的機械を作動させるためには、言葉による説得であれ、金銭的な合意であれ、あるいは暴力や恐怖による脅しであれ、「私」という主体という次元をバイパスすることはできない。だから、鉱山やプランテーションは、奴隷叛乱の可能性を完全に潰すことができなかった。「自分が自分である感覚」「私が他ならぬこの私である感覚」である本源的ナルシシズムは、メガマシンが機能するうえで必要条件であるが、同時にその機能不全をもたらす原因でもあったのである。
だが、個人の意識が市場化し産業によってコントロールされる、ハイパーインダストリアル社会では、本源的ナルシシズムの貧困化が生じる。スティグレールによれば、メディアテクノロジーの進展によって、「時間的対象=モノ(temporal object)」が生産される。過去の時間を記録し、再生する映画やレコードのような時間的対象が「私」の身体と結びつく時代においては、「私」という主体に命令や指示を出すことなく、知覚のレベルで権力が身体図式に介入することができる。こうしてジル・ドゥルーズがコントロール社会と呼ぶ支配の体制が生じる。
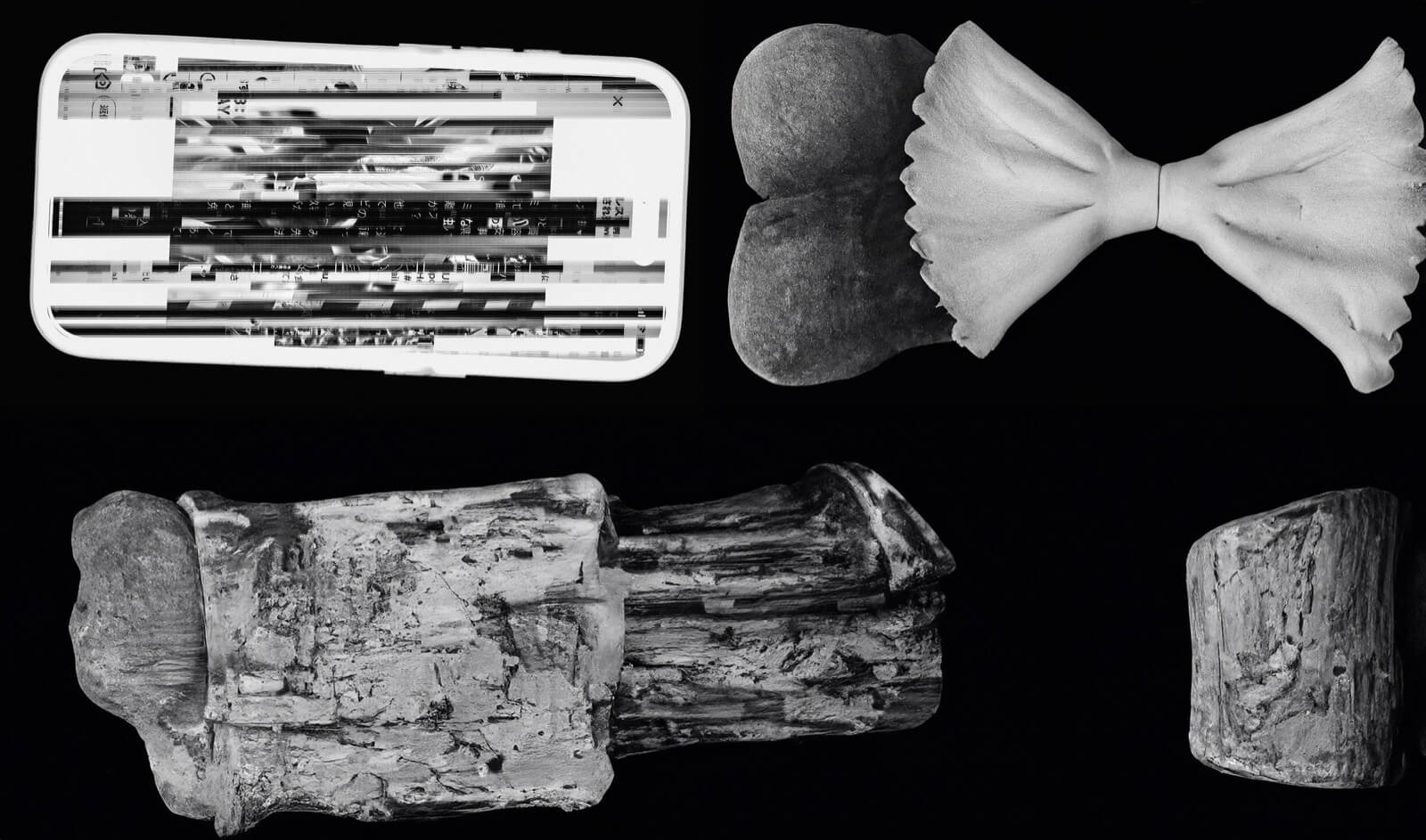
時間的対象の生産とコントロール社会
演劇であれば、すでに作家によって書かれ印刷された台本があるかもしれない。音楽のコンサートであれば、すでに書かれた楽譜があるかもしれない。これらの外部記憶を俳優たちや演奏家たちが現在へともたらす。その現在化の時間性は観客と分有される。観客もまた、いま見たり聞いたりしていることが、いま起きているものとして感覚され、それらは「私」の時間として生きられ、「私」への生成を果たす。
ところが、スティグレールが典型的な時間的対象と考える映画やレコードでは、「私」ではなく誰かの記憶ないし過去が自動的に再生される。これでは、その過去を「私」の現在として生きる必要がなくなってしまう。これは私の記憶なのか、それとも他の誰かの記憶なのか。「誰か」から「私」を隔てるための時間が省略されてしまい、「誰か」と「私」が重ね書きされてしまう。
これがスティグレールの言う本源的ナルシシズムの危機である。そのとき、ひとは、無理やり自分を他者から差異化するためにアクティングアウトを起こしてしまう。これは私だけの記憶だ。この記憶の始まりにいるのはたしかに私だと自らに信じ込ませるために。「私だ、私こそが本物の、オリジナルの笑い男だ」と。もちろん、その記憶も信念もコピーのコピー、オリジナルの定かではない模造品に過ぎず、私は本当に私自身であることを、自分自身を含めた他の誰に対しても確信させることはできない。
あるいは、シリアルキラーを考えてみてもいい。自分が規格化されたシリーズ物の量産品であることを否定するために、自分自身の固有の死を取り戻そうとするのだが、自己と他者、自己の死と他者の死の区別がつけられないために殺人を繰り返す。「私は自分を殺そうとしたのに死んでいたのはいつも他人だった」と、多くのシリアルキラーは回想する。
身体図式は感覚(受動)と運動(能動)とを総合する作用である。より正確に言えば、図式において受動から能動への転換が生じる。その転換が起きる場所ならぬ場所が「私」なのだ。しかし、デジタル化されたネットワークテクノロジーは、想起や知覚といった「私」の最も内奥に位置すると思われていた総合作用を、産業的生産物(検索や記憶再生のためのプログラム)によって代替することを可能にした。「私」から能動性や自発性を奪うのだ。
このような本源的ナルシシズムの危機に際してアクティングアウトを起こさず踏み止まるために、《攻殻機動隊》シリーズのバトーは全身義体化した身には不要な筋トレを欠かさない。バトーは筋トレのことを自分の同一性を失わないための外部記憶と捉えている。サイボーグの彼が筋トレをしても、生身の身体図式を取り戻したり、生身の時間性が義体に上書きされたりすることはないのだが、かつての生身と義体の連続性を担保するために、生身の身体の記憶の、オリジナルなきシミュラークルをつくり出そうとするのである。
ところで、義体と「私」という主体の関係とはどのようなものなのだろうか。「私」と身体との関係には「私が身体である/私は身体をもっている」の両義性があることはすでに触れた。これは、道具を掴む手が私の身体なのか、私にとっての最初の道具なのか、そのどちらかにきっぱりと決定できないということだ。たしかに自分の身体であっても思う通りに自在に動かせる訳ではない。身体がいささかも道具的でなかったら、私たちは道具を掴むこともできず、決して道具を使えなかっただろう。しかし、身体と道具の境界はたしかに存在する。
例えば、私はメガネをかけているのだが、メガネ越しにコンピュータのモニターを見、キーボードを操作するとき、メガネは私の身体の側に取り込まれてはいるが、コンピュータのモニターやキーボードはそうではない。たしかに世界は一定の行動可能性を身体に喚起する一種の「指向弓(arc intentionnel)」をなしていて、私の身体の近くで閉じる円環から、最終的にはこの世界全体を経巡る円環まで、無数のレイヤーが重なっている。しかし、その円環の途中には(見ることの境界面としてのメガネ、触れることの境界面としてのタイヤ、あるいはパンチやキックの発生する場所としてのコントローラのような)切れ目があって、その手前と向こう側は差異化されている。
《攻殻機動隊》の世界で、義体はたしかに大抵の場合、この切れ目の手前側、道具連関の手前に位置する身体の側にあるように思える。けれども、義体化技術、いや、そもそも電脳化によって、道具連関と身体の断面はつねに一定のハードウェアによって媒介されている。しかも、ネットと常時接続されているために、笑い男のような超A級ハッカーの手にかかれば時間的対象を使った支配どころか、「私」という主体までリアルタイムでハッキングされるおそれがあるということだ。電脳化されたテクノロジーを生きる「私」からすると、身体と道具連関だけでなく、そこに境界を見出す「私」さえもあまりに滑らかに繋がっているので、そのあいだに何かが差し挟まれていたとしても気づかない。
ここでドゥルーズのコントロール社会論を思い起こそう。彼は「コントロール社会」という言葉をウィリアム・バロウズから借りてきた。それが意味するのは、コントロール社会について考える際に、ドラッグという観点は欠かせないということだ。ドラッグは分子レベルで直接神経に作用する。同じように、コントロール社会において権力が介入する地点はもはや主体ではない。拷問等によって主体に働きかけ、表象を経由して(「この指は何本に見えますか?」)その意志を変えさせるのではなく、直接神経に物質的レベルで作用してコントロールする社会。オーウェルではなくバロウズ。
『S.A.C.』の世界では、ドラッグではなく、ネットとの神経接続とナノマシンが「表象/主体」とは別のレベルで私たちに作用する。(メガマシンのように)王のような中心が存在して、それが一貫したかたちで命令を発するのではなく、ネットワーク上に分散したコマンド(それ自体一種の分散表象のようなものとして存在しているだろう)の離合集散の中から、ある行動が生まれる。私の身体図式が、「私」には気づかないレベルの分散された微小な表象のレベルで、私の与り知らぬネットワークに接続されている。《攻殻機動隊》は、このような常時接続が主体さえも道具化する中で生じている世界なのだ。
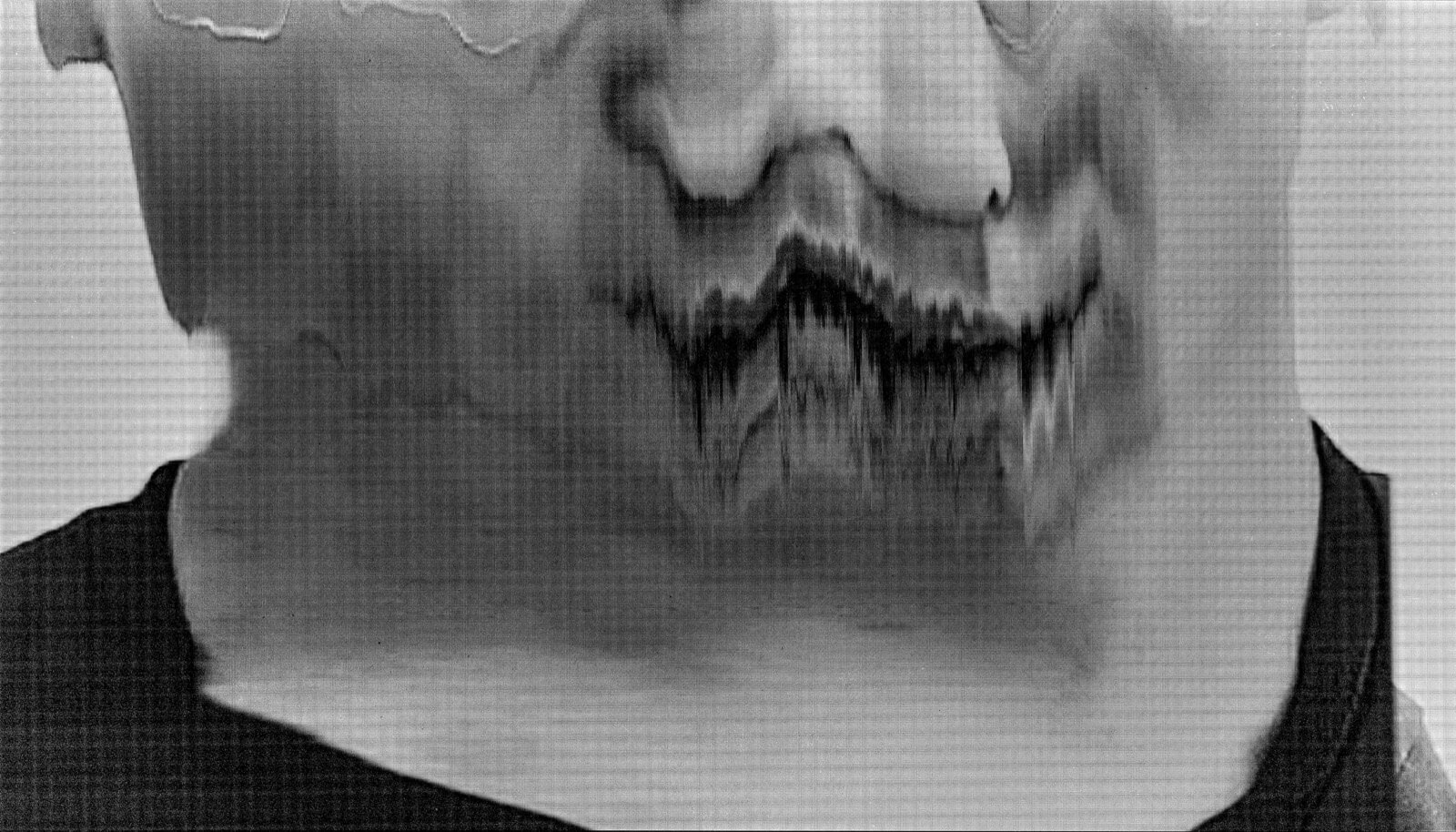
天使たちの時間、機械たちの時間
キリスト教神学では、基本的に被造物は形相と質料からなる複合的な実体とされる。個物(=実体、例えば一匹のイヌ)は抽象的な形(イヌ一般のような)と具体的な物質性が不即不離で、(「不定形性」も含めて)形を伴わない物質性も、物質性なしの形もそれだけで自存することができない。だが、天使は被造物であるにもかかわらず、形相からだけなる実体(分離実体とか単純実体と呼ばれる)であるとされた。それは物質性をもたない純粋な知性であり、何かを認識するにあたって感覚器官やそれが生み出す感覚的表象を必要としない。というよりも、そもそも天使は身体をもたないのだから感覚的表象をもちようがない。それはまた、天使に学びや習熟の時間性がないということをも意味する。天使は学ぶのではない。瞬時に認識する。例えば、円周率の一億桁目が十進法表記でいくつになるかを知るには、人間は計算しなければならないが、神や天使などの純粋な知性は即座に知る。
『S.A.C. 2nd GIG』には、光学迷彩で人間の眼には見えない存在となったバトーが、後ろで髪を束ねた姿で登場するシーンがある。ここで参照されているのは、ヴィム・ヴェンダース監督『ベルリン・天使の詩』(1987年)でブルーノ・ガンツが演じている主人公の天使ダミエルである。天使たちはただ見るだけの存在で、知ることはできるが直接世界へと、歴史へと介入することはできない。先達の顰みに倣いバトーは、ただ見守るだけの守護天使になってしまい、危うく本来の使命である国際的な爆弾事件の容疑者を取り逃がしそうになる。
だがそもそも、『S.A.C.』で天使に類する存在はバトーでも草薙素子でもない。それはタチコマたちだろう。
天使と違い、私たち人間は不可避に感覚的表象に頼らざるをえない。例えば、電子書籍は端末にダウンロードするだけではだめで、モニターでの表示や読み上げ機能によって一度アナログ化する必要がある。それに対してタチコマたちは、デジタルデータとしてダウンロードすれば十分だし、データを劣化させることなく他のタチコマとも共有できる。もちろん、タチコマは公安9課の活動を支援するためのものなので、単に見守るだけではなく、腕や脚もあれば、様々なセンサーも備えている。個々のセンサーを通して捉えた情報は、天使のそれというよりは、人間の感覚的表象に近いとも言えるだろう。
しかし、タチコマたちが(少なくとも第一シーズンの「笑い男」では)ひとつミッションを終えるごとに記憶を並列化され個体差が生じないようにされていたという事実は、どうも天使を想起させる。ここで思い出されるのが、純粋な形相である天使は一個体が即種であるのかをめぐって、中世ヨーロッパで戦われた論争である。というのも、しばしば個体化の原理は質料にあると考えられていたからだ。つまりイヌの形相は種としてのイヌに対応し、個々のイヌは質料との合体によって現実化する、だから個体化の原理は質料にある、という論理である。
天使の質料の話をタチコマに差し戻してみよう。定期的に記憶が並列化されるとき、タチコマの物理的身体による個体差は消去される。つまり記憶の並列化を通じて形相の状態を取り戻すタチコマの場合、質料を伴うということが個体化の要件にはならないように思える。質料のない天使と同じく、タチコマにも個体差を消す並列化というテクノロジーを介した、種と個体の一致が生じているようにも見える。たしかに、記憶が並列化されているために、犬を探す少女と出会ったのはどの個体か、あれはどの個体の記憶なのか、区別がつかない。「私が他ならぬこの私である感覚」である本源的ナルシシズムなど生まれるはずのない存在、それがタチコマであった。
だが、そのような並列化を繰り返しながらも、タチコマたちは個体化のプロセスを止めることはなかった。例えば、デジタルデータをダウンロードするのではなく、光学センサーを用いてアナログの紙の本を読むことを好む個体が現れる。それは、天使のように即時的に知を得る無時間的な知ではなく、身体性を伴い時間をかけて「学ぶこと」への関心である。デジタルデータのダウンロードでは、「知らない/知っている」という二つの状態の差異は、それ自体は時間の厚みを欠いた、非時間的とも言える「知」によって区切られる。しかし、身体的で感覚的表象を伴った「学ぶこと」「習熟すること」はそれ自体始まり(むしろ「すでに始まっていた」)と終わり(同じく「まだ終わっていない」)をもった時間的広がりの内にあり、「知りつつある」という時間性がそこにはある。『S.A.C.』におけるタチコマとは、天使どころか、天使的な時間性(シンクロニー)への抵抗を担う物語上のエージェントなのだ。

常時接続下での身体化の探究
ネットへと常時接続された人間たちは、一方で、本源的ナルシシズムの衰弱に耐えられず、アクティングアウトを起こし、並列化された時間から近代的個の記憶を切り抜き(虚しく)抗おうとする。他方で、別の人間たちは、むしろ常時接続(そこではまだ個体性は存続し、個体と個体を隔てるボーダーは消滅していない)を超え、身体を捨ててネットと一体化するという誘惑に駆られる。
『S.A.C. 2nd GIG』で難民叛乱のリーダーとなるクゼは、そのカリスマ性で、電脳化していない貧しい難民たちをも虜にできる存在であり、揺らがぬ信念をもった革命家である。だが、彼の目指す革命とは、じつは、人間たちにその身体を捨てさせ、そのゴーストごと(つまり、何らかの仕方で個体性を失うことなしに)ネットの中に移住させることなのだと、クゼは素子に明かす。「身体性から非身体的であるネット上の存在への移行」が低次の存在から高次の存在への移行と同義であり、その移行こそが個と集団、そして個人の時間性の、集合的な歴史性への統合であるとする物語的な時間性への理解が示されるのだ。難民居住区への核攻撃が迫る中、苦渋の選択として、難民たちをゴーストごとネットへと移送させることがクゼから提案され、素子はタチコマたちにネット上に300万人のデータを保存するスペースを確保するように命じる。本当にゴーストごとネットに上げられるのか、成功するのか定かではないこの試みに、「失敗したとしても人類の新たな段階に踏み出した偉大な先駆者として名を残すだろう」というクゼの言葉を信じるかのようにして。
だが、タチコマたちは素子の命令に抗い、自分たちのサーバーが搭載された人工衛星を、そうと知りつつ核ミサイルに衝突させて、難民たちを身体のままの存在として救う。
クゼは、『S.A.C.』の中で、じつは、最も『GITS』の物語に近い存在だった。その物語に素子も誘惑されかけ、『S.A.C.』に「身体/ネット」「物質/情報」という二元論的結構を与えかねなかった。それに対してタチコマたちは、常時接続下での身体化の探究という物語を守ることを選ぶ。
たしかに、それは常時接続された身体が織りなすコントロール社会からの出口やその全体を批判できるような「外部」を提示する物語ではない。だが、「私たちはコントロール社会の中にとどまりながら、どのように身体や(外部)記憶をめぐる時間性を探究していくべきなのか」という問いの先駆的探究者として、タチコマ(たち)の個体性=集合性を形象化し物語化した意義は計り知れない。少なくとも、『S.A.C.』を観たあとで、これまで社会や身体やテクノロジーに関して自分が立ててきた問いの立て方が適切であったかを真剣に考え込まなければならなくなることは確かだろう。
もちろん、重要だが、問われなかった問いを取り上げ直す必要もあるだろう。『S.A.C.』のジェンダーに関わる規範は極めて「古風」である。人型のオペレーターのアンドロイドはすべて女性に象られ、他方で秘書用のアンドロイドは男性型、登場人物にしても、主人公・草薙素子以外には、女性は第二シーズンの「日本初の女性総理」茅葺、それとトグサの妻やその他の登場人物の妻という具合に、現在の日本の状況と大差ない男性中心的社会となっている。その点で、タチコマの存在は(一人称が「ボク」であるにしても)ユニークなものとなっている。
天使と質料の問題には続きがある。質料を伴い、身体化した存在である個体が、自らの複製をつくり出す=生殖するには質料化された道具、つまり同種の別個体を必要とするのだ。言い換えるならば、個体が「性を伴う(sexué)」のは、個体化の原理である質料性の故である。裏を返すと「性化(sexuation)」とは、個体が質料によって身体化されている証ということでもある。タチコマのジェンダーのアノマリーさは、身体性と性化(gender化というよりもsexuation)の結びつきという点からは無視できないはずなのだが、『S.A.C.』では素子のセクシュアリティも含めて、ジェンダーやセクシュアリティの問題は仄めかされるだけで正面から取り扱われない。バイナリーではないかたちで、“gender”と“sex”というかたちできれいに切り分けられない性が、身体図式にどのように組み込まれているのか。その探究は、言うまでもなく私たち(というより私自身)の課題である。

[参考文献]
●ベルナール・スティグレール『象徴の貧困1』ガブリエル・メランベルジェ、メランベルジェ眞紀訳、新評論、2006年
●ベルナール・スティグレール『技術と時間3 映画の時間と〈難-存在〉の問題』石田英敬監修、西謙志訳、法政大学出版局、2013年
●トマス・アクィナス『神学大全4 第一部第44問題-第66問題』高田三郎、日下昭夫訳、創文社オンデマンド、講談社、2021年
●ルイス・マンフォード『機械の神話』樋口清訳、河出書房新社、1971年
たざき・ひであき/ポストコロニアル・クィア理論、身体社会論、身体政治論。立教大学現代心理学部教員。1960年、東京都生まれ。著書に『ジェンダー/セクシュアリティ』(岩波書店、2000年)、『無能な者たちの共同体』(未來社、2007年)、翻訳書に『否定的なもののもとへの滞留 カント、ヘーゲル、イデオロギー批判』(スラヴォイ・ジジェク著、酒井隆史共訳、太田出版、1998年)など。

