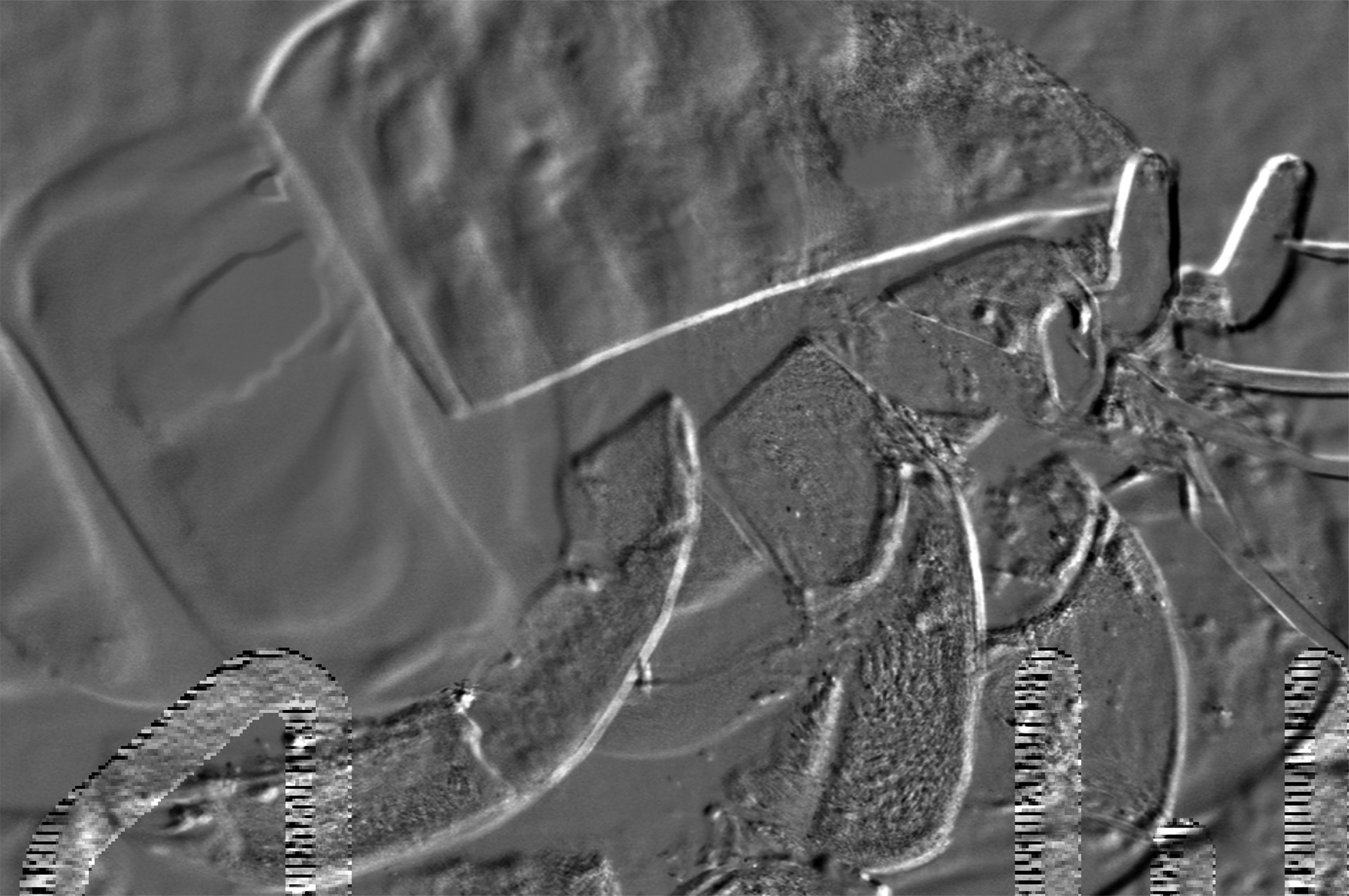
官僚として長らく経済産業省に勤務した西山圭太は、不良債権処理から情報通信政策まで、日本社会が抱える山積みの課題に向き合ってきた。1985年に入省した西山のキャリアは、ほとんどが「失われた30年」に捧げられたことになる。しかし、その表情に曇りはない。2019年のダボス会議で日本が発表し、その後G20やG7においても活発に議論され続ける「DFFT」(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)の影の立役者でもある彼は、統治における人工知能(以下、AI)の可能性を信じる現実的な楽観主義者だ。
オプティミズムの背景には、骨太な思想がある。官僚として働く傍ら、ディープラーニングのメカニズムや神経科学のモデルとして使われる「マルコフ・ブランケット」からインスピレーションを得た西山は、生命や物質、情報を貫く独自の宇宙論「強い同型論」を提唱。AIにも人間にも、ほかのあらゆる生命体にも共通する「ある」ことと「知る」ことの同型性から、物心二元論や要素還元主義を超えた関係性の実在論へと向かう壮大な理論を展開したのである。その構想はAI研究者の松尾豊と経済学者の小林慶一郎との共著『相対化する知性』としてまとめられている。そこには士郎正宗が《攻殻機動隊》シリーズにおいて展開した生命哲学とも近しい想像力が胚胎しているだろう。
産業構造の転換を超えた思想的な変化の端緒として生成系AIの登場を言祝ぐ西山は、日本社会の行く末をどのように展望しているのだろうか。最新の科学技術と古今東西の思想、各国のガバナンスとAIの関係性、デジタルトランスフォーメーションと国内外の組織改革、テクノロジーと歴史哲学……思想と公的実践の複雑な絡み合いの中で育まれる氏のヴィジョンをじっくり聞いた。
目次
明治=昭和平行説のあとに
批評家の柄谷行人は『終焉をめぐって』の中で、明治と昭和のあいだには平行的な構造があると書いている。例えば、明治10年には西郷隆盛が明治政府に反乱を起こした西南戦争があり、昭和11年には陸軍青年将校らが政党政治を倒そうとした2.26事件があった。明治も昭和も21-22年ころに憲法体制が確立している。おおよそ同じようなサイクルで時代の浮き沈みが見られるというわけだ。明治と大正を合わせると60年、昭和は64年だから、60年周期説だとも言える。
官僚として仕事をしているあいだ、政策を構想するには、歴史の流れを捉えることが大事だと思っていた。2000年代初頭に不良債権問題に取り組んでいた私にとって、柄谷の見立ては説得力があった。もしいまが60年前の反復なのであれば、これは戦後処理のようなもの。克服できれば、きっと新しい時代が来るはずだ。また、多くのビジネスマンが不良債権という過去のしがらみに囚われ、言い訳と先送りに汲々としているようにも見えた。「不良債権処理は経済問題というより人間の解放のためのものだ」、当時そんなふうに政治家に必要性を訴えたりもした。
──その後については、誰もが知っているとおり。2000年代後半までに不良債権処理は決着した。しかし、日本社会にダイナミズムが回帰したとはとても思えなかった。それからは、日本社会の周期的なリズムというより、グローバルな変化の影響がずっと強く働いていると感じていた。
第3世代AIとの出会い
2012年ごろだっただろうか。変化の兆しはないものかと思いながら過ごしていたとき、AI研究者の松尾豊さんに出会った。松尾さんの専門であるディープラーニング技術について話を聞くうちに、単なるひとつの技術的なブレークスルー以上の意味があるように感じられた。私が官僚として仕事をしてきた平成の時代は、ポストモダンと評され、「決定的なことはもうない」とも言われた。しかしいままさに「決定的な変化」が起きようとしている、そう直感的に思った。そして、その意味を深く探究したいとも思うようになった。ほどなく新しいAIはメディアを席巻するようになり、松尾さんもあちこち引っ張りだこになった。
ここで簡単にAI開発の歴史を遡ってみたい。2010年ごろ以前のAI開発は二度のブームと「冬の時代」を過ごした。第一世代のAIは人間の与えた論理に則って推論させること、第二世代のAIは専門家の知識を教え込むことをそれぞれ重んじて開発された。しかし、どちらもなかなか成果をあげることはできなかった。きわめて限定的な状況でしか問題を解決できない。知識を学ばせるコストは膨大なのに、教えられたこと以外は答えられない。そんなハードルを乗り越えられなかったのである。
これに対して、現在開発されている第三世代のAIは、まったく異なる考え方で開発されている。脳を模したニューラルネットワークに、ディープラーニングの「ディープ」にあたる階層構造を与えたうえで、大量のデータからAI自体に学習させようという発想だ。
その学習方法は非常に独特である。それまでのような、人間がトップダウンでロジックやルールを教え込むような手法とはほとんど反対と言ってもいい。例えば自然言語処理が急発達する背景には、「アテンション」あるいは「トランスフォーマー」という新しい学習のメカニズムがある。私なりにそれを説明すれば、「単語の気持ちになって考えてみる」ということだ。それはかつてのように文法や構文といった人間の理解するルールをAIに与えることとは異なる。例えば「哲学」という単語の気持ちになって考えれば、「デカルト」とか「理性」とは近くにいたいが、「パスタ」とはそれほどでもないだろう。そういう単純な語順とは違ういわば意味的な距離を計算する。大量の文章を読み込ませて単語と単語の距離感を学習させ、それをベクトル表現する。すると、単語が構成する多次元の意味空間のようなものができあがるわけだ。
こうした手法によって、第三世代AIは目覚ましい成果をあげるようになった。データから直接学習したことがない内容であっても、質問の文脈を読み解きながら回答を組み立てる「GPT-4」をはじめとする生成AI(Generative AI)は、すでに多くの人が知っているだろう。AIは複雑な情報の中からパターンを発見し、それをべつのコンテクストで適切に活用するようになったのである。
マルコフ・ブランケットの衝撃──階層性と創発性
私が第三世代AIに決定的な変化の可能性を感じるようになったのは、成果や手法を知ったことだけが理由ではない。さまざまな理論を参照すると、そのメカニズムはAI以外にも広く共有されていて、そう考えることによって我々のこれまでの世界像を大きく変えると思ったからだ。
なかでも衝撃を受けたのは、「マルコフ・ブランケット」という概念である。マルコフ・ブランケットは、元々はAI研究者のジュディア・パールが考案したベイジアンネットワークの一種である。ベイジアンネットワークは、事象同士の確率的な関係を記述したもので、AIによる機械学習やディープラーニングを支える重要なモデルのひとつである。それを言語に当てはめれば、先の比喩のように、単語を近いものと遠いものとに分け、グループ化するための手法だとイメージしてほしい。私がなにより惹かれた理由は、これを脳神経科学者のカール・フリストンが応用し、生命一般に対して適用したからだ。
フリストンは、マルコフ・ブランケットを応用して、生命体が環境とのあいだで行う「局所的な作用」を説明する。局所的な作用というのは、私たち人間の例で言えば、家庭や職場などの身近な出来事には敏感に反応するのに、宇宙の果てで起こる出来事は気にも留めないようなことを指す。そして、局所的な作用には、周辺環境についての予測や推論と、周辺環境への働きかけの二つがあるとされる。
ではなぜそれが寝るときにくるまる毛布のようなもの、つまり「ブランケット」と名付けられるのか。それは、周辺環境を予測しようという働きが、予測の対象である環境としての「外部」と、予測する自分としての「内部」とを分けるように作用し、そのあいだに「仕切り」すなわちブランケットが生ずるからである。生命体の基礎にある細胞膜の発生は、そのように説明される。予測しようとするから環境と自分が別物として認識され、あいだに仕切りが生まれる、そう考えるマルコフ・ブランケットという発想は、何かを「知る」ということと、何かが「ある」ということが裏表になった世界観を示唆しているのである。
また、細胞などが外部環境を予測するということは、外部環境を個別の感覚データの単純な集積ではなく、パターンとして認識していることになる。パターン化できないと、つねに一回限りの新しいこととしてしか認識できず学習にならないからだ。フリストンは、生命体は環境に対応する「生成モデル」を予測のために形成し、誤差をできるだけ小さくするために、つねにデータに照らしてモデルを修正していると考える。生命体の基礎メカニズムと第三世代のAIのメカニズムとがそっくりなことがわかるだろう。
それだけではない。彼は細胞が器官を、器官が人体を構成するといったように、システムがより上位のシステムをつくりだすプロセスにも着目した。そしてそのプロセスは、マルコフ・ブランケットを内包するより包括的なマルコフ・ブランケットを生み出す、マトリョーシカのような構造なのだと考える。あるレベルのシステムが複数組み合わさるなかで、周辺環境の認識と適応に役立つより上位の階層のシステムが確立される。エマージェンス(創発)と呼ばれる現象である。そのメカニズムがあることで、世界の複雑性が増し、同時に複雑な秩序に対応することが可能にもなるわけだ。
このようにマルコフ・ブランケットは、AIと人間の知能、さらには生命体を貫いて説明することが可能な原理であり、第三世代AIはまさにそのメカニズムを体現しているのではないか。そう考えるようになったのである。
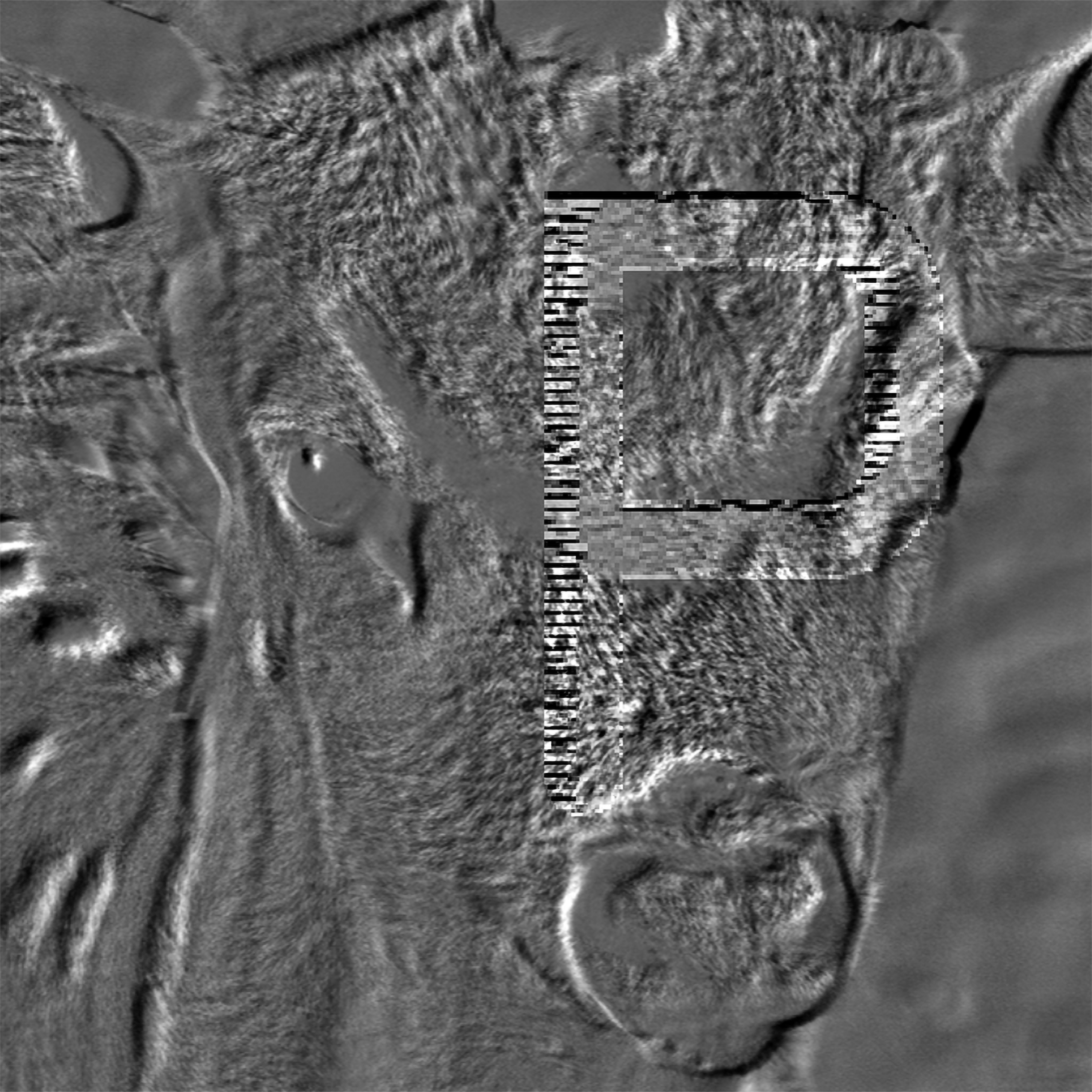
強い同型論──環境適応とパターン
ディープラーニング技術を背景にした第三世代のAIは、大きな世界観の変化をもたらしつつあるのではないか。強いインスピレーションを受けた私は、官僚として働く傍ら、先の松尾さんにくわえて経済学者の小林慶一郎さんを誘い、一冊の本をつくることにした。2020年に出版された『相対化する知性』である。同書で私は「強い同型論」という一種の世界観を提示している。これはマルコフ・ブランケットのメカニズムをもとに、AI開発の進展がもたらす世界認識の変容を描いたものだ。
では、何と何が同型なのか。まず、先ほどマルコフ・ブランケットの説明を通じて述べたように、AIの使っているメカニズムと生命体の基本メカニズムとは同型である。それだけではなく、人間の知能、とくに人間はどうして言語を使って世界を認識することができるのか、ほかの動物にないその能力はどこから来るのか、という問いとも関わっている。参照するべきは、近年行われている、AIの学習メカニズムを使って人間の知能の獲得過程を検証するという研究だ。UCバークレーのアリソン・ゴプニックがその中心人物だが、彼女によると、幼児は言語を学習する以前に環境をパターン化、抽象化して認識するフレームを身につけているとされる。第三世代のAIが示していることと同じように、人間の知能の基礎には、言語や論理の獲得より前に、局所的に認知された感覚データを使ったパターン認識の学習があるということだ。つまり、人間の知能と生命体、AIが同型のメカニズムだということになる。
次に、マトリョーシカのような構造についてだ。フリストンが言っているように、細胞から器官、人体へとより複雑性の高い仕組みが形成されるが、それは同じマルコフ・ブランケットのメカニズムが繰り返される中で、より高次なレイヤーが創発される階層構造だと理解できる。そんなたびたび現れる階層的で創発的な存在のありようを同型であると表現している。
最後に、「知る」と「ある」が同型だということだ。この点は哲学上の唯名論と実在論の論争、つまり人間が対象を認知するからそれがあるように見えるだけなのか、それは本当にあるのか、という論争とも関係する。マルコフ・ブランケットのスタートラインは、内外を区別する境界である。もし何かが「ある」なら、生命体と環境とは区別が可能なはずである。反対に、もし外部環境と完全に同期していたとしたら、その区別は不可能で、「ない」ということになる。その内と外とを分ける仕切りが、細胞であれば細胞膜である。同時に細胞膜は、外部環境のデータを感知して予測を行う機能と外部に働きかける機能を果たす。それを通じて細胞の内部は外部環境の「サプライズ・ショック」に晒されず、秩序が維持される、言い換えれば、エントロピーが増大しないということになる。つまり、生命体が環境から区別可能な存在として「ある」ことと、生命体が外部環境について「知る」ことはひとつのメカニズムの裏表になっている。そのような意味で、生命体においては、「ある」ことと「知る」こととは同型なのである。
これらの特徴をもつ「強い同型論」から、どのような世界像が得られるのか。第一に、物心二元論ではないということだ。「ある」ことも「知る」こともひとつの自然的な過程の中にある。第二に、要素還元主義ではないということである。我々が生きている世界ではさまざまなパターンが生まれ、階層的に創発が繰り返されることでより複雑なパターンと秩序が生じる。大数の法則のように要素のランダムな運動の中で偶然に秩序が生まれるということではない。いわば秩序から秩序が生じるという考え方だ。第三に、計算的な世界観である。生命体は環境の変化を予測し、そのモデルを計算して生成することで秩序を維持している。生成AIが人間との対話の中で行っている振る舞いと同じである。第四に、関係的な世界観である。パターンの発生はあくまで何かが何かと関わることで生まれる。細胞が環境と関わり、私があなたと関わることで、お互いをパターン認識する。第五に、実在論的な世界観である。パターン認識が成立するのであれば「それは本当は「ない」のではないか」という設問はおそらくあまり意味がない。「ある」と考えたほうが素直だ。
このような発想そのものは、マルコフ・ブランケットの登場以前から存在する。その例として、井筒俊彦が『意識と本質』で整理している東洋思想に共通する特徴を見てみたい。井筒は近代以前のイスラーム哲学や、宋学/朱子学を取り上げながら、とくに本質の実在を肯定する立場、例えば「猫」というパターンは実在するという考え方に着目して分析を進める。そして、そこに意識を一層だけの表層的な構造ではなく多層構造として捉えるという特徴を見出している。まさに実在と階層性とがセットになった考え方である。また、禅の思想にみられる「縁起」という概念は、しばしば「無」と結びつけられてきたが、それは本来であれば自己分節して経験的世界を構成するダイナミックな過程全体として捉えるべきだという。簡単に言えば、「無」ではなく、ダイナミックで流動的な「有」から考えようということだ。「強い同型論」は、階層性や関係性を分析して実在論に至ろうというタイプの東洋哲学と響き合っている。
こうした世界観は、人間だけが全体を特権的に認識できると考えるような、近代的な思想とは大きく異なっている。たしかに人間は、宇宙の果てまでをも知ろうとする。しかし、本質的には個々の人間も人類も局所的に適応し、ある種のコンピュテーションを行っているだけで、すべての条件を計算し尽くせるわけではない。そういう意味で我々すべて根本的には世界内存在であって、ほかの生命体と同じである。
同型論が示す世界観は関係的なものだが、そのことは量子理論が示しつつある考え方とも通じている。例えば理論物理学者のカルロ・ロヴェッリの著書『世界は「関係」でできている』の世界観は、実在性を個体に還元しない。モノも人間も、ほかのあらゆる生命体も、それ自体で厳然と実在するのではなく、すべてそれがほかにどう立ち現れるかという関係性として説明される。これは量子理論で有名な二重スリット実験についての解釈とも関係している。つまり、人間の観測を含めたインタラクションから対象の特徴を説明しようとする考え方だ。こうした発想は、生命体は外部環境を予測しパターン認識しており、環境の側もまた生命体をパターン認識しているというマルコフ・ブランケットの示す考え方とも親和性が高い。「強い同型論」は、それらをつなげて解釈してしまおうという試みでもある。
そしてこの考え方は、なぜ世界には何もないのではなく、これほどまでの多様性や複数性が存在しているか、エントロピー増大則があるにも関わらず、生命、社会、情報までを貫く複雑化がなぜ生じ進化するのか、このような問いに答えるアイデアでもある。
人間とAIをともにガバナンスする
官僚として政策を構想するには、歴史の流れを捉える必要がある。そんな考えを最初に述べた。その中で出会ったのが第三世代AIであり、それを元に展開したのが「強い同型論」という世界観である。では、この考え方は私の官僚としての仕事にどう影響したのか。
ちょうど『相対化する知性』の原稿を執筆していたころ、私は経済産業省でデジタルとデータ政策を担当するポジションに就いた。執筆にあたって考えたことと政策の検討とはお互いに影響を与えているが、とりわけ政策面の発想でこの世界観と一番関係しているのは、「ガバナンスについてのアプローチが大きく変わる」という考えだと思う。当時これを「ガバナンスイノベーション」と名付けた。
簡単に言えば、第三世代のAIがそれ以前のAIと異なるように、「固定的なルールを適用するガバナンス」から、「環境適応のためのパターンを発見し進化させていくガバナンス」に変えていくべきだということだ。また、要素還元主義ではなく関係的な世界観だということも述べたが、これは企業などの組織の境界は固定的に厳然とあるのではなく、ほかの主体との関係性の中で柔軟に設定されるというガバナンスの発想につながる。PDCA的に最適なプランニングを追求するのではなく、OODA的に環境の観察からスタートするガバナンスへの移行だと言ってもいい。フリストンのいう生命体の原理と同じように、環境に対する局所的な認識と適応、そしてその進化から考える、という発想だ。このようにひとつのメカニズムで考えることで、人間とAIとを同一のフレームワークにおいたガバナンス、そして共存のあり方を考えることができる。
当時、日本がG20を主催する番となり、私はデジタル分野を担当した。デジタルという各国の関心が非常に高く利害対立もある分野で、米欧中印露を含む20カ国が合意できるような前向きのアジェンダを日本が示す必要があった。そのときに当時の安倍晋三総理大臣のもとで進めたのが、「DFFT」(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)の構想である。DFFTというフォーミュレーションは、各国間の「落としどころ」を意識したものではあるが、あえて「強い同型論」の世界観と近づけて説明すれば、「トラスト」という言葉を選択したことと関係がある。
グローバルなデータ流通の安定化を進める定石は、国際間でルールをつくることである。約束事をつくって、特定の局面に対して適用する。必要に応じて、その約束事をアップデートする。もちろんこれは間違いではない。けれども、トラストにはそれとは少し異なる語感があると思っている。これは日本語で言えば信頼である。「あの人は信頼できる」というとき、ただ単に「約束事を守ること」を意味しているわけではないだろう。むしろ、約束事の前提から逸脱するような、予測不可能の事態が起こったときに、それでも「期待を裏切らないような対処をすること」が信頼の本質ではないか。信頼はルールを超えた概念なのである。
当時の私の頭の中ではDFFTにおける「トラスト」と、「ガバナンスイノベーション」とがセットになっていた。ガバナンスイノベーションが目指したものは、一般性の高いルールによる一律の規制というよりも、部分における適応の努力の総体として起こる創発を組み込むガバナンスの発想だからである。
この「ガバナンスイノベーション」という発想は海外ではそこそこ評判になり、2020年1月のコロナ禍直前にOECDがパリで大規模な会議を開催してくれた。懐かしい思い出だ。ただ、ガバナンスイノベーションという言葉は多義的でわかりやすくはない。そこで当時はリンカーン大統領のゲティスバーグ演説をもじって説明した。つまり、ガバナンスイノベーションには、governance “of” innovation, governance “by” innovation, governance “for” innovationという3つの側面があるということだ。それぞれ「AIによるイノベーションを統治すること」、「統治にAIなどの技術を活用すること」、「AIによるイノベーションを促進する統治とすること」を意味している。
権威主義のAI、多元主義のAI
もうひとつ、同じころに官僚として注力したのは「アーキテクチャ」を政策の中核に置くということである。具体的には「デジタルアーキテクチャ・デザインセンター」という、企業間のデータ共有連携の仕組みや、規制に関係するアーキテクチャをデザインする組織を独立行政法人情報処理機構(IPA)の中に立ち上げた。
これもガバナンスと関わっている。端的に言えば、デジタルやAIの世界では、ルールや法をつくったり改正したりするだけでは問題は解決しない、ということである。インターネットは分散的なシステムであると言われる。しかしそうなった理由は「分散型にしろ」というルールがあったからではないし、もしそういうルールをつくったとしてもそれだけでは実現しなかっただろう。それは「分散型のアーキテクチャ」をデザインする取り組みがあって初めて実現される。
個人情報保護の意識が強いEUでは、国境を超えたデータの流通の制限を含むGDPR(General Data Protection Regulation:EU一般データ保護規則)という規制をつくっている。個人的には、この人間中心の理念を深く尊敬する。しかし同時に、当時EUの人たちにDFFTの構想を説明する中で、こうしたアーキテクチャの重要性を訴えた。つまり、欧州の理念を実装するためにも、その要求を充たすアーキテクチャの提案が必要で、それを多国間かつ官民で取り組んだほうがいいのではないかという話である。もちろん私に言われずともそう考えていた欧州の人も多いだろうが、これによって関心をもってもらうことができ、それがOECDの大会議にもつながった。
アーキテクチャをめぐる議論は、『相対化する知性』の世界観とも関係している。AIがもたらす未来像を描くときに、典型的にイメージされるのがビッグブラザー的な監視社会のイメージである。権力者が巨大な計算マシンをつくって人々を支配する、そのマシンが暴走して取り返しのつかないことになる。そんな強権的で中央集権的な印象は根強くあるだろう。古典的なSFに登場するマザーコンピュータを思い浮かべる人もいるかもしれない。現実社会におけるAIのイメージは、物語作品での描かれ方と深くかかわっている。そういうディストピアにならないという保証はない。
同時に、私自身は多元主義者だから、AIは本来多元的な存在であり、そう活用してこそ可能性があると信じている。それは私が民主主義の国に生きているからというだけのことではない。すでに紹介したように、第三世代AIは、決まった論理に基づく推論や、人間が教え込んだ知識をもとに最適解を出そうとするこれまでのAIとは異なり、人間の脳を模した分散的な情報処理を基礎において、ミスを起こしながらもそれを修正して学習するアーキテクチャを採用している。人間が細胞一つひとつに指示をしているわけではなく、その全体をコーディネーションしているだけであるように、AIそのものにも分散的で多元的な性質があるはずなのだ。現代的なアーキテクチャというアプローチには、このように共通性とオープン性、多様性と進化とを両立させる発想があると思う。
『相対化する知性』で訴えたかったのは、いま発達しようとしている第三世代AIのメカニズムは、局所的な作用とパターン認識、そこからの創発の繰り返しであり、本質的に多元的なものだということだ。またそれは「世界の外側に立って最適解を計算しつくことはできない」という世界観でもある。
オーストリアの経済学者であり思想家のフリードリヒ・ハイエクは、1945年に「社会における知識の利用(The Use of Knowledge in Society)」という有名な論考を書いている。これはすべての知識を中央に集中させても解決できない問題があると指摘し、知識の分散化やそのコーディネーションの重要性を訴えることを通じて、市場メカニズムの優位性を説いたものだ。おそらく現代は、この「市場」を超えた分散的で多元的なシステムとガバナンスの可能性が問われている時代なのだと思う。
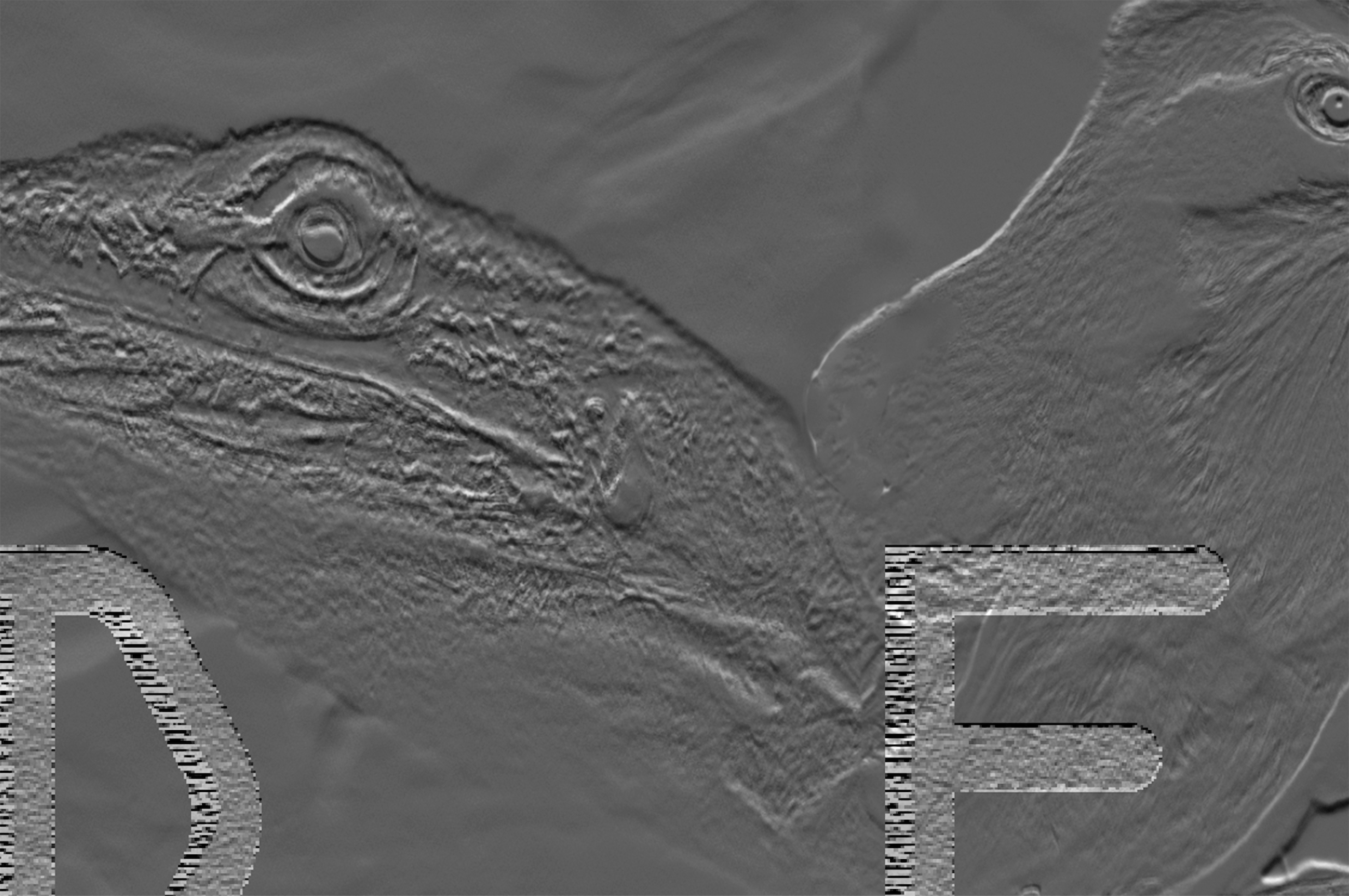
インディア・スタックの理想
ではそうした未来をどうイメージしたらいいか。物語作品ではないものの、ガバナンスイノベーションのイメージを伝える事例がある。インドが推進している「インディア・スタック」というデジタルプラットフォームだ。一般化してデジタル公共基盤(DPI)と呼ばれることもある。
インディア・スタックは、4つのレイヤーからなる構造をしている。一番目は基礎となるアイデンティティ(本人確認)レイヤーで、アダハーあるいはアダールと呼ばれる。顔や虹彩、指紋といった生体情報を使って個人の認証を行うものだ。普及するのに10年近くかかったが、この仕組みができたことで、個人が銀行口座を開設するコストは劇的に下がり、口座の保有も進み、給付金なども受給できるようになって、社会的なインクルージョンが進んだ。給付金も「爆速」で給付できるようになった。政策決定から2週間で5億人に給付したこともあったという。公務員の出退勤管理にもこれを使っていて、「幽霊公務員」がいなくなった。
二番目が決済レイヤーである。銀行口座を使いつつそこへのアクセスをオープンにすることで、新興の決済プレイヤーが参入しやすくするなど、金融サービスの急速な普及と革新が起きた。三番目がデータマネジメントレイヤーである。個人が公的な証明書などのデータを自分で管理し、コストと手間をかけずにさまざまな申請に使える。利便性とデータ主権を両立させる仕組みである。四番目はそれらの上に乗る各サービス分野のアプリケーションだ。教育分野では、学習、教育、管理のプロセスをモジュールに分けて提供し、それを組み合わせて生徒、教師、管理者がカスタマイズできるようにしている。例えば、科目履修、卒業資格などの取得したステータスを確認するためのモジュール、教材コンテンツをオープンな情報から組み合わせて制作できるようなモジュールといった具合だ。ちなみにこのステータス確認モジュールは、コロナ禍でワクチン接種の管理に転用され、接種の早期展開に貢献している。
このような詳細を当時は知らなかったが、官僚時代に私はこの仕組みに強い興味を抱いて、インドの省庁を訪ねてこのプラットフォームについて質問して回った。2018年のことだ。しかし、カウンターパートからはあまり明確な答えがなかった──半年後に再訪すると、今度は庁舎内にインディア・スタックコーナーができていて「ぜひ見てくれ」と言われたので、少し可笑しかったけれども。しかし、これもわからない話ではない。じつはインディア・スタックの開発を主導していたのは政府内部の人間ではなく、iSPIRTという非営利のシンクタンクだったからだ。そして私はその人たちとも出会うことになる。
iSPIRTのエンジニアが語っていたことで印象的だったのは、自分たちのエコシステムをもたなければならないという強い危機意識だ。インド国内に適切なプラットフォームがなければ、インドのエンジニアにどんなに高い技術力があっても、海外プレイヤーに取り込まれてしまう。実際のところ、iSPIRITのチームにはGAFA出身の世界レベルのエンジニアがおり、その言葉には説得力があった。
組織図から見取り図へ
インディア・スタックのような考え方は、これまでの日本の行政やビジネスのアプローチとはまったく異なる。そしてそのアプローチの大胆な転換がデジタルトランスフォメーション(以下、DX)の成否と深くかかわっている。そのひとつは、政府の構造をレイヤー構造にする、つまりはAmazonのクラウドサービス「AWS」のような構造にしてしまうということだ。それは政府を省庁別、部局別、国や自治体別といった縦割りでピラミッド型の分担構造から考えるのではなく、システムやプラットフォームがベースにあったうえで、そこに分野別のアプリケーションが乗ると考える横割りの発想であり、それらを連携させるための相互運用性をもたせた規格や仕様が重要な構成要素になる。そのためには、政府の機能を横串でレイヤー化し、組み合わせの自由なモジュール化をする必要がある。先ほど説明したインディア・スタックの構造はまさにそれだ。
これまでの縦割りの発想だと、教育で言えば、初等教育、中等教育、高等教育と分け、次に教科に分けて、それぞれに教科書と副教材とテストをつくって……という発想になる。インドで取り組まれている教育のモジュール化は、それとはまったく異なる発想であり、そもそも学校教育でも高等教育でも職業訓練でもリスキリングでも同じモジュールを使い回すという発想でできている。つまり、既存の組織図から考えないということだ。我が国では民間でも、領域を超えたプラットフォームの設計に成功している例は多くない。AI活用を目指すと語る企業も、部署ごとに縦割りでまずPoCをやってみようとなりがちだ。革新的な技術であっても、既存の組織図の中に閉じ込めていてはポテンシャルを発揮できないだろう。
そんな中にあって、縦割りの組織図にとらわれず成果を上げているDXの事例をお話ししよう。ひとつは、私も関わっているIGPIグループが関係する「みちのりホールディングス」による、地方バス会社の経営改革の取り組みだ。地方のバス会社の多くは、人口減少によって経営が悪化している。運転手をはじめとする担い手不足も深刻だ。バスの本数が減ったり、路線がなくなったりすれば、買い物や病院へ通院するためにバスを求める高齢者など地域住民は、生活そのものが成り立たなくなるかもしれない。
その経営再建のためにまずとられたのが、横串の経営である。みちのりホールディングスは東北地方を中心にいくつかのバス会社を経営している。それぞれのバス会社が立地する地域は、地理的条件、人口密度、降雪の有無などその特徴はまちまちである。そうなると経営はそれぞれべつに、と考えがちだ。しかしみちのりホールディングスは違うアプローチをとった。バス会社の経営を分解すれば、車両の調達や安全対策、利用増のための新企画など8つほどの要素に因数分解できると考えた。理屈はインディアスタックと同じである。そしてそれぞれの要素について横串でベストプラクティスを導入する。そうすることで経営改善が進んだ。
その延長線上にデジタル技術を導入した。ダイナミックルーティングと呼ばれるAI技術を横串で各社に導入したのである。いわば「どこでもバス停」のようなもので、路線を固定せず、乗客の時々のデマンドに合わせてルートを変える。通学の多い時間帯、通院の多い時間帯、買い物の多い時間帯に合わせてルートを変えるわけだ。
そうなると経営形態にも変化が現れる。地方では、病院向けの福祉バス、スクールバス、路線バスを別々に運用することも多いが、ダイナミックルーティングを使えばその必要がなくなる。また、たまには自宅の近所に寄ってくれるのであれば、荷物の集荷や配達にも使える。いわゆる客貨混載である。こうして路線バスというサービスがAI活用を経由してべつのサービスに転化していく。その先にあるのがMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)である。
もうひとつの例は、愛媛県にあるHITO病院の取り組みである。この病院は、2018年に医師や看護師のコミュニケーションツールをiPhoneに共通化した。もともとはほかの病院と同様にPHSやパソコン、日報を通してやり取りしたり、電子カルテにアクセスしたりしていた。このようなやり方だと、忙しく診察をおこなう医師に対して看護師は電話をかけづらく連絡が滞ると聞いた。
しかし、iPhoneに切り替えたことで、コミュニケーションは劇的に変わった。チャット機能を使えば読めるときに読んでくれるという安心感から、積極的にコミュニケーションが取られるようになる。また、チャット機能だとべつのチームの医師や看護師にも同時に伝えられるので、コミュニケーションが横割りになり、チーム編成も柔軟に変更しやすい。さらに、やり取りが自動的に保存されてあとから見ることができるので、いちいちすべてを日報に書くために残業する必要もなくなる。また、一人一台はなかったパソコンを確保するべく院内を歩き回る必要もなくなったので、仕事中の歩行距離が大きく減った。こうしたことの積み重ねで、勤務環境が劇的改善し、看護師の離職率がゼロになったという。入り口としてiPhoneの導入があったものの、大事なのは、その結果として医師や看護師のコミュニケーションが変わり、縦割りでなくなり、組織風土まで変わったということだ。
ただし、急いで付け加えておけば、本当の意味での病院改革は、経営陣やスタッフの努力だけでは難しい。見取り図をさらに広げようとしても、制度の壁にぶつかってしまうからだ。医師や看護師は、それぞれ厳密に職域が決められており、究極的にはその業務範囲から自由になれない。ほかの分野でもそうだが、デジタルを真に活かすためには、医師や看護師、薬剤師を含む資格や業務範囲の柔軟化、そのための規制改革が必須だというのが私の意見だ。
ピラミッド型からレイヤー型へ
かれこれ30年くらい、社会学者の大澤真幸の本をよく読んでいろいろなことを学んできた。大澤の代表的なコンセプトに「第三者の審級」がある。物事の価値や善悪に関する規範の前提をつくりだす、超越的な他者を指すものだ。大澤の著作では、その概念を使って近代や資本主義のメカニズムについて説明し、また、キリスト教や絶対王権の歴史を辿ってその生成のプロセスを解明している。
私なりに「第三者の審級」のメカニズムを単純化すれば、それは未来に理想的な、あるいは普遍的な到達点──すべてが充たされる点を仮構し、それに向かって運動するということだ。現実世界ではそれに代わる中間目標、例えば欧米列強や先進国に追いつくとか、ユニコーン企業になるとかを置いて、それを入れ替えながら運動することで、社会や個人の人生の方向が定まり、安定する。いわば頂点を抽象化して未来に置いた、ピラミッド型の社会モデルだと言えるだろう。
明治維新以降、日本はこのような社会モデルで発展してきた。明治なら司馬遼太郎『坂の上の雲』の時期、昭和なら高度経済成長の時期は、このモデルがとくに効果を発揮していただろう。欧米に追いつけ、追い越せ。生き残るためには、課題を単純かつ具体的なものとして捉え、トップダウンで進む必要があった。柄谷の明治=昭和平行説は、それが達成されては緩む、繰り返しのプロセスを捉えたものではないか。
もちろん「第三者の審級」という大澤のアイデアは、日本固有の仕組みを説明するものではない。近代や資本主義一般の性質を説明するためのものだ。では、これが悪く機能するとどうなるか。未来の到達点や理想を固定してしまうと、そこに向かう動きだけが許容され、それから逸脱する動きは排除されるという意味で、全体主義的で非多元主義的な社会になってしまう。また、目標に近づくことに成功したとみなされたプレーヤーに富の集中が起きる。まさにいま資本主義に突きつけられている問題点である。
第三世代のAIがもたらす世界像には、その転換の契機があるのではないかと私は考えている。2021年に出版された『DXの思考法』において、ピラミッド型の社会モデルを変えるという提案をしたが、それもこのことと関係している。最後に、この話をしてみよう。

ところで、「第三者の審級」のメカニズムを全体主義のような方向に悪く作用させてしまう原因をつくった思想家として、ヘーゲルが取り上げられる場合も多い。彼の『歴史哲学講義』などを読むと、西欧近代という理想に向かって世界史が単線的に描かれているようにも見える。先ほど紹介した大澤は『〈世界史〉の哲学 現代編1』において、そんなヘーゲルの思想についてべつの読み取り方ができると論じている。
その糸口は、ヘーゲルの「具体的普遍」という考え方にある。大澤は具体的普遍について、数学の集合論では禁止されている「ラッセルのパラドックス」、つまり「自分自身を要素として含む集合」という問題を解決する考え方として取り上げる。集合Aには要素としてa,b,cがあると考えるのが通常だとして、集合Aの中にa,b,Aがあると考えるとどうなるだろうか。詳しくは同書を参照してほしいが、これを認めてしまうと、その概念が集合のうちにあるのかないのか未決定の状態になってしまう。大澤によれば、ここで具体的普遍という考え方を使うと、類的概念Aがべつの類的概念Bに転換するプロセスとして捉えられるという。同時に、その転換は類的概念Aそのものの内部から自律的に生じるとされる。具体的普遍にあたるのがAであり、Aは類的概念に属するとともに具体的個物でもある。
この大澤の議論は、ピラミッド型の社会を変えることについて、どのような示唆を与えるだろうか。そのヒントは、先ほど紹介したみちのりホールディングスによるバス会社のトランスフォメーションにある。みちのりには個別のバス会社、例えば岩手県北バスや福島交通が属している。そしてバス会社というビジネスを生き残らせるために最大限努力し、人口減少という課題に対応して、これまでのところ成功してきた。その結果起きたことは何か。それは、路線バス以外の機能を有し、貨物も運ぶようなビジネスに転換するということである。いわば「バス会社を超えるバス会社」になったわけである。これはまさにバス会社という概念Aからバス会社を超えるバス会社概念Bへの転換、すなわちトランスフォメーションだ。しかもその転換は、個体としてのバス会社がそのビジネスを守る取り組みの中から自律的に生じているのである。さらに言えば、トランスフォメーションを可能にしているのは、技術でいえばダイナミックルーフティングというAI技術であり、経営で言えば、ピラミッド型ではなくレイヤー型でバス会社を捉えようというアプローチなのである。
このような具体的普遍をめぐる議論は、「強い同型論」の世界観やマルコフ・ブランケットのモデルとも関係している。個体と環境との局所的作用が組み合わさることで世界に安定的なパターンが生じるとする点や、環境に適応しながら新たなパターンや階層が創発されると考える点は、まさに具体的普遍と同じプロセスだと言えるだろう。ただしこの世界観では、「第三者の審級」のような最終的な到達点を仮構する必要がない。その一方で、同じことが繰り返される循環的世界観とも異なる。環境への適応のために当面必要な打ち手は選択可能で、レイヤーが増えることによって、より複雑で進化したパターンも生まれるからだ。同型論は、「第三者の審級」を必要としない一方で、循環的世界観とも違っているのである。
じつは社会学者のニクラス・ルーマンも、『社会システム』において、そのようなヘーゲル解釈を述べている。ルーマンは自身の理論について「単一の中心がコントロールし意味づける」という世界観とは異なるという。そして、着目する差異が各々世界を意味づけるという考え方──個別のシステムが周辺の環境に適応することと考えてもよいだろう──を採用すべきだともいう。そして未実現の第三の可能性群、つまりこれまでは選ばれなかったが、将来にはありうる可能性を含めることで、世界は初めて理解できるという考え方であるとする。ルーマンは、これこそが「弁証法」や「止揚」という概念でヘーゲルの言わんとしたことだと述べる。
大澤やルーマンのような、ヘーゲルとその弁証法の解釈を踏まえると、「強い同型論」をある種の社会思想としても展開できるかもしれない。人間もほかの生命体もAIも、等しく局所的な計算の繰り返しによってつながり、階層を積み重ねながらシステムそのものを自己進化させてゆく。しかしそこには計算可能な不動の最適点はないし、時々に行う選択や変化が絶対的な進歩かどうかを評価できる尺度もない。それにもかかわらず、「なんでもあり」のアナーキーとも違って、安定的なパターンと秩序が生まれる──。
もちろん「強い同型論」の世界観は、まだ完成しているわけではない。しかし、世上言われる「新しい資本主義」というものがもしあるのだとしたら、そのヒントは、AIやデジタル技術に対する深い探究と先人の思想を見直すことの中から生まれてくるのではないか。私はそんなふうに予感している。
西山圭太
にしやま・けいた/1963年東京都生まれ。東京大学未来ビジョン研究センター客員教授。東京大学法学部卒業後、通商産業省入省。オックスフォード大学哲学・政治学・経済学コース修了。株式会社産業革新機構専務執行役員、経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局担当)、東京電力ホールディングス株式会社取締役、経済産業省商務情報政策局長などを歴任。日本の経済・産業システムの第一線で活躍したのち、2020年夏に退官。株式会社経営共創基盤シニア・エグゼクティブ・フェロー。パナソニックホールディングス株式会社社外取締役。株式会社ダイセル社外取締役。著書に『DXの思考法』(2021年)、共著に『相対化する知性』(2020年)がある。

