
特集「東洋的|The East」の監修を務めた文芸批評家・藤田直哉による編集後記。2021年に刊行された著書『攻殻機動隊論』(作品社)では、同作をネット時代と並走し、濃密な相互作用を起こす現代日本文化史のメモリ(記録装置)そのもの=「未来を創造する伝統」と位置づけた。作品分析の根幹を成すテクスト論・作家論に加え、目まぐるしく変化する実社会の運動や政治、思想的な変遷、ネット/コンテンツカルチャー全般が人々の生活にもたらしてきた影響など、《攻殻機動隊》をフィクションと現実の境界面に立って鋭く検証している。
本特集の制作は、そんな藤田の『攻殻機動隊論』に、その増補版としてのコンテンツを加えるとしたら、というアイデアからスタートした。テーマに掲げた「東洋的」なものが秘めた可能性について、《攻殻機動隊》と著者とのこれまでの付き合いを振り返りながら、綴ってもらった。
目次
自己点検としての『攻殻機動隊論』
1995年。
小学6年生の僕はインターネットに出遭った。世界が拡張し、技術とともに自分自身の可能性がどんどん拡大していくように感じられた。同じ年に『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(以下、『GIS』)が公開される。物語の結末で、人工生命体と融合し、高度な次元へと移行する素子を見て、自分自身と重ねた。このとき、僕の目の前には広大なネットというフロンティアがたしかに展開されていた。
そして、飛び込んだ。
結果、そこにあったのは『GIS』で描かれていたような、スタイリッシュでロマンチックなサイバースペースなどではなかった。2ちゃんねるに象徴される匿名掲示板や、そこにおける露悪的な「本音」たち。人類が新たな次元に進化するという『GIS』の提示した期待とは裏腹に、人間が高度化した端末や回線を用いて行ったのは、ヘイトスピーチ、デマ、陰謀論、他者へのマウンティングやネットいじめであり、むしろ人間という存在の、進歩できない愚かさが前面に出てきたかのような現実があった。
2000年代になると、『攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX』の影響もあり、僕はネット内外の政治運動にコミットするようになる。既存のマスメディアとは違う、ネットというメディアがもたらした力が社会を革新し、正義と自由を増してくれるものと期待していた。コピーレフトやハクティヴィズムなどに共感し、それを信じて、戦った。
それらすべてが無駄だったのではないか、間違いだったのではないかという思いに囚われたのが、2017年ごろ。インターネットが変える新しい文化や、芸術や、政治を信じ、積極的にコミットしてきた自分自身のこれまでの行いに疑問を感じて、もはや鬱々とした状態になってさえいた。そうさせられるだけの惨状が、ネット上では展開されていた。
サイバースペースにおけるアナキズムやリバタリアニズムの価値観こそが、世界を悪くしたのではないか。「自由」への信仰こそが、ヘイトスピーチや陰謀論やデマの温床となり、暴力や死を生み出しているのではないか。IT産業への産業構造の転換が、既存の産業を破壊し、中間層を減らすことにつながったのではないか。その結果もたらされた格差の拡大が、人々の尊厳や生活を破壊したのではないか。世界を覆い尽くす「失望」が、現世の破壊を願うようなラディカルな陰謀論へと飛びつきやすい状況を助長しているのではないか。
僕はこれまでの自分の考えや行動を、総じて点検しなければならないと思った。そのために、自分に大きな影響を与えた《攻殻機動隊》の検証を行い、自分自身の考えと、同時代の思潮をもう一度考え直す作業に入った。その結果をまとめて、2021年に『攻殻機動隊論』という本を刊行するに至った。

西洋と東洋──根底に差異はあるのか
そのとき、それまで自分が無視したり、軽視してきた部分にこそ意識的に向き合うよう努めた。それは《攻殻機動隊》の中にあった、日本神話や神道、神秘主義、仏教などの主題である。1983年に北海道で生まれ、ゲームの発展やアニメーション文化の隆盛と並行して成長したニューメディア世代の僕にとって、それは古臭く感じられ、むしろ反発してきたものだった。しかし、それでは《攻殻》の半分しか理解できない。その茂みへと分け入って行くことは、既存のものを否定し、新しいものを肯定しながら、先へ先へと急ごうとする自分が見落としていたものに気づくプロセスでもあった。
能楽堂に繰り返し通い、神道やアニミズムの関連書籍を読み、実際に神社仏閣や聖地とされている山や森に赴いて歩き回った。そして少しずつ、神道や仏教の語っているもの、世界観を理解しようとした。そうするうちに、少しずつ自分の感覚が変わっていくことに気づいていった。
以前までの僕は、自我や意識や知性を重視し、論理や科学を尊重していた。世界が進歩していくことを強迫観念的に望んでいたし、観念や概念を重要視もしていた。自分自身の身体や生が、社会や、歴史や、自然とどうつながり合っているのか、それがいかに不可分な関係であるかなどということは、微塵も考えていなかった。
進歩の先の無限の彼方へと向かえば、救済されたり、ユートピアに辿り着けるのではないかという「幻想」に見切りをつけなければいけない。人間としての僕は、生命の連鎖の中でひとつの位置を占めた「通路」でしかなく、無限の彼方にも、神にも、ユートピアにも到達することはできない。そう認識することは、ただ老いて死にゆく身体をもった、大地に属した存在である自己を受容することでもあった。
すると不思議なことに、この死すべき身体、生命、自然に、ある神聖さのようなものが感じられるようになってきた。「無限の彼方」や「中心」にそれがあるから目指すというのではなく、いまここに実在しているすべての存在そのものに神聖さや霊性的なものがあるという感覚──これまで散々小バカにし、軽視してきた日本の土着信仰のような──であり、自分の身にほとんど初めて起こったことでもあった。
あるひとつの転向/回心を、自覚せざるをえなかった。
『GIS』と『イノセンス』のあいだにあったものはこれだったのか、と腑に落ちた。『イノセンス』は、デカルト的二元論やそれに基づく思考方法一般を否定するために、能を導入し、身体・環境・動物とが霊性においてつながり合っているような未来像を描いていた。それは高度化し、進化し、超越的な方向にひたすら向かおうとしていた『GIS』の素子に対する批評のようにも思われた。
身体を捨てて、情報や、抽象や、観念の世界に上昇していくことを重視する価値観。あるいは大地に戻る死すべき身体と、動物や自然に霊性があり、それらを肯定する価値観。そのような価値の根底部分での差異を、本特集では仮に「西洋」「東洋」と呼んでいる。生命や人類の存在意義、あるいはその思考法などにおいて、この世界にはどうにも異なる原理があるようだ。そのようなことに、謙虚にならなければならなかった。自分には何も見えていなかったのだ、という痛切な反省。
本特集も、その延長線上にあるものだと捉えてもらっていい。
「衝突」ではないやり方で
士郎正宗の漫画原作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』と『攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE』は、よく読むと、日本神話や仏教、アニミズムやスピチュアルな用語が頻出する。かつては読み飛ばしていたその意味を、本気で考えてみることにした。そこで理解されたのは、彼が仏教や日本神話で語られていることと情報理論などのあいだに、共通性や連続性を想像しているということだった。
実際に、本当につながりがあるのか、ないのか、僕には判断することはできない。しかしそこには、テクノロジーや制度といった外来の意匠を受け止めるときに、それを古来から続いてきた価値観や文化の延長線上で、心理的に咀嚼しようと努力した痕跡があると考えることはできる。平安時代には「和魂漢才」、明治時代には「和魂洋才」という言葉が使われていたが、《攻殻機動隊》は「和魂情才」とでも言うべきだろうか。それはテクノロジーによって不断に変化させられていく情報社会の中に、日本のスピリットがあり続けるという連続性の物語を、想像力のうちにつくり上げようとする努力のように思われた。
日本は近代化、第二次世界大戦後と、外来の文化や制度を導入しながら大きく変化してきた。そのとき同時に、それまでのアイデンティティや価値観を失うことの嘆き、あるいは変化の軋みが挙げる悲鳴すらも、芸術や娯楽などで表現してきたのではないか、と。
現在、巷ではAIによる第四次産業革命が謳われている。日本ではDXをはじめとする産業構造の移行に対する心理的な抵抗や、動きの鈍さばかりが目立っている。古くからある不合理な制度や慣習、価値観もいまだに多く残っている。古きに固執する者と、新しきに飛びつく者との分断は依然激しいままである。
きちんと先に進むために過去を受け継ぐこと。この「連続性」をつくり出すことこそが、未知の時代に進んでいくために重要なことではないかと思われる。これはきっと日本に限定的な課題などではなく、急速に変貌していくすべての社会に当てはまることではないだろうか。
過去と未来という時間的な連続性だけではなく、空間的な連続性をつくり上げようとした創造性も、《攻殻機動隊》のもつもうひとつの重要なポテンシャルであったと、僕は感じている。サイバーパンクというジャンルの始祖であるウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』は、日本のチバシティから始まった。映像におけるサイバーパンクの始祖であるリドリー・スコットの『ブレードランナー』は、放射能の雨をネオンサインが照らす、日本的な街へと変貌を遂げたロサンゼルスが舞台である。
サイバーパンクというジャンルの背景には、黄禍論とジャパンバッシングがある。アメリカが日本化(アジア化)してしまうことに対する恐怖と抵抗が、当時はたしかにあった。サイバーパンクそれ自体がアジア化してしまう西洋の未来を考察するジャンルであり、そこにはそれを受容できるか否かの葛藤も見られた。レプリカントなどの「ニセモノ」と「人間」の違いという主題系にも、アジア人と西洋人の寓話を読み取ることもできる。キリスト教的背景や西洋哲学の伝統、サイエンスの思想を共有しないのに、技術を使いこなしながら高度化していった日本を、どう受け止めるべきかという心理的課題が、その背景にあったと考えることも可能だ。
むしろサイバーパンクは、西洋と東洋を折衷したジャンルであるということに大きな価値がある。より抽象的に言えば、原理レベルで違う文化・文明を折衷し、より高次のあり方を創造しようとしたという点にこそ、このジャンルを積極的に評価できるポイントがあるように思う。
文明を衝突させる、ではないやり方で。相互を理解し、原理レベルの違いまで含めて折衷させたかたちで、新たな文化を創造しようとする努力──これが必要なのは、何も西洋と東洋だけに限った話ではない。アラブだってそうであろう。「文明の衝突」をしている場合ではないのだ。
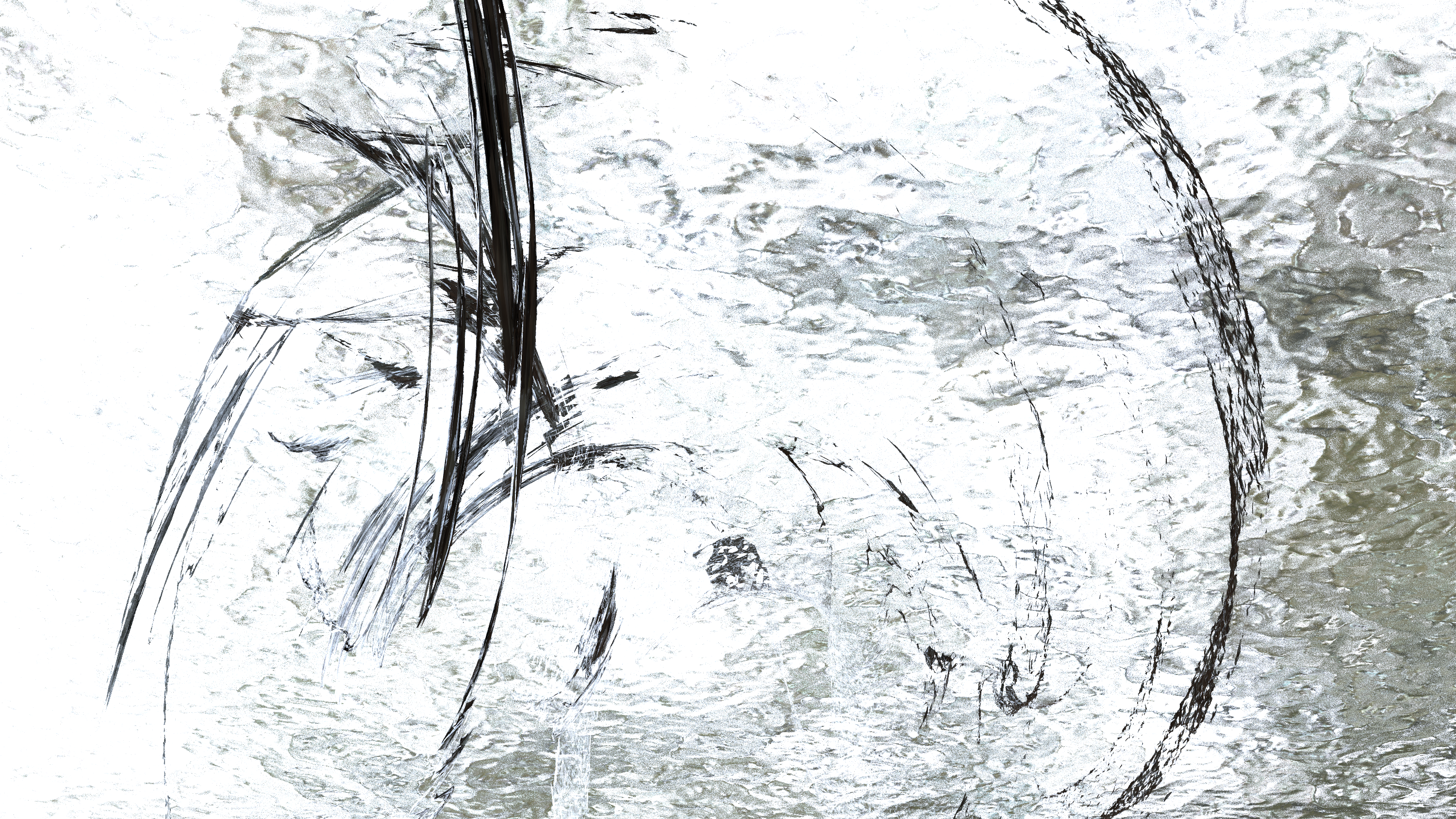
調和した未来
本特集の監修を依頼され、主題を「東洋的|The East」と提案したときに考えていたのは、このようなことであった。
AIに関連する書籍を読んでいると、シリコンバレーの経営者やMITの教授らが書くものと、日本の学者や開発者が書くものとのあいだには、傾向の違いがあるように思われたのだ。アメリカでは、生命とは情報であるという認識や、身体を捨てることにポジティブな論調が多いように感じられる。対して日本のAI論では、生命とは身体と不可分な関係であるとする考えがベースにある。比較文化的な言い方にはなるが、AIをめぐる言説ひとつとっても、やはりその地域の文化や価値観が反映されており、開発や研究、現実化の方向性もまた異なる道を進んでいるのではないかと思われた。
そのような仮説に基づいたうえで、「東洋的AI」の可能性と限界を探ってみたい──というのが、この企画における、監修者としての僕の内在的な動機であった。
本特集は英訳され、世界でも読まれる機会を得たことを嬉しく思う。あえて「東洋的」という特集を冠したことにも狙いがあるわけだが、実際の研究・開発現場においても、その原理の違いを見つめ直し、相互理解のうえで折衷されていくことを期待したい。より高次の段階に進むかどうかは、そのとき明らかになるだろう。
かつてスティーヴ・ジョブズが禅に傾倒していたことはよく知られている。シリコンバレー精神が、世間で言われているような「ヒッピーとヤッピーの野合」から生まれたとすれば、そのような自由な精神、愛と平和を願う気持ちの中から、世界を変えるような創造性が生まれてきたはずだと、いま一度その足場をたしかめるべきではないだろうか。「東洋的」と掲げたが、東洋も多様であり、東洋以外にも様々な文化が存在する。集団も個々人もそれぞれ違う。それらすべての文化を受け入れて広がる、新しい、高次の多元的な文化の創造に寄与することで、衝突や争いのない調和した未来の構築を夢想する。
さて、そこに可能性があるのか、否か。
判断するのは、あなたである。
藤田直哉
ふじた・なおや/批評家。日本映画大学准教授。1983年、札幌生まれ。東京工業大学社会理工学研究科価値システム専攻修了。博士(学術)。著書に『虚構内存在』『シン・ゴジラ論』『攻殻機動隊論』『新海誠論』(以上、作品社)、『新世紀ゾンビ論』(筑摩書房)、『娯楽としての炎上』(南雲堂)、『シン・エヴァンゲリオン論』(河出新書)、『ゲームが教える世界の論点』(集英社)、『百田尚樹をぜんぶ読む』(杉田俊介との共著、集英社新書)ほか。

