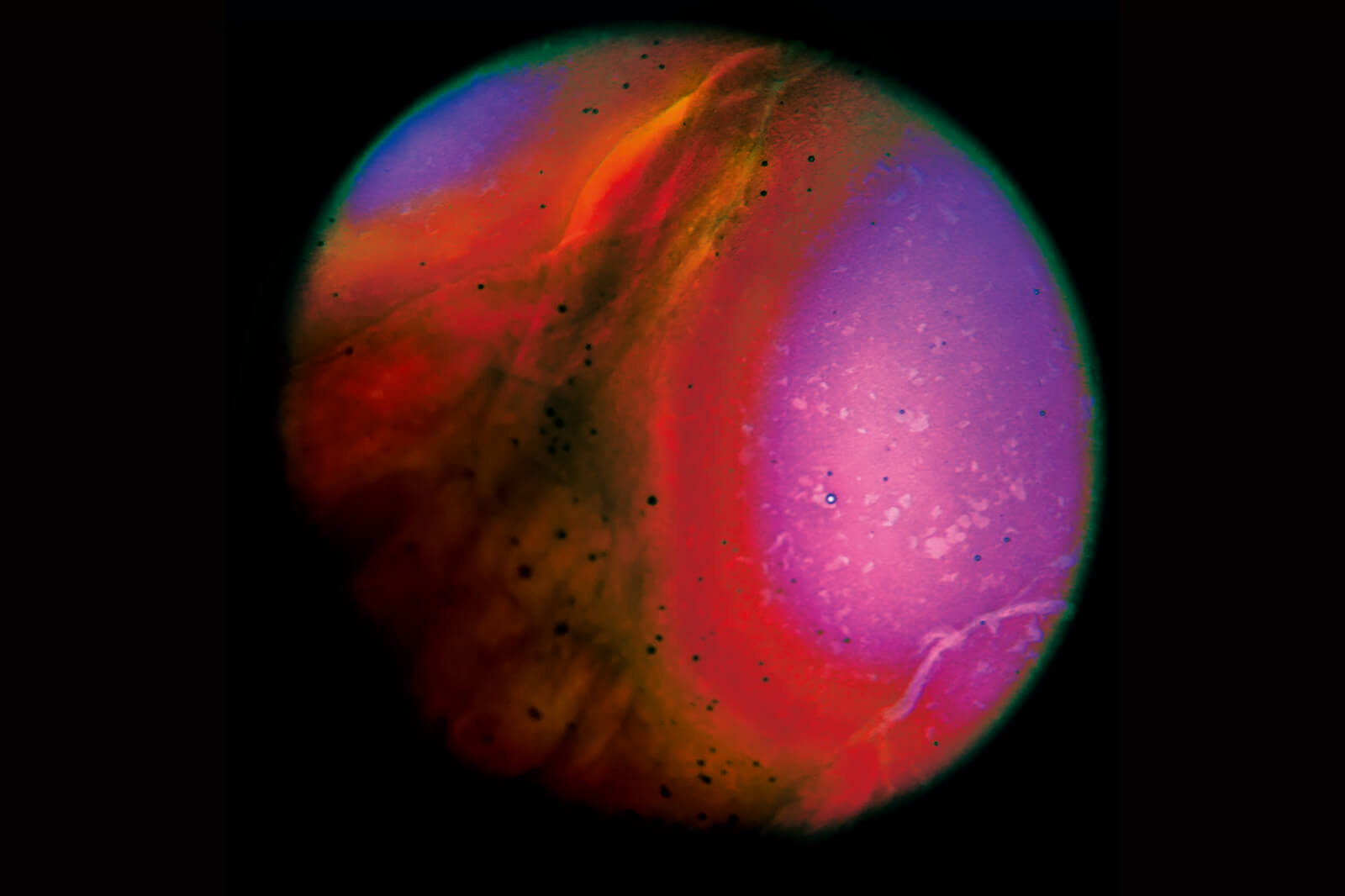
重要なものは、欲望ではなく欲望の布置であり、脳殻ではなく皮膚の皺であり、性的差異ではなく義体者のよしみである。バトーとタチコマ、パズとかつての恋人、草薙少佐とバトー、三様の関係性分析を通じて、古怒田望人/いりやは「大局的にホモソーシャルな欲望を展開」する《攻殻機動隊》の作品世界にクィアな親密性を読み込んでいく。その際、いみじくも古怒田がオッカムの剃刀として用いたのは「同じさ(sameness)」という概念である。
セクシュアリティをこの「同じさ」の視点から捉え返し、非人称的なナルシシズムを生きるものたちが取り結ぶアウトローな親密性を称揚した人物がいる。2022年に帰幽したクィア理論家、レオ・ベルサーニだ。「愛する者の愛する自己は愛される者の自己でもあり、愛される者は愛する者の自己として愛される自己を愛する」と書くように、ベルサーニの思索の前提にはあらゆる既存の秩序への包摂を拒絶し、他者との関係性そのものを否定するような、ラディカルに自閉した個の存在がある。孤絶した個をいたずらに否定するのではなく、自己愛の極限にある「非人称性」をとりだし、その「同じさ」を通じて、私たちが「私たち」となるための可能性を斜めに(slantwise)探るベルサーニの思想は、《攻殻機動隊》の世界の、文字通りに「STAND ALONE COMPLEX」を生きる、異貌のナルキッソスたちが抱える葛藤とも共鳴する。
重要なものはだから、「関係性」の「ありえなさ」である。その「ありえなさ」から目を逸らさず、しかし、その可能性を古怒田/いりやのように探りつづけることそこに「ゴースト」が宿る刹那を見逃さないこと。
目次
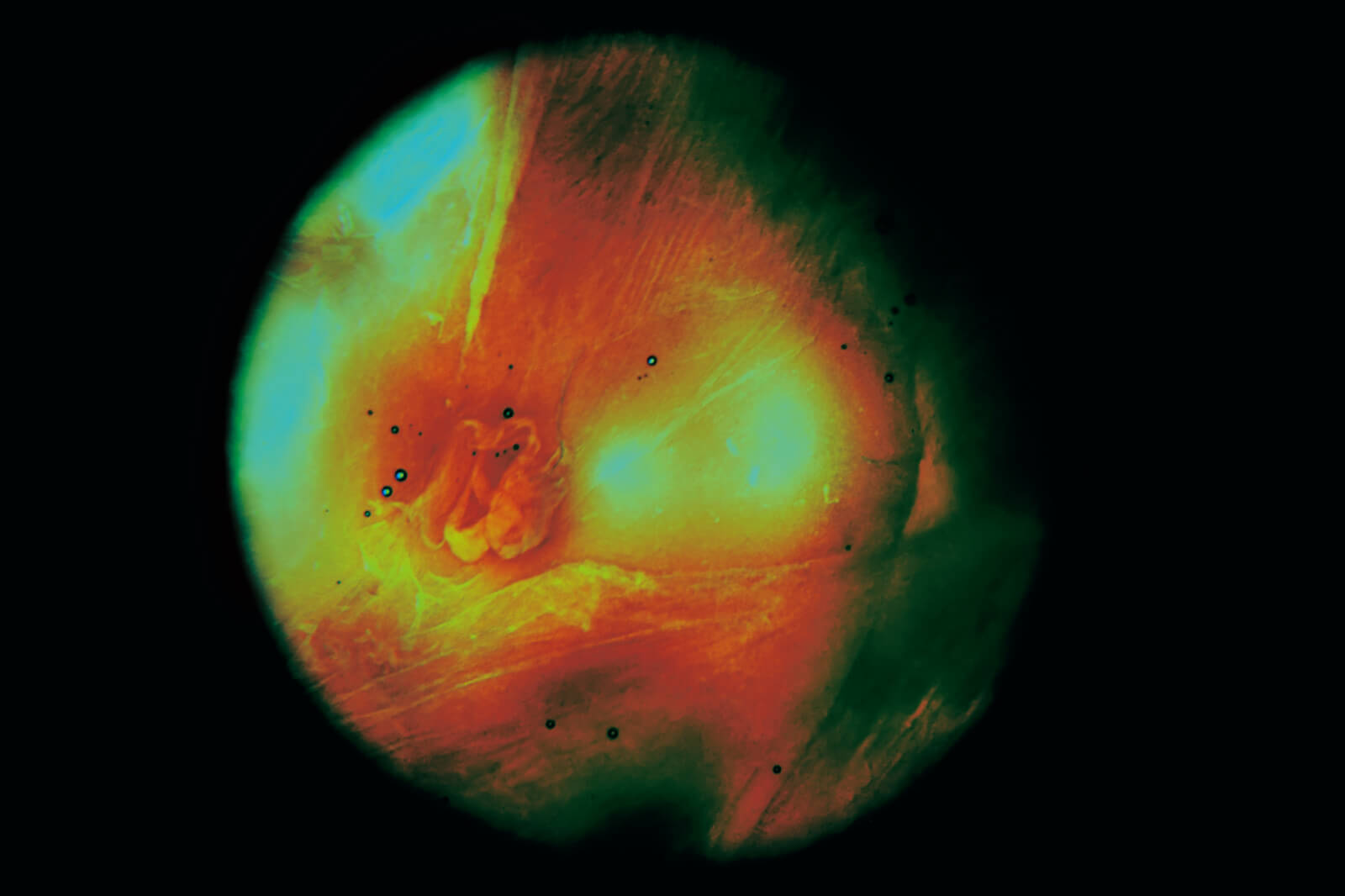
《攻殻機動隊》に潜在するクィアな欲望
そして、第一のユートピア、人間たちの心の中の最も根絶しがたいユートピア、それはまさしく非身体的身体のユートピアでありうる。*1
初めてセックスをしたとき、無意識の内に正常位を行っていた自分自身に吐き気を覚えた。世間的な男の振る舞いを身体化してしまっているのだと。そして、その男性性への嫌悪感から抜け出すために、ボクは女装をするようになった。しかし今度は、女性性を周囲に要求されるようになった。きれいでかわいい女であれと。出口のない男女の檻。そこから自由になるイメージは、子どもの頃に読んだ少女漫画に出てくる美少年たちの裸体だ。ペニスを付与されず、性差を示すことのないその裸体は、男女の檻に縛られることのないユートピア的な身体に映った。それはまるで、性差のないサイボーグの身体のようでもあった。
人は、ペニスあるいはヴァギナに縁取られた身体に縛られている。既存の社会の多く──とくに日本国内において──生まれたときに割り当てられる性別は、基本的に、ペニスあるいはヴァギナの有無に照らして決定される。そして、公的な書類にその性別が組み込まれると、人の人生はその性別に左右されることになる。例えば、ペニスをもつ男なら、男らしさを身に着け、女を愛し、父として家族をつくることが普通、当たり前であると。
では、ペニスやヴァギナという身体的記号が無効になる社会においてはどうなのだろうか。《攻殻機動隊》シリーズの社会では、身体の性別を変えることができるような機械化された身体が提示される。表面上、そこで男女の身体的性差は無効に見える。
しかし、《攻殻機動隊》という作品は、奇妙なほどに男女の身体的性差に縛られている。例えば、公安9課のメンバーのほとんどは男の外見をした人物たちで、オペレーターや雑務を勤めるアンドロイドたちだけが女の姿──しかも男たちとは異なって画一化された女の姿──をしている。ここには、男が社会の主体となり、女にはその副次的な役割しか与えられないという家父長制の存在が見てとれる。それゆえ、《攻殻機動隊》の世界は表面上、ペニスとヴァギナによって決定されない身体を設定しているにもかかわらず、ペニスとヴァギナによって定められたおきまりの世界を示すに留まっている。
だが、《攻殻機動隊》シリーズにおける表象には、男女の身体的区別から解き放たれている側面もある。例えば、劇場版『Ghost In The Shell/攻殻機動隊』(以下、『GITS』)の終盤に登場する、草薙素子少佐(以下、「少佐」)が戦車の装甲を引き剥がそうとする場面の身体表象は、男とも女ともいえない曖昧な身体を映し出している。そこで本論は、《攻殻機動隊》シリーズにおける欲望の表象に着目し、そこに潜在するクィアな欲望のありようを浮き彫りにしたい。
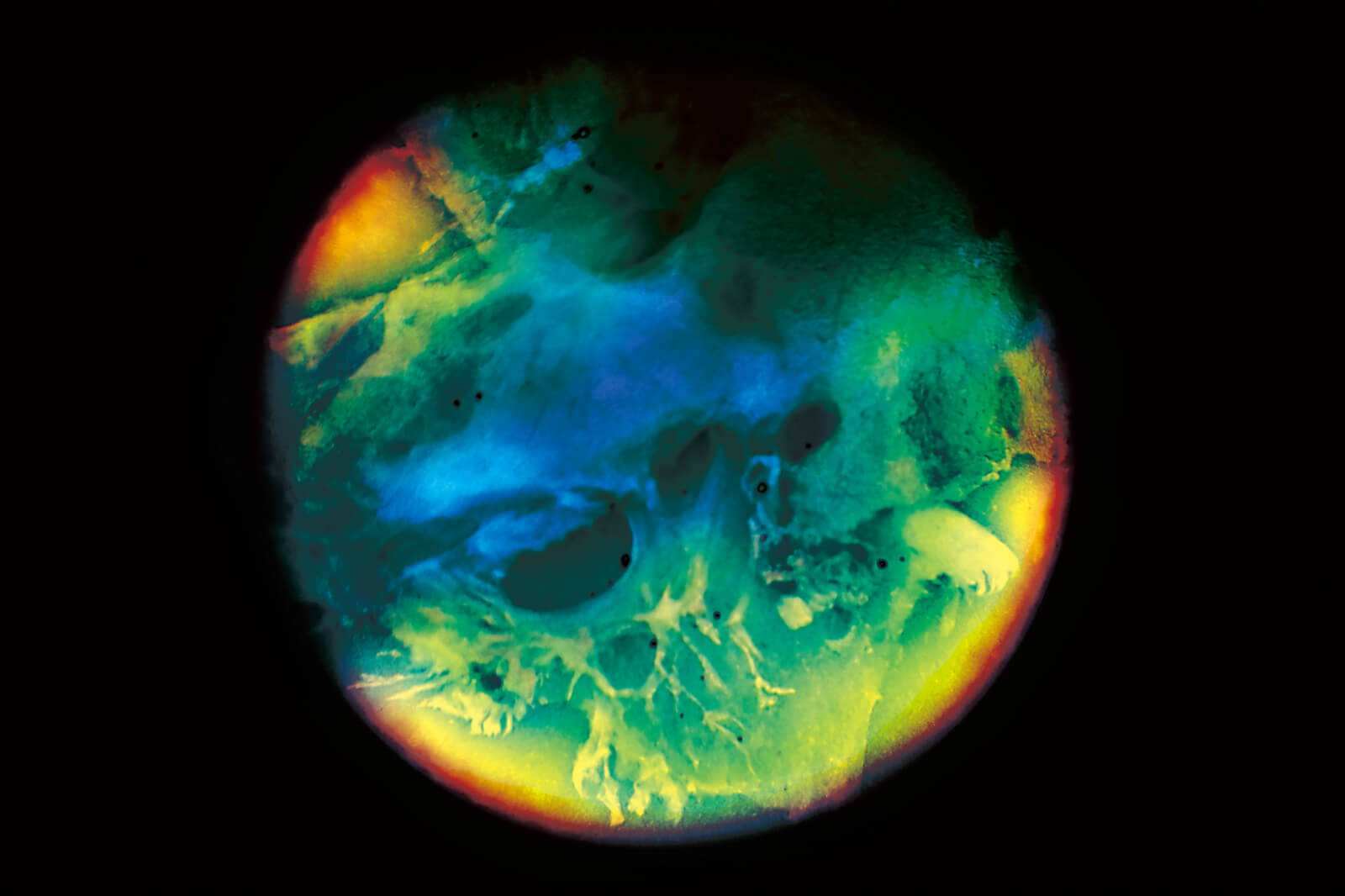
義体者のよしみ
《攻殻機動隊》におけるバディと言えば、少佐とバトーだろう。サイボーグ化している者同士の組み合わせは、押井劇場版*2やS.A.C.版*3において、ある種の親密な関係性を描いている(例えば、少佐を「素子」という名前で呼ぶのは、押井劇場版においても、S.A.C.版においてもバトーだけである)。表向きは極めて異性愛中心主義的な作品である《攻殻機動隊》シリーズ*4において、この少佐とバトーのバディも異性愛関係と読めるのは確かだ。だが、両者には異性愛関係とは別の親密性が存在するのではないだろうか。
ところで、『GITS』において、少佐は人形使いと一体化することで、個人的な身体を捨て去る。それにより、少佐は、特定の義体と電脳ではなく、アクセス可能な無数の義体と電脳を駆使するようになる。人形使いがそうであったように、もはや少佐のジェンダーを特定する記号はどこにも存在しない。少佐は、性別(セックス)に縛られない身体を生きるだけではなく、ジェンダーの記号にすら還元されない存在となる。バトーが『イノセンス』で少佐を「守護天使」と形容するのは、文字通り、少佐に性別もジェンダーもないからだといえる。
だが、そうしてジェンダーの記号から離れてもなお、少佐はバトーとの親密な関係性を維持する。『イノセンス』終盤で、バトーに向けて少佐の口から語られる「あなたがネットにアクセスするとき、私は必ずあなたのそばにいる」というセリフがそれを示唆している。ジェンダーに依存しない存在となってもなお、バトーとのバディ関係においては、少佐は「そばにいる」親密な他者のままなのだ。
では、この少佐とバトーの親密性とは何なのだろうか。彼ら*5の関係性をかたちづくる欲望の布置とは何なのか。
両者の親密さに迫る鍵のひとつとなるのは、彼らの近さなのではないか。外見も行動様式もまったく異なるが、少佐とバトーにはある種の近さがある。この近さは、『S.A.C.』第1シリーズの終盤で顕著に見られる。軍隊の特殊部隊に追い詰められ、少佐のセーフハウスに身を潜めた少佐とバトーは、互いの義体に関する執着の類似性に出会っている。すなわち、一方で少佐は女性ものの腕時計をつけられる義体を選び続け、他方でバトーはサイボーグ化された身体にはもはや必要のない筋トレをし続ける。つまり、両者は、全身義体となることで特定の身体に依存しない身体を手に入れたというのに、義体の個別性に執着しているのだ。
たしかに、少佐とバトーのこのような義体への執着は、典型的な女性的身体/男性的身体への執着であり、そこには規範的なジェンダー表現が見られる。だが、彼らの義体への執着は、男女二元論的な性的差異に還元されないものである。
少佐とバトーは、九課のホモソーシャルに閉じた欲望の図式から逸脱する。『GITS』での、ボートの上で少佐とバトーが話し合うシーンを例にとってみよう。酒を酌み交わしながら仕事の話をするといういかにも古典的な男性性の規範に則ったやりとりが展開される中、少佐はバトーにのみ九課の任務から外れたプライベートの話をする。公的な関係でありながら私的な関係も垣間見させる二人のやりとりは、九課から逸脱した親密性を感じさせる。少佐がバトーにだけ打ち明け話をするのは、二人とも全身義体であるということと無縁ではないように思われる。『攻殻機動隊 ARISE』のバトーの言葉を借りれば、「義体者のよしみ」がこの親密性には現れているのではないだろうか。もしそうであるなら、同じくバトーが少佐に抱く恋心にも似た親密さも、性的差異に基づいた男の女に対する欲望ではなく、全身義体の者同士の類似性に発する欲望と捉えるべきだろう。こう考えてみると、少佐とバトーは、単なる仕事上のバディであるというだけではなく、(シスヘテロな)男性性に閉じられた九課から独立したバディ、つまり異性間の身体的差異に発する親密性ではなく、義体という身体タイプの「同じさ(sameness)」に基づいた親密性に貫かれた、クィアなバディに見えてくる*6。
ただし、少佐とバトーの「同じさ」に基づいた親密性は、少佐とバトーを一夫一婦制に類するカップルの関係性には閉じない。というのも、義体の親密性は、少佐とバトーの「孤独」に裏打ちされているからだ。『GITS』に顕著なように、少佐はどこか他者と距離を置いたような態度を保っている。自分を理解してくれる者などどこにもいないと言わんばかりに。他方で、少佐が後景に退いた『イノセンス』のバトーも、愛犬のガブリエルとの関係を除けば、他者とは距離をとる姿勢を貫いている。そして、この彼らの「孤独」は、彼らの身体が全身義体であり、自分も含めて誰も自らの機械化された身体を理解できはしないという感情に伴うものなのではないか(だからこそ、互いに自身の義体に執着しているといえる)。少佐やバトーが、義体化されていないトグサとバディを組まない、あるいは組んだとしても不調和を起こすのは、義体でないものの前では自身の全身義体の者としての孤独がより一層あらわになるからではないか。それゆえ、彼らを繋ぐ「義体者のよしみ」は、そもそも誰とも分かり合えないという感情に裏打ちされているのではないか。したがって、少佐とバトーの関係は、バラバラなまま繋がっているという逆説的な親密性なのだ(それゆえ、《攻殻機動隊》シリーズにおいて、少佐とバトーが結ばれることがないのだといえる。なぜなら、彼らの親密性は、互いに孤独であることが前提となったものなのだから)。
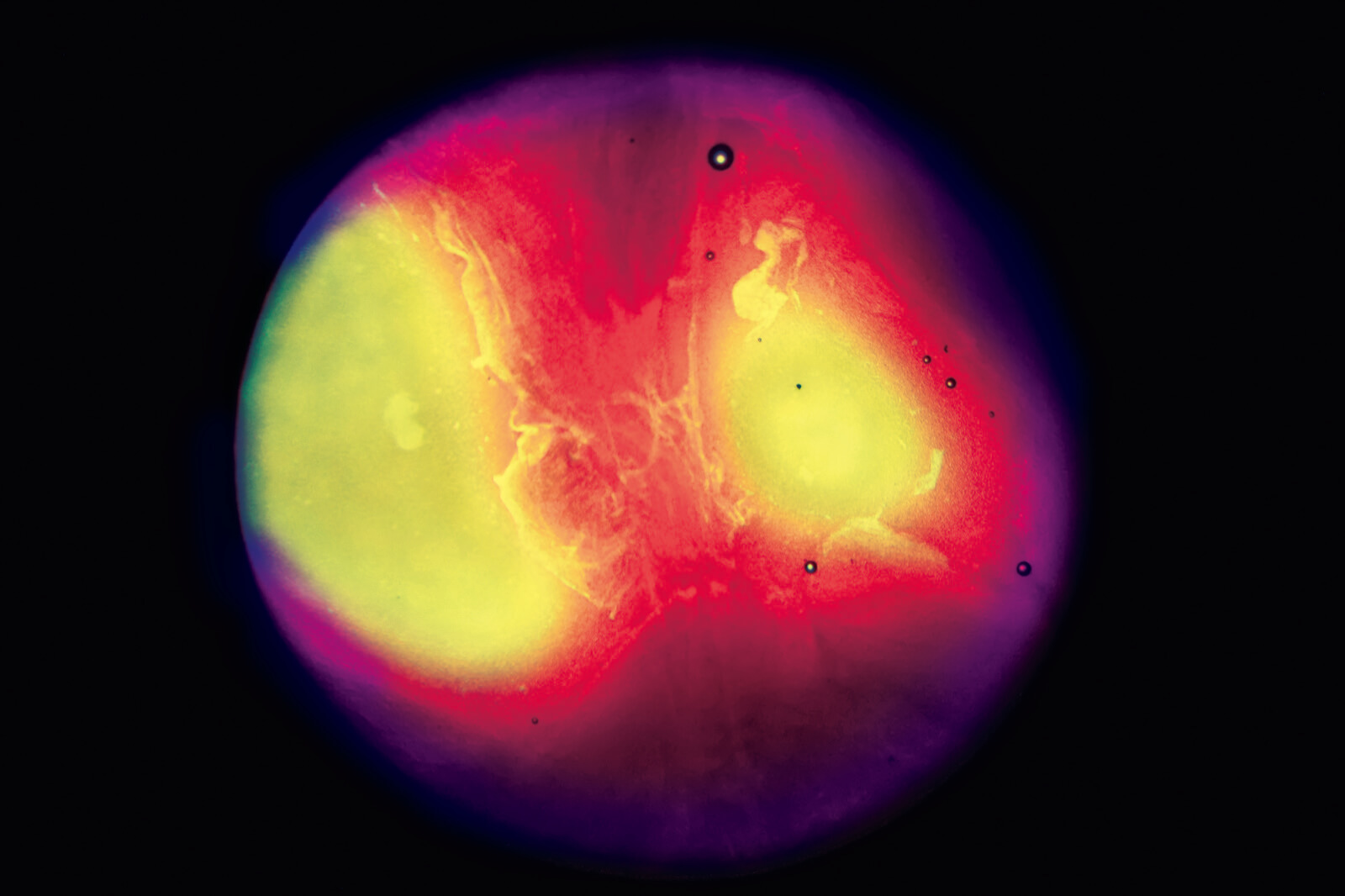
タチコマの「非アイデンティティ主義的な同じさ」
人工知能を搭載した思考戦車であるタチコマに性別はない。実際、彼らの「ボク」という一人称は、「俺」という一人称が多用される九課において特異なものである。さらにタチコマには、「個」という概念も存在しない。九課での任務が終わったあと、タチコマたちの記憶は並列化されるためだ。タチコマ自身の言葉を借りれば、「あらゆるデータは(タチコマにおいて)並列化されている」ために「一体の経験は、全体の経験として記憶されている」(カッコ内は引用者による補足)。ネットの海にダイブするわけではないが、個を逸脱した存在になるという点で、タチコマたちは原作あるいは押井劇場版の少佐に似ている。
だが、バトーがタチコマに向ける欲望が、彼らに個の概念をもたらす。『S.A.C.』第1シリーズでバトーは、バディ関係を結んでいる特定のタチコマに天然オイルを与える。その結果、このタチコマの人工知能は個性を獲得することになる。さらに、この個性を獲得したタチコマの記憶が並列化されて、すべてのタチコマに自我が目覚めてしまう。個体性を捨てて普遍的な存在になることを志向する押井劇場版や原作と比べると、『S.A.C.』第1シリーズでは並列化された普遍的な存在から、どのように個が立ち現れるかが描かれている(実際、原作や押井劇場版での少佐が元の義体を捨てて、男あるいは子どもの義体で去ってゆくのに対し、『S.A.C.』第1シリーズでの少佐は、子どものリモート人形に偽装工作していた身体を、元の義体に戻すことになる。「やっぱりこっちの身体じゃないと」いけないのだと)。
個に目覚めたタチコマたちは、バトーをバディとして求める欲望を前景化させる。自我が生まれてきたことから兵器としての性能に問題が生じたと見なされ、ラボ送りとなったタチコマたちだったが、『S.A.C.』第1シリーズの終盤、バトーの危機に駆け付ける。ほとんどが解体され残された3体のタチコマたちは、バトーのバディとして闘う意志を示す。そして、バトーを守るためにタチコマたちは犠牲になり破壊される。
親密性を論じる本論においてポイントとなるのは、人工知能が自己犠牲の精神、すなわちゴーストを獲得したという結果ではなく、個別性のない普遍的な存在が、親密な他者から向けられた欲望を介して個性を獲得するプロセスのほうだろう。バトーの介入を得て個性を獲得したタチコマが他のタチコマと記憶を共有する並列化は、個性を普遍性へと解消するのではなく、バディであるバトーの欲望を介して普遍的な存在から皆がそれぞれ個別的な存在となるプロセスを意味する。バトーや少佐と同じく、タチコマのように性別をもたないノンバイナリーな存在(『イノセンス』での少佐と同じく、バトーの窮地を助けるという意味で、『S.A.C.』第1シリーズのタチコマもまたバトーの「守護天使」だ)もまた、その機械化された身体に根差した欲望の布置を通じて、個体性を得るのだ。
だがタチコマの個体化は、アイデンティティの獲得と同義ではなく、むしろアイデンティティを粉砕することで生じる。『S.A.C.』シリーズにおいて、九課の主要メンバーがどのような危機に陥っても決して死ぬことがないのに対して、タチコマたちのボディは作中で幾度も破壊される。そして並列化によって、タチコマの個体としてのアイデンティティは幾度となく粉砕することができるものとして描かれてもいる。それゆえ、タチコマの個別性を形成しているのは、彼らが他の個体との関係で自らを同定するアイデンティティではなく、バトーという他者の欲望を介した関係性の布置であるといえる。アイデンティティが消失しても、欲望を通じた関係性は失われることはない。そのため、『S.A.C.』シリーズにおいて、タチコマはいくら破壊されても何度も甦り、そのつどバトーのバディとなるのだ。
このようなタチコマのありようは、レオ・ベルサーニが、同性愛を理論化して論じた「非アイデンティティ主義的な同じさ(nonidentarian sameness)」*7という観点と照応している。ベルサーニにとって、同性愛的な(homosexual)欲望は、それぞれの個別的な差異=アイデンティティを引き払い、そのアイデンティティの消失が「同じさ」という同質的な(homogenous)欲望に繋がるものである。タチコマにおいても、個体としてのアイデンティティが粉砕される自己消失の経験は、彼らのあいだで並列化された、バトーへの同質的な欲望の回帰(ある種の自己複製の経験)と隣り合わせのものである。
しがって、タチコマとバトーのあいだで働いている欲望は、(シスヘテロの)男女関係をモデルとした《攻殻機動隊》シリーズの表向きの表象から逸脱した、クィアな欲望の発露なのだ。
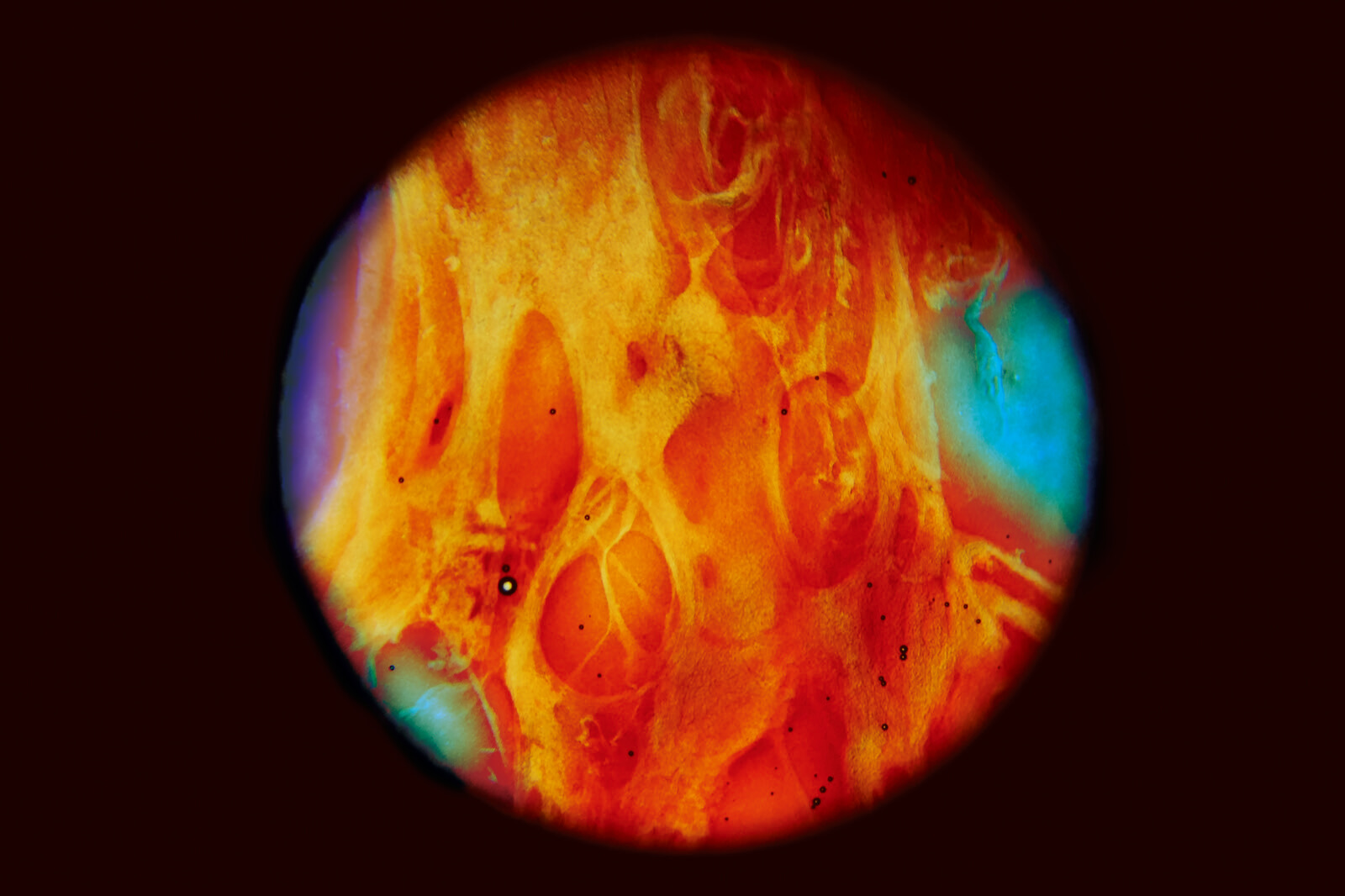
「皺」としての身体
最後に、《攻殻機動隊》の欲望の表象が、現実のクィアな生と交わる点について論じてみたい。まず、『S.A.C.』第2シリーズ第13話「顔 MAKE UP」のエピソードをとり上げてみよう。このエピソードは、九課が追っていた造顔作家が、九課のメンバーであるパズにそっくりの人物に殺害されたところから始まる。その後も、なりすまし犯による殺人事件が起こり追い詰められたパズは、殺された造顔作家の顧客リストから、ある人物を特定する。
パズが顧客リストから特定した人物、それは過去に彼と恋愛関係にあった女だった。自分のもとからパズが去った理由を理解するために、女はパズにそっくりの義体を手に入れていたのだった。「あたしはあたしのなかにあなたのゴーストを手に入れたから」と言う女は、行き場を失ったパズへの愛を自らに傾け、パズの身体と同一化することを選んだのだ。異性愛的な欲望が相手の男に同一化するという帰結に至るという意味で、彼女の異性愛的な欲望は、規範的な観点からは想像もつかないような絡み合いを含んでいる。
性器に向かわないという点で、彼女の欲望は非異性愛的である。パズと一体化した女は、「ゴースト」が、「脳核」の中ではなく、「皮膚、とくにその顔に刻まれた皺」に宿るのではないかと語る。つまり、彼女は、パズのペニスを有した身体ではなく、その皮膚に刻まれた「皺」を手に入れたいと願っていたのだ。彼女の欲望は、性器のある身体に向かわないクィアネスを帯びている。
パズの「皺」を身に纏うことが彼と同一化する術だと考えるこの女性の欲望に、ボクは親近感を覚える。なぜなら、ボクの身体もまた、非性器的欲望と交わっているからだ。
ボクの背中には突起物がある。ステゴサウルスの背中のように、背骨の一部が隆起しているのだ。これは、ボクがクィアであることの痕跡となっている。というのも、これは、ボクがクィアな人々とセックスを重ねていたときに、「なんの病気があるか分からないから触らないで」と親族に言われたことに傷つき、自殺未遂を図って負った圧迫骨折の痕だからだ。けれどもこの背中の傷は、悲しみに満ちたものではない。この傷は、血縁という小さなコミュニティに閉じられることのない、女装、ニューハーフ、純女(じゅんめ)、純男(すみお)といったクィアな欲望をもつ人たちとの関係性の痕跡でもあるからだ。つまりボクは、様々なクィアな人々との欲望を通じた「関係性のゴースト」をこの背中の傷に宿しているのだ。ボクの隆起する背骨は、パズと同一化した女が手にした身体と同じく、性器とは異なった身体領域から欲望の痕跡を描く。スティグマに由来する傷は、悲しみの原因とはならず、ボクのクィアネスの痕跡として働いている。
ボクが非性器的欲望を通じて獲得した「クィアな関係性のゴースト」は、《攻殻機動隊》における全身義体をもつ人々の感覚と重なり合う面がある。『S.A.C.』第2シリーズの終盤に、メインキャラクターの一人であるクゼ・ヒデオは、少佐にプライベートな自身の心身の問題を語る。彼は、子どもの頃から全身義体であったために、「心と身体の不一致を絶えず感じていた」と。しかし、彼が放浪の道中で出会ったアジア難民たちは、彼のつくり物の顔を「とてもいい顔」だと承認してくれ、「ゴーストが顔に現れているのだと褒めてくれた」という。そのとき彼は初めて、「心と身体は不可分な存在なのではないかと実感し」、「自分も肉体をもつ人間」なのだと感じることができるようになったと語る。
パズと一体化した女の言葉を想起しよう。彼女の言葉を借りれば、アジア難民との遭遇と彼らによる承認によって、クゼの「ゴースト」は、「脳核」の中ではなく、「皮膚、とくにその顔に刻まれた皺」の中に宿った。パズと同一化した女の顔と心身の不一致を感じていたクゼの顔をつくったのは同一の造顔作家であり、彼は戦争の負傷者の傷跡に負傷者たちの心の傷の深さを見て取っていたという。造顔作家の思いは、クゼが難民によって顔の良さについて承認を受けたあと、自身の皮膚に刻まれた傷跡(「皺」)が自身のゴーストを認識する媒体となった瞬間に成就された、といえるだろう。
幼い頃から性別違和をもっていたボクにとって、社会では男性性を象徴し、親密な場面でも正常位を模倣してしまうこの身体は、自らを男ではないと感じる心と食い違っていた。それゆえ、クゼが感じる「心と身体の不一致」の意味がよく分かる。しかし釘を刺しておくなら、ボクは、「トランスジェンダーの抱えている困難は心の性と身体の性の不一致だ」というステレオタイプ化された言説を繰り返したいわけではない。むしろ、クゼがそうした「不一致」を、心身二元論的ではない仕方で昇華したということを強調したい。それはすなわち、「ゴースト」は「脳核」の中ではなく「皮膚、とくにその顔に刻まれた皺」の中に宿っているということ、言い換えれば、「心(の性)と身体(の性)」を二つに分けることはできず、その心身の「不一致」の感覚にアプローチするためには「身体を通じて浮き彫りになる心」が必要になるということだ*8。実際、ボクが生き、傷跡として身体化されたクィアな関係性に関する欲望は、男という出生時に割り当てられた性別によって引き起こされた「心と身体の不一致」から抜け出すひとつの手段となった。したがって、クゼが感じる(そして、おそらく、少佐やバトーのような《攻殻機動隊》における全身義体の登場人物たちすべてが感じる)「心と身体の不一致」は、心身二元論的な袋小路で行き詰まってしまうのではなく、むしろ心身が不可分であるような領域にまで至って初めて、ボクのようなクィアな存在が生きる欲望と交錯する。
ところで、「皮膚」や「皺」といった、他とは異なる個人の身体的アイデンティティに依存しない身体領域から欲望を考えることは、関係性をアイデンティティとは別のモデルから展開することに繋がるだろう。ボクも、パズと同一化した女も、クゼも、「皮膚」や「皺」を介した「形式的な類縁性(formal affinities)」*9によって混ざり合う。それは、差異によってつくられるアイデンティティとは異なった「同じさ」によって欲望を紡いでいた少佐とバトー、あるいはタチコマとバトーとの関係性とも絡み合う。《攻殻機動隊》における機械化された欲望は、個別のものとして差異づけられた個人のゴーストではなく、身体化された「関係性のゴースト」によって自己の外部と繋がる仕方を提示している。
《攻殻機動隊》の世界はフィクションの世界だ。全身義体の身体も、自己粉砕を繰り返す人工知能も、性別をまったく入れ替えることのできる義体も、現在の社会ではまだ実現不可能だろう。しかしそれでも、架空の未来を描いた《攻殻機動隊》の欲望の表象は、今ここで現実を生きるクィアな欲望と交錯する側面がある。大局的にはホモソーシャルな世界観を展開する《攻殻機動隊》には、クィアな欲望を現実で具体化するためのユートピアの装置ともなりうる希望が潜在している。
[註]
*1
ミシェル・フーコー『ユートピア的身体/ヘテロトピア』佐藤嘉幸訳、水声社、2013年、p.17
*2
押井守が監督を務めた『Ghost In The Shell/攻殻機動隊』と『イノセンス』の2作品を指すためにこの語を用いる。
*3
TVアニメシリーズ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』の略。なお、本シリーズの第2シーズン『攻殻機動隊S.A.C.2nd GIG』は「『S.A.C.』第2シリーズ」と表記する。
*4
例えば、原作や『S.A.C.』版には少佐が女性と性的な関係をもつ描写があるが、『S.A.C.』第2シーズンと『ARISE』版で描かれているのはおもに少佐と男性とのパートナー関係である。女性同士のパートナー関係はそれほど明示的に描かれてはおらず、《攻殻機動隊》シリーズにおいて、レズビアン関係は副次的な地位に貶められている部分がある。
*5
本論において「彼ら」という代名詞は男性代名詞の複数形ではなく、theyという中性代名詞の複数形を指すものとする。
*6
この点で、『S.A.C.』第2シリーズでのクゼと少佐の親密な関係性も、異性の男女関係ではなく、全身義体の「同じさ」に基づいた親密性と捉えることができる。
*7
Leo Bersani, Is the Rectum a Grave? and Other Essays, The University of Chicago Press, 2010: 183.
*8
このような「皮膚」や「皺」に関する身体性を、唯物論的に解釈する必要は必ずしもない。というのも、この「皮膚」や「皺」の感覚は、パズと女との「あいだ」あるいはクゼとアジア難民との「あいだ」で形成されている「イメージ」としての身体でもあるからだ。この点で、《攻殻機動隊》の身体観は「身体イメージ」としての身体性を提示していると言える。
藤高和輝「「性別違和」とは何か?: トランスジェンダー現象学の導入に向けて」稲原美苗他編『フェミニスト現象学入門』ナカニシヤ出版、2020年、pp.115-126
*9
なお、この「皮膚」の観点に関しては、長尾優希「ベルサーニの暴力的ケア/サエボーグの横滑りする身体」『ジェンダー&セクシュアリティ』(第18号、2023年)から大きな示唆を得た。
Leo Bersani, HOMOS, Harvard University Press, 1995:121
こぬた・あさひ(いりや)/1992年生まれ、神奈川県出身。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程所属。男にも女にもありきれないジェンダークィアとして生きている。専門は、現代思想、クィア理論、トランスジェンダー研究、エマニュエル・レヴィナス、レオ・ベルサーニ。おもな論文に、「初期レヴィナスにおける性の記述の問題:その規範性と可能性をめぐって」(『現象学と社会科学』第5号、2022年)、「後期レヴィナスの倫理におけるクィアな人々への喪と生存可能性の観点:バトラーとフロイトの喪の観点を介して」(『現象学と社会科学』第6号、2023年)、共著に『フェミニスト現象学入門:経験から「普通」を問い直す』(2020年)と『フェミニスト現象学:経験が響きあう場所へ』(ともにナカニシヤ出版、2023年)がある。

