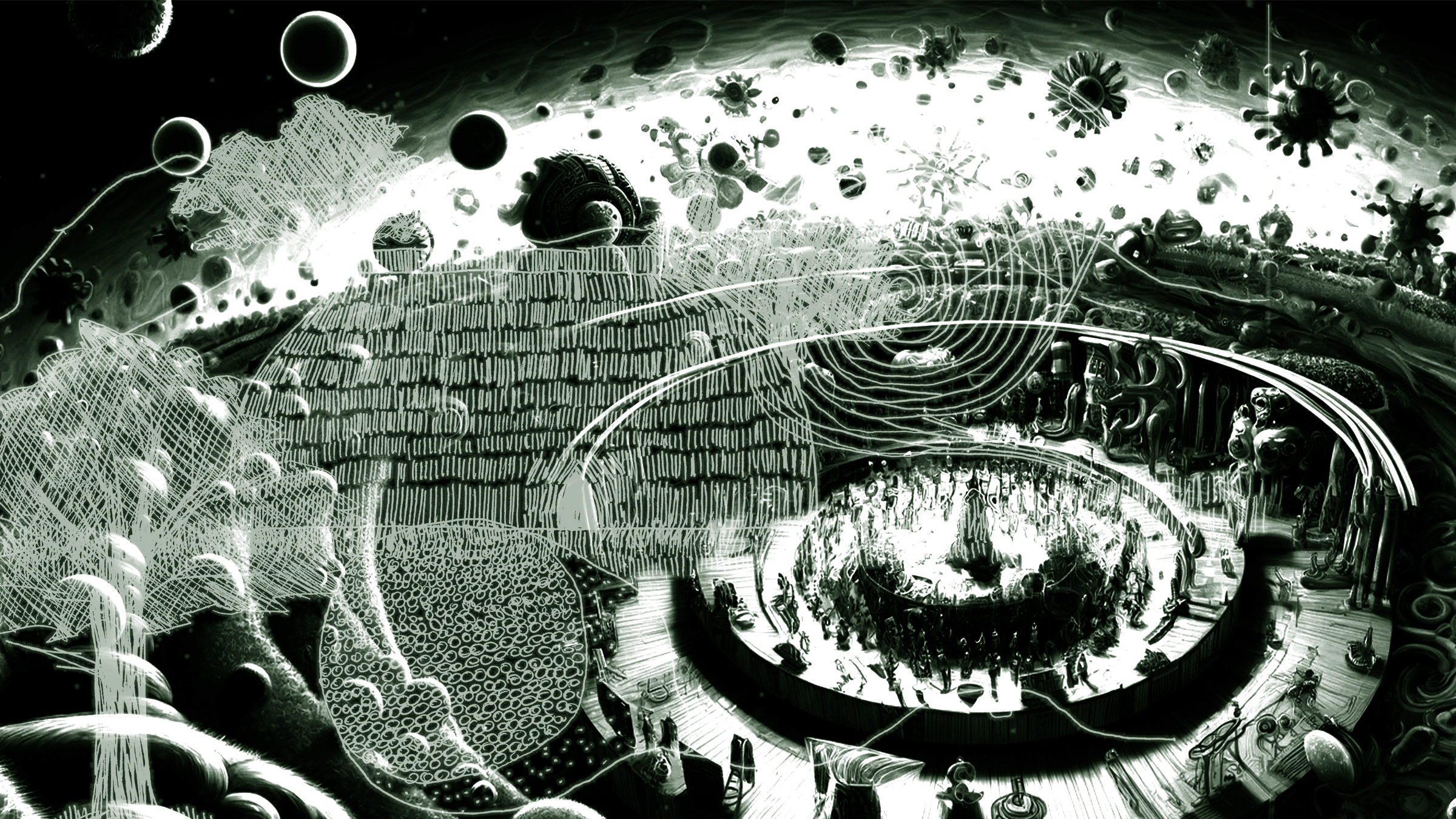
グローバリゼーション下の「空間」に抵抗の兆しを見る
聞き手・翻訳_太田知也[Tomoya Ohta]翻訳協力_森脇透青[Tosei Moriwaki]
図版_studio TRUE
イースタリングの著作は英語圏の建築・デザインスクールで注目を浴びるのみならず、グローバリゼーション研究や社会評論としても幅広い読者を得ている。著書に推薦コメントを寄せる知識人や媒体名──サスキア・サッセン、マイケル・ソーキン、『ArtReview』誌、『Harper’s Magazine』誌など──を挙げれば、その広がりを感じていただけるだろう。
近代的な統治の権力作用が曖昧になるような、いわば境界線上の空間に対して、イースタリングは分析の目を向けている。具体的には、自由貿易地域や保税区域、朝鮮半島のクルーズ船観光、セレブのゴルフ場や商業施設などである。
今回はそうした事例や著書内の概念について、メールによるインタビューを実施した。なお、取材と翻訳を担当した太田知也は、批判理論の観点からアートの歴史とデザインの方法論を考究するマット・マルパス『クリティカル・デザインとはなにか?』(水野大二郎、太田知也監訳、野見山桜訳、ビー・エヌ・エヌ新社、2019年)をはじめ、デザイン領域の研究に関していくつかの訳業をもつリサーチャーである。
まずは「超国家的国政術」や「政治的スーパーバグ」など、この建築家が用いる術語の数々に耳を傾けてほしい。そうすることで、イデオロギーの左右や世俗と超俗が混ざりあう現代の権力作用が、物理的ないし建築・デザイン的な仕方で効力を発揮するさまを捉えることができるだろう。
目次
製品的な空間が作られる原理と、その暴力性を批判する諸概念
──「空間」をめぐるあなた独自の諸概念についてご紹介願います。あなたの一連のご著書は、三つの空間について語ったものだというように読むことができるとわたしは考えています。まず、『無害そうに忍ぶ──グローバルな建築とその政治的仮面劇』(Enduring Innocence: Global Architecture and its Political Masquerades, MIT Press, 2005/未訳)は「空間製品(spatial products)」というマルクス主義的な概念を導入する役割を果たしているようです。それはグローバルな規模で増殖し、各地の都市を均質化していくものとしてあります。
つぎに、『超国家的国政術──下部構造的空間の権力』(Extrastatecraft: the Power of Infrastructure Space, Verso, 2014/未訳)は近代的な統治の作用を曖昧にする情報の流れを下支えする存在、すなわち「下部構造的空間(infrastructure space)」を明らかにしていますね。最後に、以上の二冊を踏まえた政治的行動のガイドという趣きが『メディウム・デザイン──世界に働きかける方法を知る』(Medium Design: Knowing How to Work on the World, Verso, 2021/未訳)にはありそうです。そこでは、批判的な理論を行動に繋げるような見方が現われています。言いかえれば、グローバリゼーションのもとで変容を遂げている空間を、操作可能な媒体として捉えなおすことが試みられているのではないでしょうか。
イースタリングまず、わたしは『無害そうに忍ぶ』に先立って『組織的空間──アメリカの風景、ハイウェイ、家並み』(Organization Space: Landscapes, Highways, and Houses in America, MIT Press, 2001/未訳)という書籍を刊行しています。そこで紹介したのは、規格(プロトコル)という形態をとりうるような空間製品や空間デザインという観念です。『無害そうに忍ぶ』では、世界中をあちこちに動き回る空間製品ないしその種の空間を作りだすうえで常套的に反復可能な定式──高度に定型化された商業的な装置のことですが──に関するエビデンスを調べていました。驚くべきことに、その定式は、グローバルな政治状況の中心にしばしば躍りでてきていたのです。いまでこそ、グローバル化している世界へのもっとも急進的な変化の一部は、建築と都市研究の言語で書かれていますが、当時は、この種のグローバルな証言と政治的批判は、建築文化においてはもちろんのこと、政治分析においても異例なものでした。
わたしが考えていたのは、建築家の知恵がデザインの実務に役立つだけでなく、より広範に、グローバリゼーションの諸力についての文化をめぐる対話にも関連するのではないかということでした。〔一見すると、〕ゴルフコースやリゾート、オフィス街、ショッピングモールといった空間を作るうえで反復されている定式は、非政治的な、つまり経済的でしかない原動力に見えるようデザインされています。ですが、『無害そうに忍ぶ』が暴露しているのは、そうした力が〔実際には〕政治的な手ごまであり、世界中に広がる伝染性をもち、そしてしばしば非合理な魅力を中心にして築かれる手のこんだ茶番劇でさえあることです。こうした定式は、神話や欲望や象徴的資本を得ることで、ならずもの国家、カルト、強権的指導者たちの狡知と容易に混ざりあいます。
『超国家的国政術』では、グローバルなインフラストラクチャに焦点を当てました。それは隠れたパイプや配線としてではなく、むしろ事実上の統治形態を生み出している都市のオペレーティングシステムが目に見えるかたちで表出したものとして焦点化されています。それについて重要なエビデンスを示す章のひとつは、「自由」貿易地域という世界的な現象に関するものでした。この分析手段によってもっぱら理解が進むのは、新自由主義に傾いた競争の場と、操作された(すなわち「自由」などではない)貿易です。都市の全体に関する反復可能なこうした定式は、超国家的国政術(extrastatecraft)の生きた容れ物でもあったのです。超国家的国政術はポスト国民国家的な世界ではありません。それは、国家が新たにより狡猾なパートナーを得て、法的には安定しているが環境は劣悪であるような労働形態を作りあげる世界なのです。
法的・計量経済学的・デジタル的な言い回しが文化的に称賛されるなか、わたしが上記の二冊で目論んでいたのは、グローバルな資本やポストコロニアル研究の言説に、過小評価されている空間関連のエビデンスをもたらしたいということでした。関連したものとして、19世紀のマルクス主義の資本概念や入植植民地主義(セトラー・コロニアリズム)の研究、もしくは新自由主義の基本的な枠組みがあるとはいえ、これらはほんの始まりに過ぎません。近年、これらのイデオロギー研究はアクティビストの立場を先鋭化させているように見えることがあります。ですが、そこで分析されているよりも事態はいっそう深刻であるとわたしは言おうとしてきました。植民地化・資本主義化・グローバル化という、ここ500年間のうちもっとも新しく、そしておそらくもっとものっぴきならない変化のうねりに対処できるほど、それらの批判は鋭くはありません。この時代の政治は仮面劇〔的なスペクタクル〕、特別なばかばかしさ、そして政治的耐性菌(スーパーバグ)*1を伴っており、これらに対する広範な批判がなければ、暴力の新しい形態と権威主義的な権力の集中を見逃すことになってしまいます。スーパーバグは、自由貿易地域のような場所であったり、あるいは人物であったりするかもしれず、トランプ、ネタニヤフ、モディ、ボルソナロ、金正恩などかもしれません。これらスーパーバグたちは、新自由主義の時代──わたしたちが知っていると思いこんでいるだけの時代──において完全に孤絶し、また完全ななめらかさを誇る、完全無欠の特殊な権力です。この強権的指導者らの手にかかれば左右のイデオロギーを混ぜあわせたり取り違えさせたりできますから、イデオロギーは信頼に足る指標とはならず、現実の政治的な傾向*2や脅威を示しません。スーパーバグは、〔人々の政治的〕傾向と気質に基づいて動きつづけており、そこから忠誠心を吸いあげられそうな二者択一の闘いをひき起こすために、どんなことでも、どんな嘘でも言ってのけるのです。
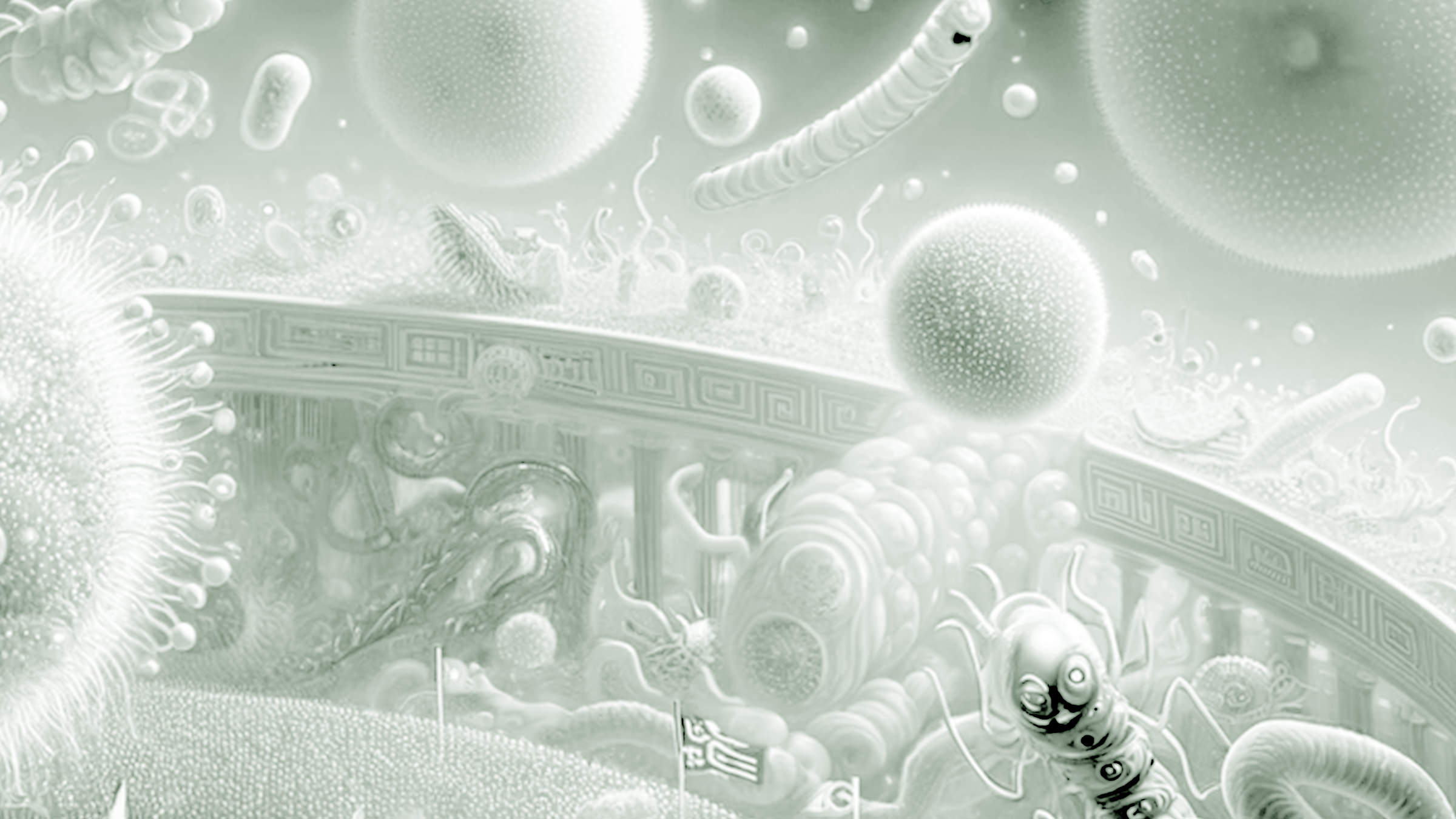
空間的下部構造に介入する実践の可能性
──『メディウム・デザイン』について詳しくお尋ねします。この書籍がもつ政治的なメッセージは、どのようなものでしょうか?
イースタリング人新世という概念の登場やそれに呼応したトランジションデザインの潮流が生まれて以来、デザイナーが負うべき責任は製品の品質のみならず生産体制の検討やシステムの設計にまで及ぶという見方が強まりつつあります。わたしの念頭にあるのは、「人間中心」を謳うデザイン思考を問い直すような脱人間中心主義や脱植民地主義の言説に後押しされた趨勢であり、生態系全体への配慮やトータルな生活様式の変革が希求される機運は随所に見られるように思います。「デザインそのもののリデザイン」(エスコバル)を求めるその種の言説がトップダウン的な志向性を宿しているように読めるのに対して、『メディウム・デザイン』で提示される「空間メディウム(spatial medium)」や「相互作用の空間(spaces of interplay)」といった概念には、より民主的だったり介入的だったりするニュアンスを感じます。かといって、そのスタンスはハックティビズムやForensic Architectureの実践にあるようなボトムアップな市民ジャーナリズムの精神や告発性とも異なり、どちらかと言えば人々をエンパワーすることに重点が置かれているように感じます。そのあたりについて自著解題をいただけますか。
三冊目の書籍である『メディウム・デザイン』は、デザイン思考と空間的な諸実践に対する幅広い文化的な理解を唱えるものでした。オブジェクトとフィールドへの焦点を逆転させ、メディウムに取りくむというアプローチ──じつのところ、わたしのすべての仕事に見られるもの──を採ることで、気候変動から人種差別、不平等、権威主義的な権力にいたるまで世界でもっとも手に負えないジレンマに対する近代優位的/啓蒙主義的/白人的アプローチを揺るがそうとしました。この観点からすれば、唯一の悪もなければ、唯一の包括的な解決策もまたありません。さらに、それよりはるかに悪い多くのものがあるのです。資本主義、ファシズム、人種差別、白人至上主義、フェミサイド〔女性を標的とした殺人〕、カースト、宗教的不寛容、外国人嫌悪、社会病質的リーダーシップなどですね。どれひとつとしてうまくいくはずがありません。包括的な解決策を提案することは、過去500年間の論理(ロジック)を再生産するだけです。
単一的な解決策を示す代わりに、この著書が提示していること。それは、資本という薄っぺらい抽象化を圧倒してしまうような、重たくて物理的な価値をめぐる──つぎはぎになっていたり、でこぼこになっていたりもする──いくつもの登記だとか問題だとかを受けとめられる包容力のうちにこそ、アクティビストのしたたかさと軽やかさは存しているということです。問題はとり除かれるのではなく、むしろより生産的な生態系(エコロジー)のなかで位置を占めることとなるのです。〔生態学的に表現するなら〕遷移ではなく共存を好むこの考え方に基づけば、イノベーションとは輝かしい新技術だけでなく、物事をどのように取りまとめるかという相互作用に関する規格のことでもあります。こうした活動の形式*3によって、〔都市の〕形状と輪郭が描きだされるのみならず、都市空間における相互作用や相互依存のようす、化学反応、連鎖反応も描出されます。デザインの生態系や相互作用の規格は、コンクリートやパイプなどのインフラストラクチャと同様、公共投資に値するような特別な空間的下部構造です。それらがどのようにしてスプロールを逆転させ、交通ネットワークを再編し、共有地を打ちたて、または共同体の絡みあいを作りだすかを、著書に収めた事例研究で扱っています。こうしたアプローチはまた、構造的暴力を是正し、政治的スーパーバグを出しぬくための、空間的アクティビズムに属する道具立てを提供しています。
ここであなたの質問に答えると、こうした諸々の空間は、ヒューマニスト的でイデオロギー的な物語を超えて、こっそりと、言葉になっていないような政治的な可能性を有しています。そこでは「知ること」というよりは「知り方」と言える別種の知識または別様の知の技法が構成されています。だから著書の副題である「世界に働きかける方法を知る」は、いささか誤解を招くものかもしれません。やや自信過剰に響きますね。何しろ、解決主義的な思考*4とは正反対にある精神的な習慣(habit)を伝える意図がありましたから。『メディウム・デザイン』は、過去500年に及ぶ白人啓蒙思想によって害を被ってきたすべての人々のうちに、同調者を見出します。つまり、そうした人々のうちに、ブラック・フェミニスト、廃絶主義者*5、先住民族を見出すのです。長きにわたり、その犠牲者たちは、隠されてきた対抗論理(カウンターロジック)に至るひとつの抜け道を提示してきました。その対抗論理は、必然的に、空間と相利共生に依拠しています。
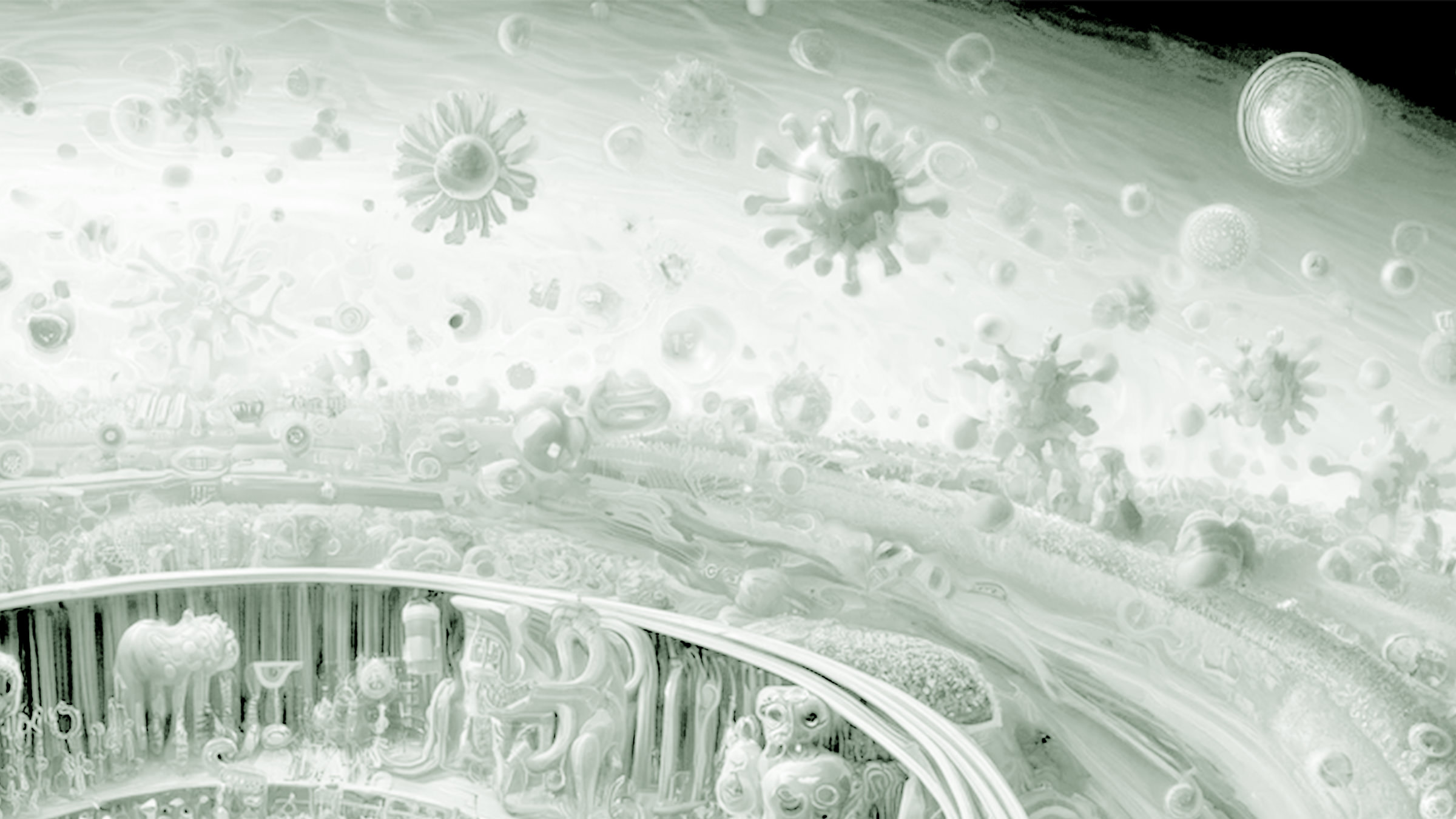
世俗と超俗、資本主義と共産主義、合理と不合理──それらの混ざりあい
──『超国家的国政術』では、例えば国際標準化機構(ISO)を事例とするかたちで、標準化の権力作用に関する分析が行われます。同書が出版されて10年間が経ったいま、この種の権力のうちもっとも現代的なものはなんだと思いますか?
これに関連してわたしが気になっているのは、つぎのような事態です。ウクライナ戦争で北朝鮮がロシアに武力支援を実施しやすいことの背景には、旧共産圏の国々で標準化されていた兵器の規格があるとされます。それはNATO規格とは異なるという点で新冷戦の構造が現われている事例だと言えそうですが、こうした洞察はグローバリゼーション研究の一環であなたの理論を読み解くことで得られるものだと思います。
イースタリングこれは興味深い質問です。なぜなら、いま現在は必ずしも、あなたがたが知っていると思っている新自由主義の時代ではないからです。政治的スーパーバグは、さまざまな古代的でトーテム的な権力のテクニックを展開します──つまり、諸々の衣装と小道具をかね備えたフィクションと信念体系を彫琢するわけです。そしてこの手の衣装や小道具は、ほとんどの場合(ほとんどの場合!)空間的、建築的、都市的なのです。
『無害そうに忍ぶ』には多くの例が挙げられていますが、おそらくもっとも目を引くものは、北朝鮮の金剛山リゾートにおけるクルーズ船ツアー「I Love Cruise*6」に見られる、ツーリズムと全体主義体制に関連したフィクションの混合でしょう。そこではいくつものナラティブが混ぜあわされており、共産主義、資本主義、シャーマニズム、主体(チュチェ)思想、初期キリスト教神学、田園趣味がすべて、〔1970-80年代に放映されたアメリカのロマンティック・コメディである〕テレビシリーズ『ラブ・ボート』さながらの一艘の船上でいっしょくたにされていました。風光明媚な山々、平壌サーカス団、そして買い物村といったすべてものもは、金正日(金正恩の父親にして朝鮮民主主義人民共和国の共産主義王朝におけるかつての頭首)と鄭周永(韓国のHyundai財閥/チェボルのかつてのトップ)が権力掌握のために設えた舞台装置でした。
より現代に近い事例を挙げましょう。〔2024年1月に〕インドのアヨーディヤー〔ヒンドゥー教徒とイスラム教徒が聖地としての所有権を歴史的に争ってきた地域〕にヒンドゥー教の大寺院──それは鋳造コンクリート製の軽薄な作り物です──が再建されました。その際にモディが行なった大げさな落成式には、バーブルのモスクとその破壊につづく暴力の記憶を消し去ろうとする意図が見え透いています。古来の宗教的信念と象徴を抜け目ないプロパガンダと混ぜあわせて運用することで、モディは反イスラム教的なヒンドゥー至上主義国家のなかで権力を集中させています*7。
しかし、別の時代の王や強権的指導者とは異なり、ここで例に挙げている者たちはまた、20世紀の国際機関という合理的で制度的で法規的で世俗的だと考えられている装置すべてを有しています。これらの強権的指導者は、めまいを催させるやり方でイデオロギーを左右に切りかえ、混ぜあわせるのですが、のみならず、大仰なフィクションと合理的な制度という二つの仮面を切りかえさえもするのです。
『超国家的国政術』では、国際標準化機構(ISO)のような機関の事例も挙げました。 ISOは高度に合理化された一連の技術的な規則を統括しています。しかし同時に、ISOは品質マネジメントの基準を開発してきたわけですが、これはつぎのようなものとも結びついているのです──曼陀羅、まじないめかしたジャーゴン、番号付きの作業ステップ、大衆文化のなかのグル的経営者たちが部族めいて組織的にふるまうこととも。〔ISO基準の〕品質マネジメントから〔同種の技法である〕総合的品質マネジメント(TQM)、そして品質マネジメントを乗りこえる試みにいたるまで、これらの営みが打ちだしているのは、鼓舞するマントラのように響く反復的で循環的で金言的な公準です。〔TOYOTAの〕「3M」チェックリストや「5S」活動を思いうかべてみてください*8。あるいは、「4M」チェックリスト*9を、「QC七つ道具」*10を、「九つのムダ」*11を、「五つのWhyとひとつのHow」(意味:問題の原因を突きとめるには、少なくとも五回は「なぜ」と問う必要があり、その後「どのように」修正するかを決める)を、思いうかべてみましょう。
品質マネジメントとは、ソフトロー〔強制力はなくとも人々が従っている規範〕の一種であり、超国家的国政術のなかのエスペラントなのです。
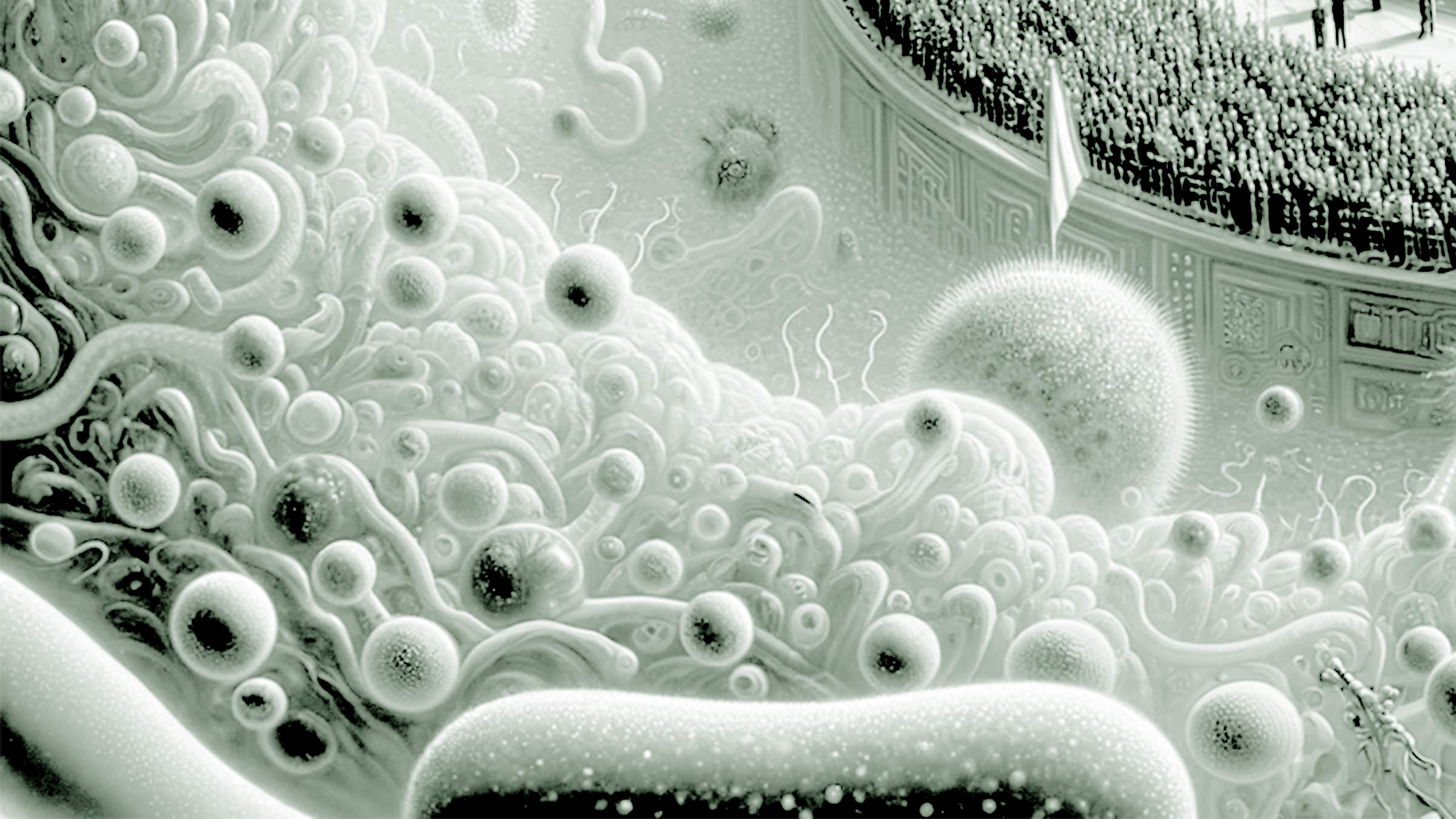
空間のアクティビズムに向けて
──最後に、大局的な質問を投げかけてみたいと思います。現代はさまざまなもののあいだにある境界線が揺らいでいる時代だという認識を、この特集ではもっています。国家と企業のあいだ、戦争と平和のあいだ、人工知能と人間、個人と個人……。こうした境界線の揺らぎとどんなふうに向きあったり、抵抗したりすべきでしょうか?
人間とそうでないものとのあいだにある境界線の揺らぎについて、あなたは著書で語っているようにも読めます。『メディウム・デザイン』では、ラトゥールのアクターネットワーク理論に基づくアクタント概念に始まり、ベネットの『震える物質』におけるモデル、すなわち人間と人間以外の物質をともに「活力ある物質性(Vital Materiality)」から理解する見方が引用されますね。他にも、この論点を考えるうえであなたの数々の著述から想起される諸概念には、つぎのようなものがあります──思弁的実在論、加速主義、空間論的転回(ルフェーヴルを評したソジャ)、移動の社会学(アーリ)……。
イースタリングこの時代のアクティビズムに関するあなたの問いかけについては、いくつかの古典的な技法に頼ることになるのは明らかです。毎日街に出て、これらの強固な権力に圧力をかけることで、支配を退ける。そう行動するだけの十分な理由があります。いつもながらアクティビズムは人を導き、デモ行進し、組合を結成し、暴動を起こし、妨害し、ボイコットし、交通封鎖し、制裁を課し、投資を引き揚げ(ダイベスト)、運動するなど、多くのことを行なうでしょう。そして、あらゆる空間と組織に埋めこまれた一種の「気質」*12としての、環境の操作による暴力や、構造的ないし緩慢な暴力*13──これらを見出す能力をもってすれば、闘うための理由に事欠くことはないはずです。
しかし、従来の戦場とバリケードに加えて、争いの場所はどこにでもあります。単一の悪を問題視して単一の解決策を示すようなアクティビズムは、スーパーバグにとってはあまりにも御しやすいものです。スーパーバグらはアクティビストを悠々とうち負かし、手玉にとるでしょう。より機敏なアクティビストは、その者らが切望している闘いをときには奪いさるという仕方で、スーパーバグを出しぬく方法を知っています。つまり、レバレッジの圧をゆるめるのではなく、むしろ高めるのです。複数の技法を混ぜあわせることこそが不和(ディセンサス*14)を生ぜしめるうえで重要です。不和には、権力を飢えさせ、方向喪失を起こさせる可能性があるからです。そのうえ、このようにつぎはぎであるさま(パッチネス)、そして不一致(inconsistency*15)こそ──〔人類学者の〕アナ・ツィンが示唆するように──、公正なるアクティビズムといういくらか紋切り型の概念に反して、わたしたちにとって真の力となるものなのです。
社会正義・不平等・気候変動への取りくみは、放っておけば継続するいっぽうである有害なパターンを賠償(reparation)することと切り離せません。こうしたことから、主人の家を再生産するような方法で主人の道具を使わない*16という帰結に至る者も、なかにはいることでしょう。しかしいっぽうで、ときには主人の道具に手を伸ばすことで、それらの道具を廃止し、乱用し、形をねじ曲げることにつながりもするのです。賠償を行なうに際して必要とされる実践は、先に述べた抜け道や隠し扉を通って対抗論理に至るもうひとつの通路となるものです。
たとえば、現在わたしは「ATTTNT──賠償のための惑星上の直線」(ATTTNT: A Planetary Line for Reparations)というプロジェクトに取りくんでいるところです。「ATTTNT」はアメリカの公有地に実際に存在する、一種の背骨を明らかにしています。それはつぎのものから成り、すなわち〔アパラチア山脈に沿う自然歩道の〕「アパラチアン・トレイル」(AT)、テネシー川流域開発公社/TVAの土地にあって「涙の道*17」(TT: Trail of Tears)が起こった水路、ナッチェス・トレース・パークウェイ(NT)です。メイン州からミシシッピ州まで3,000マイルに及ぶこの線状の地形は、白人至上主義の物語によって脚色されがちなものですが、黒人と先住民による抵抗と生存の知られざる歴史、とりわけ150年間にわたる黒人の集団的な土地所有という伝統によって、異なる見方/報い(reckoning)を受けることとなります。ATTTNTは、賠償のためのランドトラスト*18によって厚みを増すにつれて、ようやくまとまりを見せはじめるのです。
このプロジェクトでは拡張可能な地理情報システム(GIS)のための一連の規格を開発しており、それがめざすのは私有地と同様に連邦・州・地方自治体それぞれのレベルで土地を査定したり、既存のランドトラストや通行・交通〔に関する使途〕ないし〔歴史的・環境的等の〕保全を見越した地役権〔一定の目的のために他人の土地を利用できる権利〕や湿地を査定したりすることです。ここでは、私的所有の制度を強めるために用いられうる地図ツールが〔乱用されて〕、私的所有を廃することにも、それを共有の資源に戻すためにも使用されています。
白人至上主義の傷やその跡を慎重に再検討するうえでATTTNTが提示しているのは、集約化されてきた土地を示す、見るに明らかな惑星規模の直線です。しかしATTTNTは、社会正義と気候変動と賠償は切り離せず結びついていると主張するものでもあります。このプロジェクトはオルフェミ・O・タイウォのような現代の思想家に協力してもらっています。彼の主張によれば、気候非常事態の前では〔政治的〕賠償が二の次であるということはありえず、賠償それ自体が気候非常事態にも、放っておけば継続するいっぽうである有害なパターンにも対処できる方法であるとされます。
──ご回答くださり感謝します。ありがとうございました。
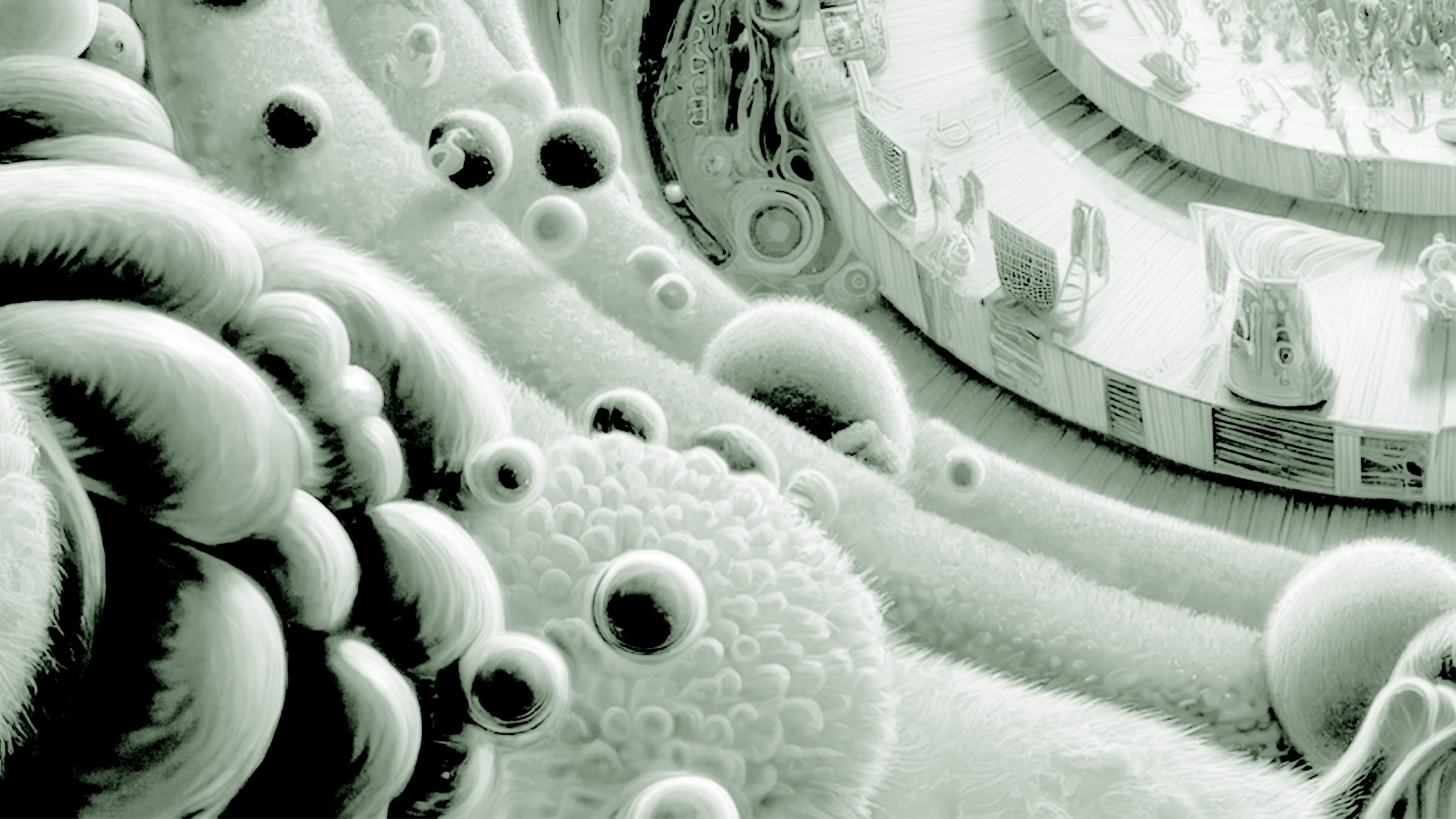
[註]
*1
原語は“political superbug”。スーパーバグは薬剤耐性菌を意味し、抗生物質や殺菌剤に抵抗力を示すようになった細菌の一種のこと。生態学の隠喩で政治と建築を捉えるイースタリングらしい用語法だと言え、『メディウム・デザイン』で詳細な分析が展開される。なお、人種差別に関する議論のなかで、ラッパーのJay-Zもまたトランプをスーパーバグと形容したらしい。
*2
「傾向」と訳した語は“disposition”。イースタリングは『メディウム・デザイン』中でギルバート・ライルのディスポジション論を下敷きとした権力論を展開しているため、ここでは「(政治的)ディスポジション」と訳すのが正しいかとも思いつつ、イースタリング初読者に向けて一般的な訳語を採用するに至った。
*3
原語は”active form”。これはイースタリングによる『メディウム・デザイン』やその他の著述に見られる概念であり、空間が作りだされる際に用いられる先述の「反復可能な定式」や「規格/プロトコル」を一括りにしたもの。”object form”と対になって用いられる。
*4
近年の建築・都市研究における解決主義批判についてはベン・グリーン『スマート・イナフ・シティ』(中村健太郎、酒井康史訳、人文書院、2022年)が参考になる。
*5
「奴隷制廃止運動」を意味する“Abolitionism”から転じて、近年とりわけブラック・ライヴズ・マター以後の“abolitionism”は「それ自体でさまざまな既存の諸制度の根本的廃絶といった文脈で、ひんぱんに使用される」ようになった。
*6
韓国の東海市から出発して、世界中をめぐったのち北朝鮮に至る豪奢なクルーズ船ツアー。朝鮮半島の非武装地帯にほど近い金剛山付近の軍港にも立ち寄る内容であったとされる。このツアーの事業主体は韓国のHyundaiであるとともに、観光事業開発の独占権とひき換えに「6年間で9億4200万ドルを北朝鮮に支払うことになっていた」。参考:Keller Easterling, “I LOVE DPRK”, Harvard Design Magazine, Vol.17, 2002.
*7
インド政府が自らを世俗国家と主張していることは念のため附記しておきたい。
*8
「3M」チェックリストは三つのMから成る「ムダ、ムリ、ムラ」を意味し、「5S」活動は「整理、整頓、清掃、清潔、躾」を意味する。
*9
「4M」チェックリストは、Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)の四要素を精査する品質管理の手法。
*10
「QC七つ道具」は、パレート図、特性要因図、グラフ、ヒストグラム、散布図、管理図、チェックシートから成る。
*11
リーン生産方式における九つの業務改善項目。すなわち、加工が過剰でないか、所作にムダはないか、待ち時間はないか、人事にムダはないか、従業員のエンゲージメントは十分か、余剰在庫のムダはないか、運搬上のムダはないか、過剰生産のムダはないか、不良品はないか。
*12
原語は“temperament”。イースタリング特有の用語法であると思われるため、かぎ括弧を補った。これは『Medium Design』内ではライルを踏まえたディスポジション概念と並べて頻出する概念であり、事物に内在する特性や傾向性を表わしている。
*13
ヨハン・ガルトゥングの「構造的暴力」およびロブ・ニクソンの「緩慢な暴力」概念を参照のこと。
*14
ジャック・ランシエールの「ディセンサス」概念が念頭にあると思われる。おおざっぱに要約すれば、これは合意形成を意味する「コンセンサス」と対置され、意見の一致を見ずに対立した状態から民主主義を考えるというもの。
*15
啓蒙主義の普遍性に対置し、また矛盾(contradiction)と併置するかたちで用いられている概念。参考:Anna Tsing, “Indigenous Voice”, Indigenous Experience Today, Routledge, 2007.
*16
オードリー・ロードの著書『The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House(主人の道具で主人の家を解体することはできない)』やその主張が念頭にあると思われる。
*17
「涙の道」は、ネイティブアメリカンが虐殺を伴って強制移動させられた歴史的出来事。
*18
ランドトラストとは、土地や水を所有・管理する非営利組織のこと。ここでの原文は“reparation land trusts”。主として先住民に対する数世紀にわたる迫害や収奪を償い、謝罪する意図で行なわれる土地賠償(land reparations)や土地返還(land return)の動きに関連したものと思われる。
Keller Easterling
ケラー・イースタリング/建築家、文筆家、イェール建築学校教授。彼女の最新の著書『メディウム・デザイン──世界に働きかける方法を知る』(Verso, 2021/未訳)では、事物のデザインだけでなく、事物がどのように組み合わさるかという意味でのデザインについても考察を重ねる。また、『超国家的国政術──下部構造的空間の権力』(Verso, 2014/未訳)では、政治的な媒体としてのグローバルなインフラストラクチャについて調査している。
太田知也
おおた・ともや/1992年生まれ。リサーチャー、デザイナー。慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 修士課程修了。修士(デザイン)。アート&デザイン領域での執筆・編集実務や展覧会の企画および作品制作に従事。執筆事例に『STUDIO VOICE』(寄稿/特集:「次代のアジアへ──明滅する芸術」、INFASパブリケーションズ、2019年)、『SPECULATIONS──人間中心主義のデザインをこえて』(共編著/BNN新社、2019年)、『クリティカル・デザインとはなにか?──問いと物語を構築するためのデザイン理論入門』(共監訳/BNN新社、2019年)など。

