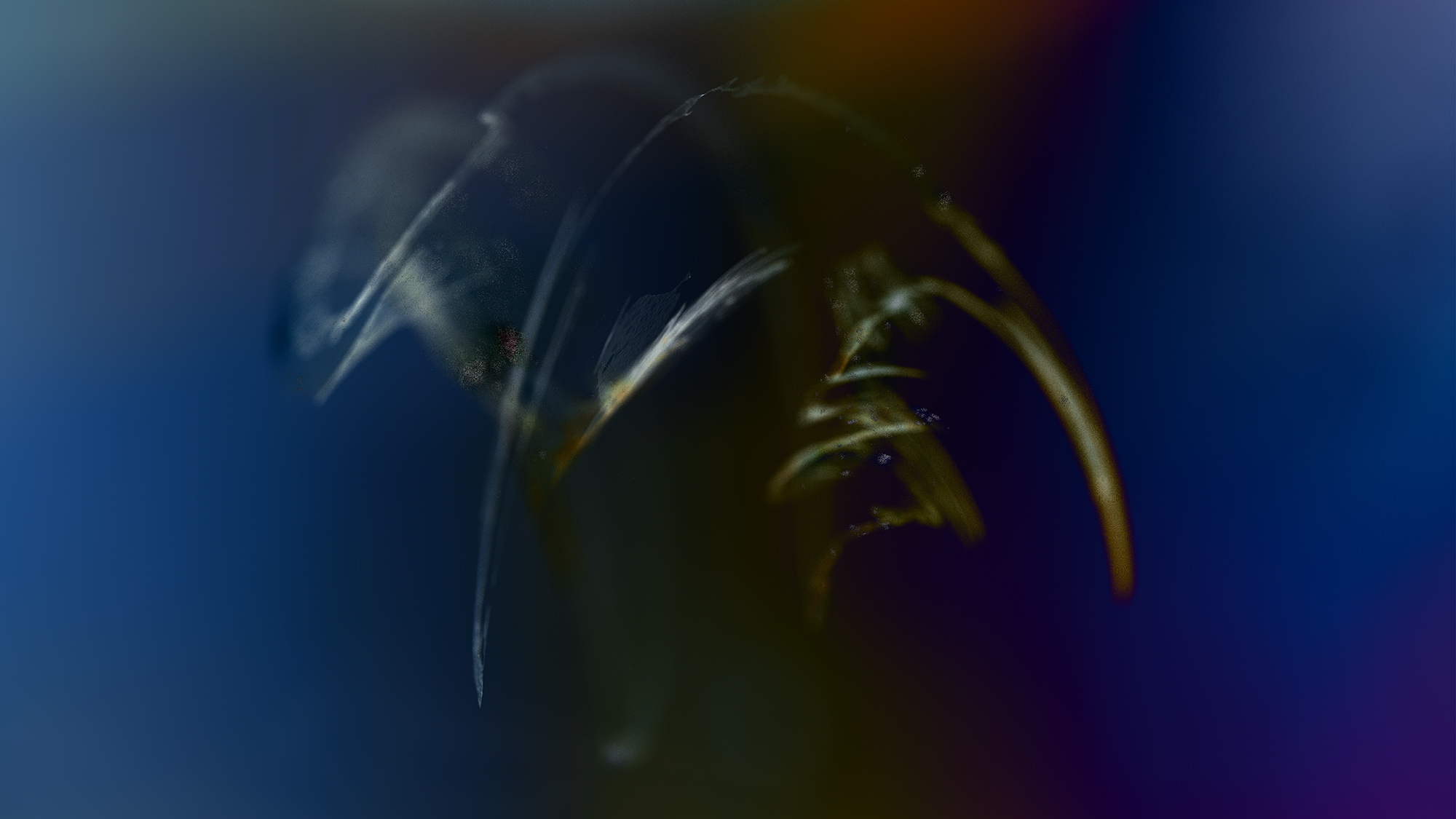
特集_境界線|Boundaries
国家と企業、戦争と平和、軍隊と警察、人間と機械、公的領域と私的領域……近代社会を構成するさまざまな境界線は、いまや激しいゆさぶりをかけられている──。そんな境界線のゆらぎは、《攻殻機動隊》シリーズが、公安9課が、草薙素子が対峙してきたものでもある。たとえば、「人形使い」は、一見不安定に思われる社会システムのゆらぎこそが、むしろ硬直化による破局を防ぐものだと口にする。他方で公安9課は、秩序をゆるがす存在を排除しなければならない使命を帯びている。物語に翻弄される草薙素子は、テクノロジーによって自他の境界をゆさぶられ、自身の「ゴースト」の所在に思い悩む。
情報技術の発展によって否応なく変化を迫られる現実世界と、作品世界で先駆的に取り上げられてきた問題群。本特集では両者を重ね合わせることで、境界線のゆらぎとそのゆくえに迫る。内容は以下の通り。実業家であり研究者の鈴木健は、民主主義の危機を正面から見据えながら、自身の提起した「なめらかな社会」のビジョンを問い直す。建築家のケラー・イースタリングは、自由貿易地域や保税区域、朝鮮半島のクルーズ船観光といった境界線上の空間に分析の目を向ける。神経科学と法学の融合領域である神経法学を研究する小久保智淳は、神経系が操作され、あるいは接続される未来におけるゴーストの所在を論じる。ロシアの軍事・安全保障政策を研究する小泉悠と国際政治・旧ソ連地域研究を専門とする廣瀬陽子は、これまで戦争のなかに閉じ込められてきた暴力が日常化した世界について語り合う。政治思想史を研究する河野有理は、《攻殻機動隊》シリーズの国家観・企業観の変遷をたどりながら、社会を支える公共性や全体性の退潮を指摘する。
特集#03「境界線|Boundaries」の監修を務めるのは、これまで技術の進化と社会の変容をともに論じてきた法哲学者・大屋雄裕。
大屋雄裕おおや・たけひろ/1974年生まれ。慶應義塾大学法学部教授、専攻は法哲学。東京大学法学部を卒業、同大学助手・名古屋大学大学院法学研究科助教授・教授等を経て2015年10月より現職。著書に『自由とは何か:監視社会と「個人」の消滅』(ちくま新書、2007年)、『自由か、さもなくば幸福か?:21世紀の〈あり得べき社会〉を問う』(筑摩選書、2014年)、『法哲学』(共著、有斐閣、2014年)等がある。

