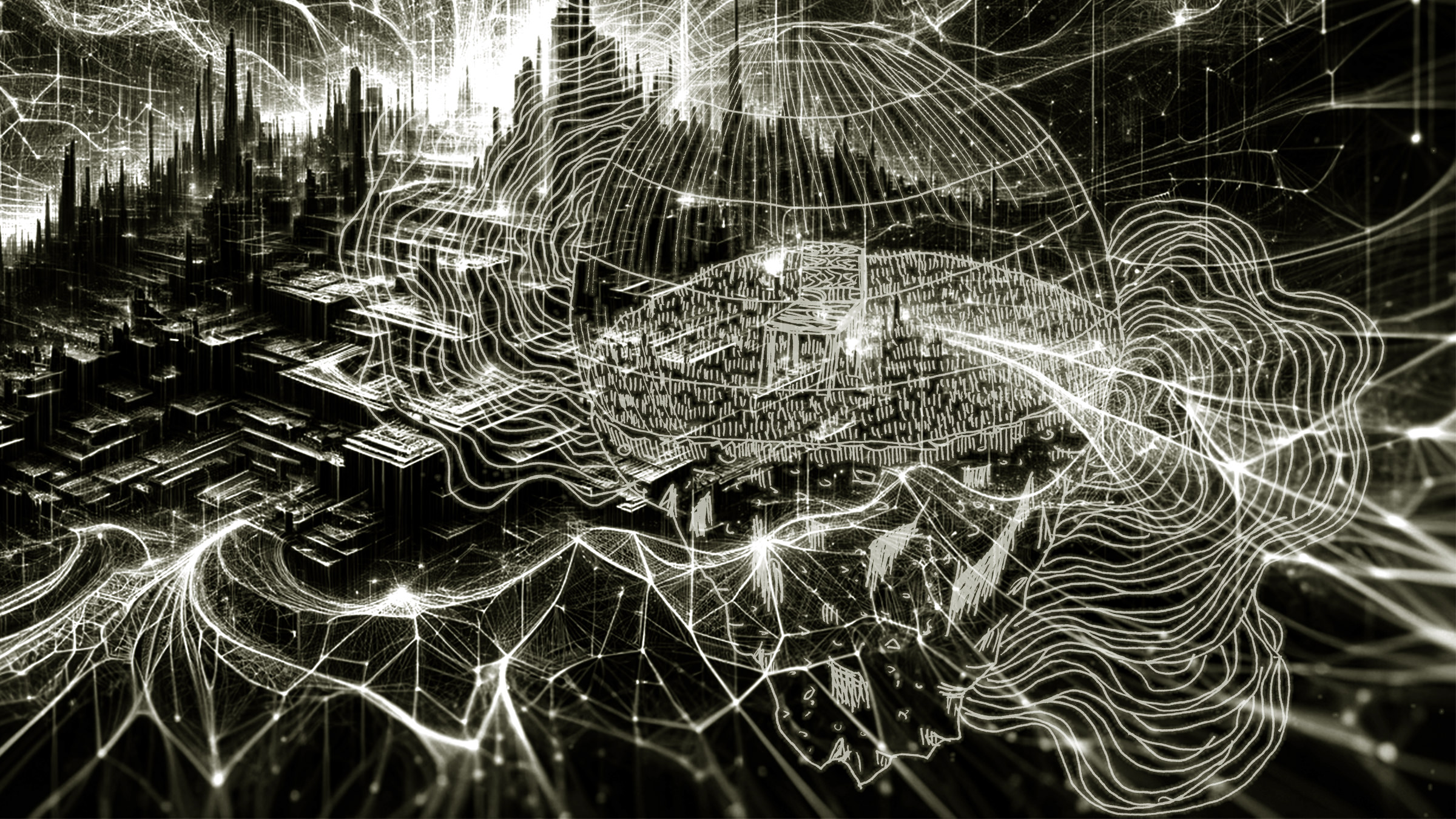
ふたりは冷戦崩壊直前に始まり現代まで続いている《攻殻機動隊》シリーズの国家観・企業観の変遷をたどりながら、現実における国民国家の弱体化やグローバル企業の台頭といった現象を確認していく。そのなかで近世から近代にかけての日本語論や、シンギュラリティ論とその解釈にまで話題は及ぶ。
対談のなかで通奏低音のように流れるのは、社会を支える公共性や全体性の退潮の感覚だ。それは技術と社会に対する黙示録的な認識をもたらすとともに、そのような暗い展望そのものすらたちどころに失墜させてしまう──。そんなダウナーでオフビートな議論に耳を傾けてみてほしい。
目次
国家と企業はどのように描かれてきたか
大屋 《攻殻機動隊》シリーズでは、士郎正宗による漫画版『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』から神山健治監督による最新のアニメシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』まで、作品ごとに国家観や企業観が異なります。まずはそのあたりから対話を始められたらと思います。
河野 漫画版の『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』における国家は、非常に権威主義的でありながら、有能かつ効率的な統治をおこなう存在ですよね。そこにテクノロジーが合わさり、デジタル・エリーティズムとでも呼べるような世界観をつくっている。それに対して、『攻殻機動隊 SAC_2045』に描かれる国家はきわめて脆弱です。さまざまな主体が自前で秩序をつくり蠢く、そんなアナーキーな社会になっていますよね。さらに言えば、この作品の特徴は、シリーズのなかでも、そうしたポリティカル・フィクションの要素が強いところにあるのかなと思いました。
大屋 私も似たような印象をもっています。『攻殻機動隊 SAC_2045』では、公安九課はもはや国の抱える組織ですらなくなり、民間軍事会社の傭兵になってしまうわけですよね。そうしたアナーキーな社会というものは、もはやSF的な未来像とも言い難い。現実に目を向けても、国家を手足扱いするグローバル企業は存在しているし、ウクライナ戦争をみても明らかなように、武装して実力行使する民間組織も当たり前です。メタバースのようなサイバー空間によって、新世界秩序を構築しようという動きもあります。
河野 そんな現実と連動するかのように、シリーズで描かれる実業家たちの姿も変化していますよね。これまでの作品では、企業組織を牛耳るのは大資本家であって、国家と手を組んで暗躍しており、そこには国家独占資本主義のようなモチーフがありました。しかし『攻殻機動隊 SAC_2045』では違います。国家の存在感は薄くなっていて、イーロン・マスクのような起業家の方がむしろ印象的です。その姿は効果的利他主義や長期主義といった考え方に取り憑かれた、カリフォルニアのお金持ちを彷彿とさせます。
公共性のゆくえ
大屋 おっしゃるとおりだと思います。現実に目を移せば、国家の退潮によって、グローバル企業が擬似的に公共性を担っている側面も登場しているでしょう。
ひとつ例をあげてみたいのですが、コロナ禍において、日本政府がCOCOAという接触確認サービスをリリースしました。これは大変不評でして、その一因はGPSで取得したを位置情報を利用することができず、特定の場所で発生した集団感染の検知や追跡に役立たなかったからですね。なぜできなかったか。AppleとGoogleが政府に位置情報を使わせなかったからです。彼らの言い分では、政府が人民の位置情報を手に入れてしまったら、なにをしでかすかわからない。たとえば、反政府組織と接触した人間を監視し、特定するというようなことができてしまうというわけです。
ここでは、国家はむしろ市民の権利を侵害する存在であって、反対にグローバル企業こそが自由の守り手として動いているようにみえる。なぜなら、彼らは商売のサステナビリティに配慮せざるをえず、そのためには顧客が長期的に存続してくれなければならないですよね。また、経済界でのレピュテーション・リスクを考慮して、あんまり阿漕なことはできない。近江商人の三方良しのような発想で、私利私欲が抑制され、擬似公共性が実現しているのではないかということです。もちろん、企業は企業ですから、私たちは顧客を保護しその自由に配慮しているのだから安心してiPhoneを買ってね、というイメージ戦略にすぎないかもしれない。つまり、「得」と「徳」を結びつけているにすぎないと言われたらそれまでなわけですが、少なくとも見かけ上は、そのように振る舞っているのです。
河野 一方には効率性を追求する国家、あるいは邪悪な意図をもつ国家があり、テクノロジーを利用して市民を監視しようとしている。もう一方にはグローバル企業があって、こちらはむしろ個人の人権を世界的に守ろうとしている。そんな図式があるというわけですね。
ただ、仮にそうした擬似公共性なるものがあったとしても、グローバル企業がそれを維持し続けることができるのか。その公共性は、大屋先生が言うように、あくまでも得と徳の結びつきのなかで実現しているにすぎないとも言えます。これに対して、国家の場合、失敗国家や破綻国家ではないのであれば、経済的な利害とは無関係に、国民を国民である限りにおいて守ろうとする。やはり両者の違いは大きいのではないでしょうか。
大屋 もちろん、その通りです。実際、多くのグローバル企業は問題を抱えているし、イスラエルのNSO Groupのように、とんでもないケースもあります。この会社は危険な人間を監視する「ペガサス」というスパイウェアを開発していて、各国政府や治安機関を相手に商売をしています。あるときペガサスを利用していたスペインで、首相と国防省の携帯電話がハックされてしまったんですね。そうなったとき、国内の治安機関で使われているペガサスが暴走したのか、外国の政府に工作されたのかわからない。NSO Groupもその情報を開示しない。まったく公共的な責任を果たそうとしないわけです。
しかし、まさに失敗国家や破綻国家についても触れていただいたように、公共性の担い手としての国家をどこまで信用できるかわからなくなってきていることも事実だと思うんです。憲法学者の愛敬浩二さんは、1990年代ころから立憲主義というキーワードが急に論文のなかで増えたと指摘しています。民主主義が機能しなくなった結果として、憲法規範という外在的なものに頼る議論が出てきているというわけですね。人民が選挙を通じて国家をハンドルするというビジョンは世界的に信じられなくなっている。これは日本においてもそうでしょう。私自身は、日本は1990年代以降に4回の政権交代を経験してるわけで、選挙も民主主義もある程度機能しているよとも言いたくなりますが……。
このように考えていくと、古典的な公と私の対立を持ち出すよりも、国家だけが公共性の担い手なのではなくて、さまざまな主体が公共性を担っているのだという連続的な認識のほうがリアリティをもつように思えるのです。
河野 なるほど。たしかに、歴史を振り返れば、そのほうが実態に近いのかもしれません。「欲望としての市民社会」を国家が統制しつつ公共的なものを具現するというヘーゲル的なビジョンのほうが、歴史的にはむしろ近代社会に特殊なもの。
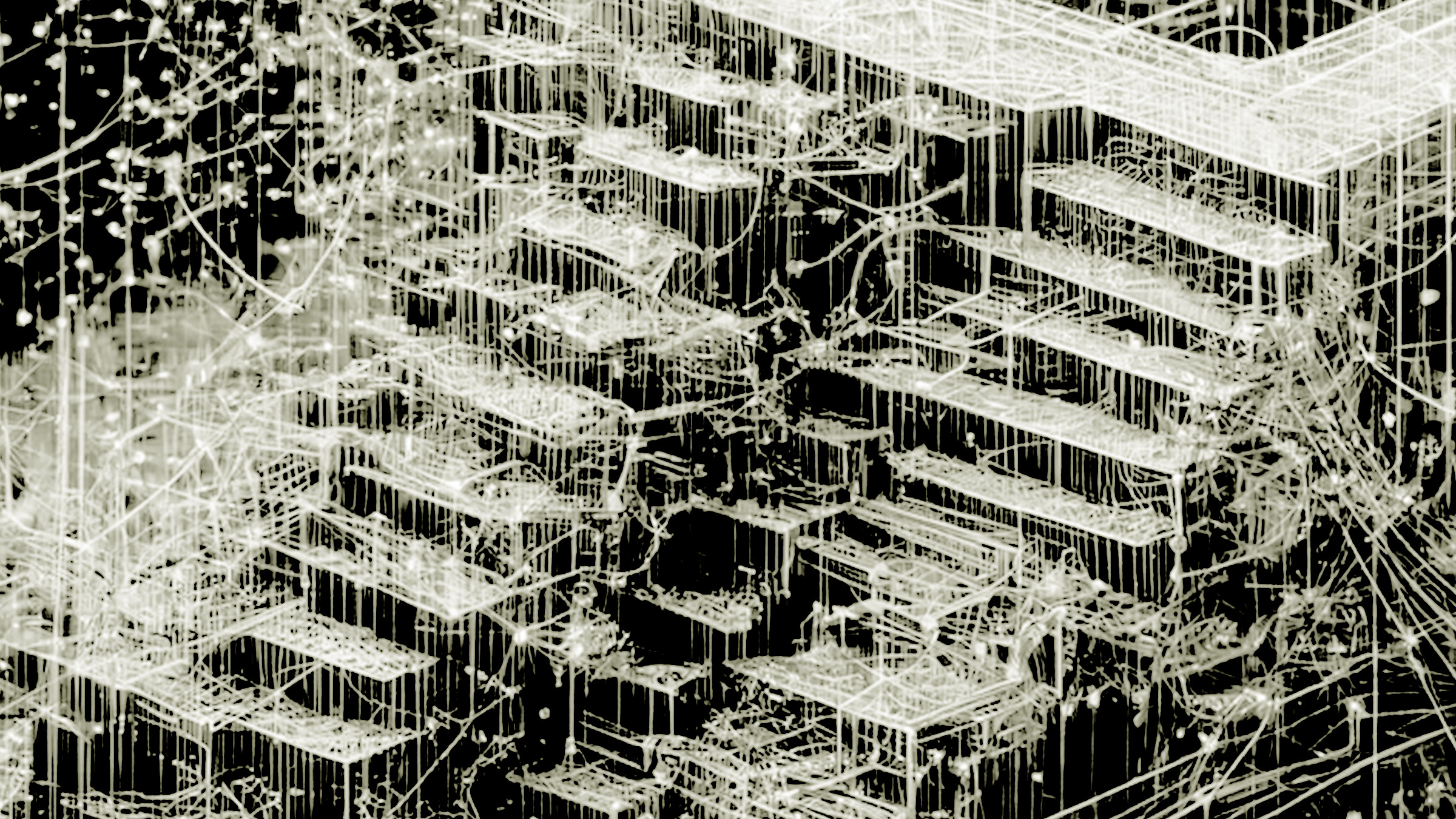
福沢諭吉の分裂
大屋 こうした問題は、河野さんの専門である日本思想史においてもみられると思います。たとえば、福沢諭吉は「中津留別の書」において、一心独立し、一家独立して、一国独立し、一国独立して、天下も独立すべしと言っていますよね。個人は自ら身を立てるのだけれども、それはただ野放図な私欲の追求ではなくて、他者を抑制せず、共存する限りでの独立である。ひとりの独立から、一家の独立がなされて、健康で健全な経済社会ができて、国家がそれを基礎として立つ……これは言ってみれば、公益と私益が結合的で一体的となったビジョンではないでしょうか。
河野 たしかに、福澤はその両立を確信しています。両者は必ずセットになっていますね。ただ、よく考えてみると、両者が常にすぐに一致するかどうかはよくわからないところがあります。一身の独立の追求と一国の独立の希求が確かに一致して見えた、明治維新期という稀有な時代を生きていたというだけのようにも見えてしまう。
別の言い方をすれば、福澤は分裂した思想家だとも言えます。一身独立と一国独立のどちらに比重をかけるかで、まったく異なる姿を見せるわけです。一身独立を強調すれば、国家に頼らなくても生きていけるグローバルエリートになれと言っているようにみえてくる。他方で、一国独立のほうに目を向ければ、負けそうだからといって国を捨てるようなコスモポリタンはダメで「やせ我慢」で踏みとどまるやつらが集まってこそ、最強の国家ができると言っているようにも見える。
その後の日本思想史のなかでの福澤の「読まれ方」もこの分裂を反映しています。たとえば、丸山眞男のように「市民社会」を重視したと思われがちな思想家が、福澤に関しては国民国家を形成するために強い主体意識に注目する。他方、丸山へのアンチとして現れた坂本多加雄のような国家主義者が、福澤について国家の強制に頼らない自生的秩序の模索を評価するといったような。
大屋 なるほど。法学の世界でも、国家主義と普遍主義が結びついたり、それがまた分かれたりといったことはあります。たとえば、19世紀ドイツの法学者でフォン・サヴィニーという人がいますよね。彼はドイツの歴史法学の祖である一方で、ローマ法学者でもあります。そんなサヴィニーは、当時のドイツで盛り上がっていた統一民法典編纂に対して、拙速だと反対しました。彼は法の根源には民族精神が必要だと説くのだけれども、それはドイツのナショナリズムによる国家主義的なものではなく、まさにローマに由来する普遍主義的なものでなくてはならない。だから歴史的起源としてのローマ法の探求こそが必要であって、現段階での法典編纂はありえないと考えたわけです。
しかし、その後の世代では、ヤーコプ・グリムのような人が現れて、ローマ法の影響を排し、ゲルマン民族そのものの歴史を探ろうというゲルマニステンと呼ばれる国家主義的な方向性や、反対に、ローマ法の体系を精緻化することで法秩序が自ずから浮かび上がるというロマニステンの普遍主義的な方向性へとはっきり分かれていきます。
日本語をめぐる問題
河野 グローバルかつアナーキーな経済社会の出現という問題に戻りたいのですが、実際のところそうした社会において困るのはどのような人たちでしょうか。何億もの金融資産をもち、プライベートジェットで世界中を飛び回れたりするようなエリート層にとって、国境はあまり関係がありません。反対に、その日暮らしのプレカリアートやアンダーグラウンドな層もまた、国家との関係は薄い。日本ではまだイメージしづらいかもしれませんが、食い詰めてしまったら稼げるところに国境を越えて移ってしまおうという身も蓋もない現象は、世界的にはよくあることです。
そうだとすれば、両者の中間層が問題になると思うんです。階層的に上位の層と下位の層はどちらもグローバルなのだけれども、中間層だけは違っている。彼らは国家の担い手であるとともに、逆に国家に依存してもいるわけですから。
大屋 日本社会について言えば、中間層の行く末は、人口問題によるところが大きいと思いますね。生産年齢人口というのは、15歳から65歳までとテクニカルには定義されていますよね。この人たちが両側を支えられなければ、どの国でも社会福祉は回らない。しかし、日本の場合、2040年ころには、生産年齢人口とそれ以外とが1対1ぐらいになってしまいます。もし中間層を維持したいのであれば、すでに海外からたくさんやってきている労働者を社会のなかにインクルードしていくほかないはずです。
河野 まさに、そう思います。日本政府は頑なに移民という言葉を使わないようにしていますが、彼ら彼女らの存在を承認し、同じ社会の一員だという帰属意識意識を持ってもらえるように社会統合を進めていくほかないですよね。卑近な例ですが、私自身が子育てをしているなかで、子どもが保育園に通うようになったとき、いろいろなルーツをもった家族がいました。東南アジア系の3世で、両親も子どもも日本語がペラペラの家庭があったり、お父さんは日本人だけれども、お母さんはそうではなくほとんど日本語が話せなかったり。
このような問題をめぐって、日本思想史のなかで意義深い研究があるとしたら、明治期の日本語論ではないかと思います。私が研究している明六社においては、思想家の西周が『明六雑誌』創刊第一号の巻頭論文として日本語論を書いています。江戸時代の政治体制はきわめて分権的なもので、日本語も多様でした。そんな時代から、いかにして均一な国民国家とそれにふさわしい日本語をつくりだすかが問われていたわけです。明治維新のときには、漢字を廃止してすべてかな文字にしようとか、ピジンイングリッシュでいいから全部英語にしてしまおうとか、いろいろな考え方がありました。西周の場合、日本語は残すけれども、それをあらわす文字はローマ字のほうがよい。そのほうがかえって日本語が保存できるのだという論説を展開しています。当時おこなわれた議論は、ダイバーシティが増していく日本社会をどうしていくか考えるうえで、きわめて現代的な意義があると思います。
大屋 私は名古屋大学で勤務していたころ、西三河の安城市に住んでいたことがあります。安城はブラジル系の工場労働者がたくさんいるので、役所から送られてくる広報誌には、ポルトガル語と英語のページがありました。役所の窓口も多言語対応していたし、災害の避難情報はピクトグラムになっている。
日本語は実は話者の数が多い言語なのですが、特徴はその分布にあります。ネイティブのほとんどが日本列島に住んでいるので、この島でだけ快適な言語なんですよね。これは外から中に入ってくる場合にも、中から外に出る場合にも障壁になっていました。地理的な条件と合わせて、中間層の形成に寄与していたのだろうと思います。韓国なんかも条件は近いですが。このような国において、日本語の未来をどのようにしていくべきかは、必ず議論しなければならないでしょう。
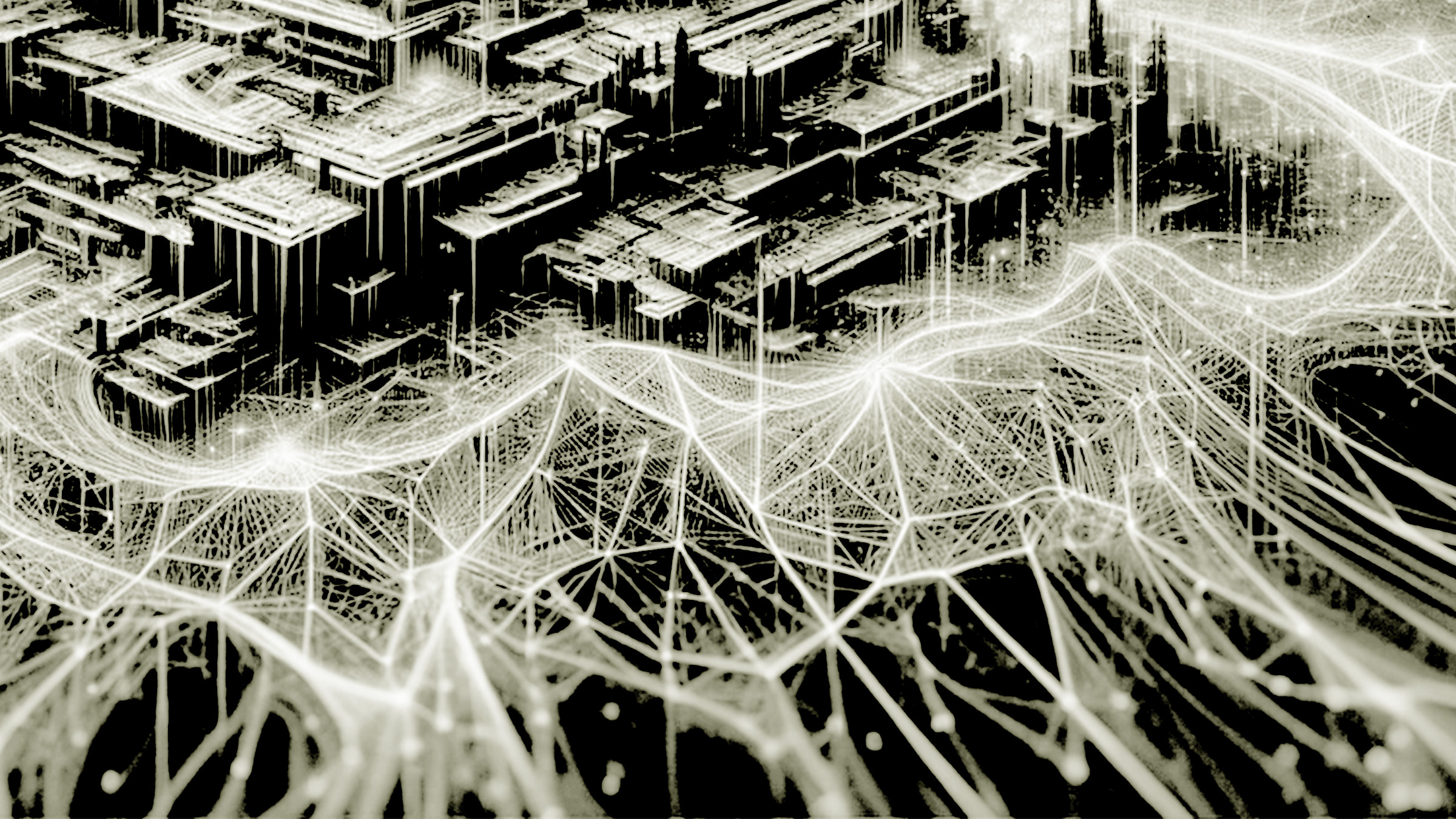
国民国家の黄昏
大屋 日本では人口や言語の問題が大きいですが、いずれにせよ統合的な分厚い中間層がいなくなってしまえば、おそらく国家は企業体や宗教体と対抗しうるような中心性を喪うことになりますよね。
そうした世界になっていくとした場合に、私は法律家だからかもしれませんが、特に気になるのは、紛争処理と情報の信頼性です。リバタリアニズムやアナルコ・キャピタリズムを信奉する人たちであれば、紛争処理は最高裁判所がなくても仲裁会社がなんとかしてくれるだろう、貨幣システムは中央銀行がなくても複数の通貨がその信頼性を競い合えばいいだろうと考えるかもしれません。しかし、そううまくいくものかなと。
河野 私は以前、明治期の思想家・田口卯吉について書いたことがあります。彼には先ほどの福澤にあったような個人と国家のあいだの分裂はみられず、明治初期のアナルコ・キャピタリズムをその後も手放さず発展させていきました。彼の構想は自己利益を追求する市民によって商業共和国を形成するというものであって、きわめてグローバルですが、それでも国家の存在は前提とされています。なぜなら、日本の場合、もちろん明治維新は大変な激動であったけれども、本当のアナーキーとは言い難かったからです。日本語のかたちがどうなるかもわからなかったけれども、人口は3000万人ほどいて、中央政府らしきものもあった。地の利もあり、国境も大半は明らかでした。
日本思想史において、中央政府が誰かもわからない、どの貨幣が使えるかも市場によって違っている、それほどまでに信用が自明でない世界というものは、中世や戦国時代にまで遡るでしょうね。ソマリアと日本の室町時代の類似性を指摘した、『世界の辺境とハードボイルド室町時代』(高野秀行、清水克行著、集英社インターナショナル、2015年)という本がありますよ。どちらも失敗国家というべき状態でめちゃくちゃなんですが、裏を返せば、国家がなくなってもみんな死んでしまうわけではなくて、人間はもやもやと生きていくのだということがわかります。2045はそういう世界を描いていると思うし、部分的には、いま起ころうとしていることでもある。
大屋 探検家の高野秀行さんと日本史の清水克行先生の対談ですね。清水先生の『喧嘩両成敗の誕生』(講談社、2006年)には、酒屋の妻を寝取ったか寝取らないかという些細な揉め事から、お互い仲間を呼び合い、京を二分する戦争になりかけたという話があります。最終的には将軍が諌めて収まったそうですが、紛争処理をする最終審級が必要だというわかりやすい例ですよね。
ほかに秩序の構想としては、国民国家によるものでもアナーキズムやグローバル企業によるものでもなく、カントの考えるような世界政府であったり、国民国家をもう少し細かく分割する、日本で言えば道州制のような考え方もあったりしますが、やはり現実性には疑問が残ります。
河野 世界政府について言えば、はたして別のところに暮らしている人間を自分と同じ存在だと思えるかという、ある種の人間観の問題になると思うんです。ふたたび福沢諭吉に戻れば、彼はナショナリストでありながら、いやナショナリストであればこそ国際的連帯というような発想があったのではないかと思います。たとえば、福澤はヨーロッパにおける人権概念を検討するうえで、武士の一分という考え方を持ち出します。武士ならば、どれほど細腕でやせっぽちであっても、強い相手に立ち向かわなくてはいけないときがある。合理的経済人であれば逃げることが正解だけれども、そこで対等に戦うことによって武士の一分を勝ち取る。こういった伝統を呼び出すことで、ヨーロッパの国々の人権概念を、日本というまったく異なる文化的背景をもつ国でも理解可能なものにしようとするんです。西洋にも武士がいるのだ、というわけですね。
私はこのようなプロセスを踏まず、平板に世界政府を実現することはできないと思います。無政府主義についても同様です。アナキストたちは、相互扶助という考え方が好きですが、そこに誰もが開かれているのかは疑問があります。強力な徒党の内部であれば相互扶助が実現できるかもしれないけれども、そこに入っていくにはネットワーキング技術が必要だし、しぶとさもしたたかさも必要でしょう。それは弱者にとっては過酷なことです。地方分権はもう少し可能性がありそうですが、どの単位で地域を分ければよいのか。仮に合理的な区分けがあったとしても、歴史的な経緯を踏まえれば、それを実現することは簡単ではありありません。そうした「線引き」の安定性を担保するのはやはり逆説的ですが強力な中央政府の権威ということになるでしょう。
そうなれば、これまでそれなりには機能してきた国民国家という単位をだましだまし使っていくということにならざるをえない。もっとも、我々はこのような議論をする一番最後の世代であって、いわば近代の黄昏に佇んでいるということなのかもしれませんが。
黙示録とその終わり
大屋 国民国家の弱体化をいつごろからとみるかは難しいですが、1989年に連載が開始された士郎正宗の漫画版《攻殻機動隊》では、まだ冷戦が続いていた時代の空気が残っていますよね。なんらかの戦争が終わったあとの世界だけれども、そこには敵対国家もいるし、ソ連もある。
これに対して、1995年に公開された押井守の映画版《攻殻機動隊》は違います。そうした国家の問題は前景化せず、個人の実存の不安が顕在化している。彼自身がポスト全学連であって、運動をはじめようと思ったら、もう終わってしまっていた。そんな感覚が現れているようにも思います。
国家間の対立があって、それぞれに国益がある、その間で裏切り者が現れて……冷戦の終結とともに、そんなスパイフィクションのような世界が終わったことはたしかですよね。ただ、そのなかでフランシス・フクヤマは『歴史の終わり』において、歴史が終わったとまで言い切ってしまった。
河野 士郎正宗の漫画版《攻殻機動隊》については、当時私は『ブレードランナー』をはじめとするサイバーパンクのムーブメントのなかで読みましたが、冷戦期のSF作品に多かれ少なかれ共通するのは、カタストロフィの予感であった気がします。それが起きたら「歴史」がそれ以上動かないというような押井守の『ビューティフル・ドリーマー』もそうですね。
この感覚は、丸山眞男にも通じるかもしれません。彼の戦後の仕事は、ある意味で黙示録的なんですよね。冷戦の最中というのは、日本を含む西側諸国ではそこそこ安定的な暮らしが実現していました。それにもかかわらず、丸山はずっと世界の終末を意識しているように見えます。どういうことかといえば、核戦争の恐怖にずっと怯えているんです。次に核が使用されたら世界は終わるという強い感覚がある。今読むと、結構びっくりします。
こうした丸山の感覚に対して反論していた人もいます。たとえば国際政治学者・永井陽之助です。丸山は全面戦争の可能性を言うけれども、冷戦中であっても、実際には各地で核を使用しない通常戦がおこなわれているではないかと。丸山の黙示録的な世界観よりは、永井の主張は現代的な感覚のほうがポスト冷戦、ポスト311の感覚には近いのかもしれません。実際には、原発事故はもちろん悲惨なものであるし、被災者は故郷を追われて大変なことになる。けれども、人口の大多数はそれでも日常生活を続けていくわけで、それはそれで歴史が終わるようなカタストロフというべきものでは全くない。カタストロフィと同じではないですね。
大屋 第二次大戦以降、戦時国際法が想定してきたような、大文字の戦争としてのザ・ウォーはなくなりました。しかし、小文字のウォーはなくならず、そこら中にはびこる。アメリカとソ連が直接殴り合うことはしたくないから、朝鮮半島のように代理戦争がおこなわれた。冷戦以降も、低強度紛争であったり、テロであったり、あるいはフェイクニュースであったり。終わりなき日常の裏側で終わりなき地獄がおこなわれているわけですね。これはパンデミックについても同様で、コロナウイルスによってたくさんの人が亡くなったけれども、スペイン風邪と比較したら、たいしたことはなかったと感じられてしまう。ウクライナ戦争やガザ紛争についてもそうです。多くの血が流れているのだけれども、我々の日常はそれとは無関係に続いていく。
アポカリプスがあったら全世界が等しく影響を受けるのだから、全員で抑制的に振る舞おうというような認識が壊れてしまったわけですよね。むしろ、なにかあったら困るのは当事者だけであって、弱い立場の人たちに負担を押しつけるだけ。一部のスーパーエリートはもちろん、先進国の中間層も案外のうのうと生活を続けることができてしまう、そんな世界像が現れてきた。もちろん、ウクライナ戦争が戦略核兵器を用いるものへとスリップし終末へと向かう可能性はないとは言えませんが、少なくとも、それで世界が終わると一般には考えられていないですよね。
河野 1990年代になると、国内では宮台真司が、終わりなき日常について語るようになりましたよね。これはレトロスペクティブにみると、必然的であったように思えます。しかし、大屋さんが整理してくれたように、冷戦が終わったあともダラダラと歴史は流れていって、終わらないということ自体が終わらない。いまはそんな感覚のほうが現実に近いと思うんです。
大屋 冷戦という大きな物語が終わったあと、それでもギリギリのところで全体性の感覚を支えていたリベラルデモクラシーすらも機能しなくなった。いわゆる「新しい中世」的な、中心がみえない時代になっていますよね。
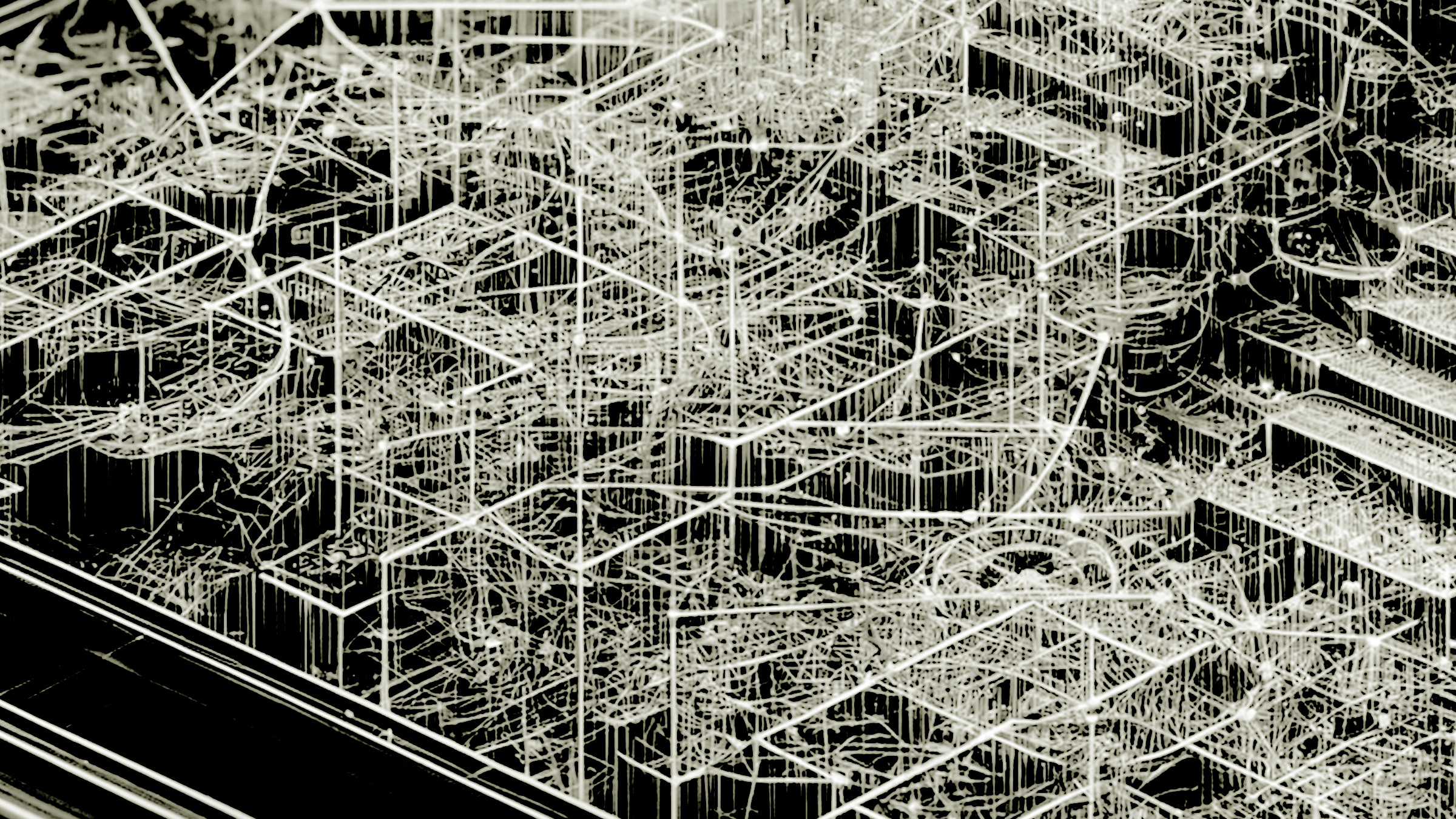
暗い進化の時代に
大屋 公共性の担い手の変化から、それを支える全体性の感覚そのものの退潮へと議論が及びました。最後に、テクノロジーと未来について考えてみたいと思います。2010年代の後半には、レイ・カーツワイルのシンギュラリティという言葉が流行りましたよね。彼の議論は、まさにアポカリスティックなもので、AIの台頭とともに超人類が現れ、そこで人類の歴史は終わるというわけです。
これに対して、中西崇文の『シンギュラリティは怖くない:ちょっと落ちついて人工知能について考えよう』(草思社、2017年)には、興味深い議論があります。将棋を打つ能力や正確に計算する能力だけで言えば、AIはすでに超人類なのであって、人間知性の捉え方次第では、我々はむしろシンギュラリティの過程を生きているでしょうと。では、それでも人間の暮らしが破綻しないのはなぜかといえば、ある技術をつくるかつくらないか、それを使うか使わないかは、結局のところ人類が決めているからだと言うわけです。人間にとって不利なことが起こるような技術は世に放たれないはずだと。
もちろん、誤って事故が起こる可能性はあります。ロシアがアメリカ大統領選挙に勝つために、フェイクニュースを生成するAIを野に放ち、それが世界にはびこってマスメディアの基盤が破壊される……そんな未来もあるかもしれません。しかし、いずれにしても、人類はそうした可能性について配慮し続けるだろうというわけです。人間にとってみれば、いつまでたっても技術のガバナンスに汗をかき続けなければならず、そこから解放される未来はないということでもあります。
河野 シンギュラリティに期待するような論調は、あっという間になくなってしまいましたよね。
それを聞いて、私はショーペンハウアーとニーチェについてジンメルがくわえた整理を思い出しました。ジンメルによれば、ふたりはともにカントの深い影響のもとに、現象と物自体を厳密に区別します。現象の世界は因果律によって支配され、因果推論によってあらゆることが説明されるものであり、他方で物自体の世界というのは、我々には到達できないものだとされます。そのうえでショーペンハウアーは、それでも人間は物自体の次元に属するような生きる意志を直観してしまうのだといいます。それぞれの生には結局苦痛しかないにも関わらず、物自体の次元に到達しようと藻掻き苦しむわけです。この考え方は反出生主義の思想的根源にもなっています。他方で、ニーチェはまったく別の結論を導きます。我々の生は無意味なのだけれども、だからこそ、それぞれがアドベンチャー・オブ・ライフを続けていくのであって、それによってベルグソンであれば創造的進化と呼ぶような、ポスト・ヒューマンのようなものがいつか出現するかもしれない。そんな超人思想に至るのです。言ってみれば、同じカント的な枠組みから、ダウナー系のビジョンとアッパー系のビジョンがそれぞれ提出されているとジンメルはみているわけです
この整理に倣えば、もともとの《攻殻機動隊》にはニーチェ的なアイデアがあったのだけれども、シリーズを重ねるごとにショーペンハウアー的なものへと移っていっていると言えるのではないでしょうか。これは同作だけにみられる傾向というより、テクノロジーによって人類が人類そのものを超えていくというアッパーな認識が退き、それはもはや人々に勇気を与えるものではないというダウナーな認識が前景化するという時代の変化を表しているように思います。
大屋 なるほど。それと主人公である草薙素子の意志の関係が問題になってきそうですね。絶対悪としてのテロリストの排除など素子には一貫した思想がいくつかありますが、なかでも重要なのは成長や変化に対する意志です。士郎正宗の漫画版や押井守の映画版では、ある種のAIと自分との間に、変化しつつも維持される秩序を組み込めるかがテーマになっています。それが『攻殻機動隊 SAC_2045』では、メタバースによって世界の秩序がスタティックなものになってしまうと考え、それを拒否しました。河野さんの整理でいえば、まさにテクノロジーそのものにポジティブな期待を向けることが難しくなってきた状況で、変化しつつも維持される秩序をいかにしてつくりだすか。そんな視点でシリーズを見守りたいと思います。
河野有理
こうの・ゆうり/1979年生まれ。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。日本政治思想史専攻。首都大学東京法学部(当時)教授を経て、現在、法政大学法学部教授。主な著書に『明六雑誌の政治思想』(東京大学出版会、2011年)、『田口卯吉の夢』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『近代日本政治思想史』(編、ナカニシヤ出版、2014年)、『偽史の政治学』(白水社、2016年)、『日本の夜の公共圏:スナック研究序説』(共著、白水社、2017年)がある。
大屋雄裕
おおや・たけひろ/1974年生まれ。慶應義塾大学法学部教授、専攻は法哲学。東京大学法学部を卒業、同大学助手・名古屋大学大学院法学研究科助教授・教授等を経て2015年10月より現職。著書に『自由とは何か:監視社会と「個人」の消滅』(ちくま新書、2007年)、『自由か、さもなくば幸福か?:21世紀の〈あり得べき社会〉を問う』(筑摩選書、2014年)、『法哲学』(共著、有斐閣、2014年)等がある。

