
国家と企業、戦争と平和、軍隊と警察、人間と機械、公的領域と私的領域……本特集「境界線|Boundaries」の監修を務めた法哲学者・大屋雄裕の問題意識は、近代社会を構成するさまざまな境界線と、そのゆらぎに向けられている。
ゆらぐ境界線は、《攻殻機動隊》シリーズが、公安9課が、草薙素子が対峙してきたものでもある。大屋はそのように分析して、情報技術の発展によって否応なく変化を迫られる現実世界の問題と、作品世界で先駆的に取り上げられてきた問題とを重ね合わせる。
両者を結びつけるのは、政治学者・五百旗頭薫による印象的な表現「昆虫化」だ。生物的なメタファーを引くことで、大屋の議論は境界線のゆらぎがもたらす危機と変容の可能性へと向かっていく。これまで技術の進化と社会の変容をともに論じてきた著者が記す、本特集を俯瞰するような編集後記。
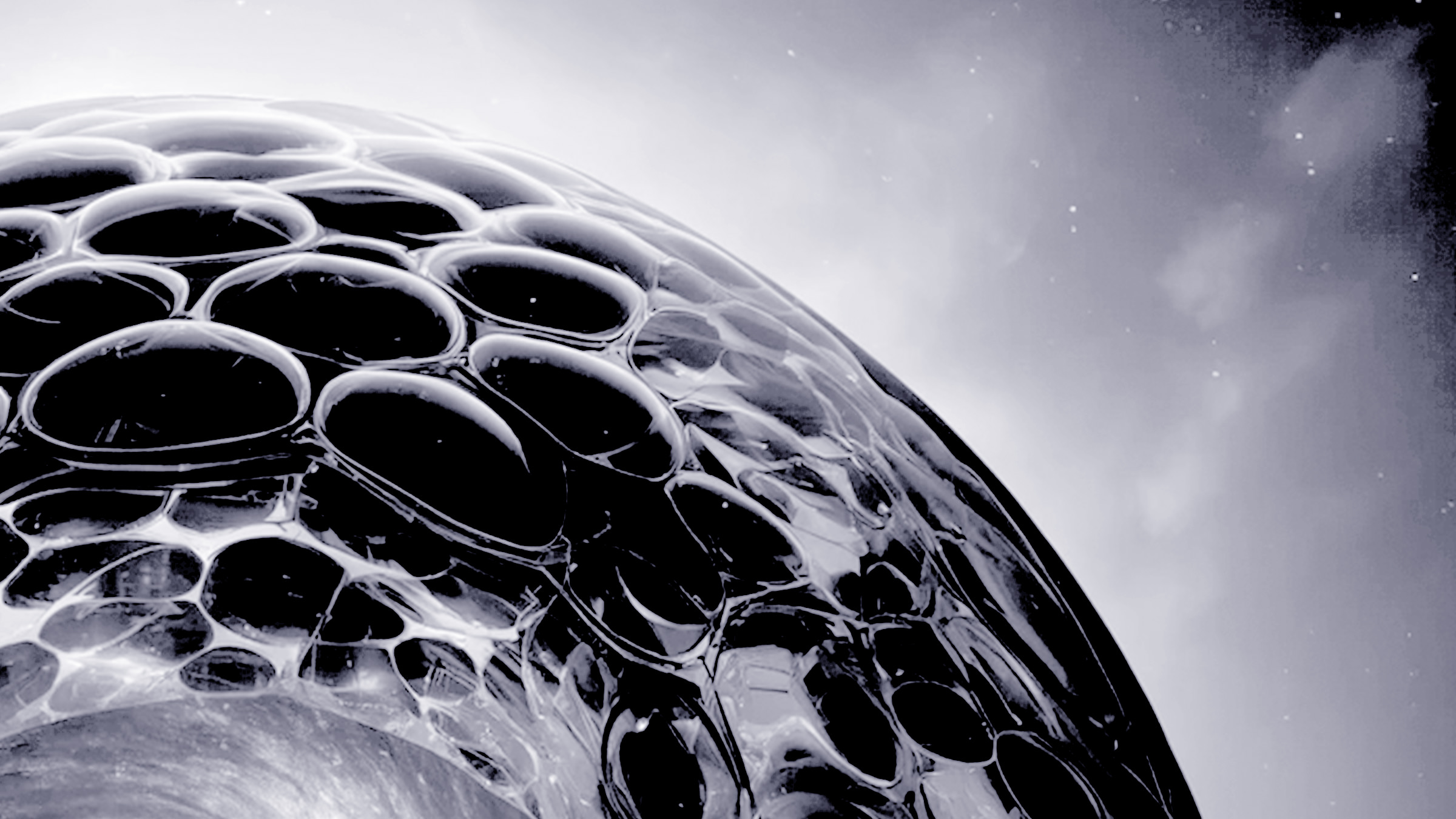
この近代社会は、さまざまな境界線によって構成されている。世界は主権を持つ国家に分割され、そのあいだに引かれた国境線では、原則として当該国家の自由裁量による入国管理が行なわれている。それぞれの社会は公的な領域と私的領域に分割され、前者では政府という単一の主体によって万人が等しく扱われるのに対し(法の下の平等)、後者では企業を中心とする私的団体の自由な競争のなかで利益追求のために顧客の差別化が目指される(銀行に行けば窓口に並ぶことなく支店長室で対応されるような(あるいは呼べば行員の方から自宅にやってくるような)大金持ちの優良顧客であっても、市役所で住民票の写しを受け取るには番号票を取って待っていなければならない)。社会の構成単位として権利や義務を認められる主体が人であり、それ以外の存在は権利の対象となる物に分類される。そして肉体という境界線によってそれぞれのヒトは区切られており、他者の痛みを私が直接に知ることができないようになめらかなコミュニケーションは阻害され、言語という不透明で頼りない手段を用いることなしにはなにごとを伝えることもできない……。
空間に関する物理的な境界線だけではない。主権国家同士は平時において対等かつ平和な外交関係を維持しており互いに干渉することがないが、宣戦布告を典型とする一定の手続きによって戦争状態へ移行した場合には相互の領土への侵入や敵軍人の殺害という行為が特別に許されるようになる。戦争の開始と終結に関する国際法上の手続きが、戦争と平和という時間的な状態の境界線を形作っているということになるだろう。
だがここまで書けばすでに自明であるように、これらの境界線は現代において大きくゆるがされている。他国への侵略が「特別軍事作戦」と呼ばれ、戦時国際法に違反する行為が繰り返される。行政も効率化の圧力にさらされ、たとえば国立大学に経営センスが要求されるようになる。そしてイーロン・マスクのニューラリンク(Neuralink)に代表されるように、侵襲的な(人体に電極などを埋め込む形の)Brain Machine Interface(BMI)すら、その実証実験が進められている。現代はまさに、近代という社会モデルを構成してきたさまざまな境界線が善悪良否含めて多様なゆらぎにさらされている状況にあると考えることができるだろう。そして、士郎正宗による漫画版の《攻殻機動隊》を起点とする一連のストーリーもまた、国家と企業、戦争と平和、軍隊と警察、人間と機械、あるいはBMIを通じた個人と個人のあいだの境界線に関するゆらぎをめぐって展開されるものだったと言ってよいのではないだろうか。
公安9課創設の際の組織イメージを確認しておこう。「上は首相だけ/責任はわしが持つ…/階級なしの実力主義…/最優先ライン」「犯罪の芽を捜し出しこれを除去する―/お前やわしが心から望んでいた攻性の組織だ/質はお前達次第だが」(士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(講談社、1991年))。外国からの諜報活動や軍政指導者のような外からの敵、腐敗した公安関係者やテロリスト、ハッカーといった内からの敵の双方に対抗し、秩序をゆるがせようとする策動に攻撃的に立ち向かうことで社会という内部を守ろうとする外殻──そのイメージはまた、内部に搭乗する少佐やバトーと一体となりその身を守るタチコマたちの姿とも重なっているだろう。
だがここには矛盾が潜んでいるようにも思われる。境界線に関するゆらぎを許容せず排除していくとすればその中身は固定されていくだろう。その果てにあるものは安定という名の死にすぎないのではないだろうか。「システムの硬化……熱的死は一見安定の概念に近い様だが/「変化に乏しく一様でゆらがないシステム」は破局の可能性が増大し/真には不安定といえる」(同書)という「人形使い」の指摘も想起しよう。そもそも守るべき対象としての社会すら、同作においては矛盾と不公正に満ちたものであることが明確にされている。その敵を排除することで公安9課は不当な現状の維持に手を貸してしまっているのではないか──。

筆者はかつて、AIにより最適化された社会のイメージについて政治学者・五百旗頭薫による「昆虫化」という比喩を借りて論じたことがある(大屋雄裕「AIにおける可謬性と可傷性」宇佐美誠(編)『AIで変わる法と社会:近未来を深く考えるために』(岩波書店、2020年)第3章)。『アステイオン』誌の特集「可能性としての未来──100年後の日本」という提題に答えて五十旗頭は、外交・防衛といったハードな政策に集中し、民政やインフラの維持といった内的な課題を忘却し、ただ閉じこもることによって外的危機の克服を目指す国家の姿を、外在的な危機から内部を守るための外骨格に全力を集中し、その内側は支えるもののないまま内臓が血液のなかを漂っている昆虫の姿に重ねて描いた──「冬来レリ、我等昆虫化シテ春ヲ待ツ」(五十旗頭薫「昆虫化日本 越冬始末」『アステイオン』91号(CCCメディアハウス、2019年)140-145頁)。内外のあいだにある境界線を前提として、あらかじめ想定された脅威に対応することにのみ適応した社会を作り上げることに向けて、AIはおそらく効率的に機能するだろう。だがそのようにして構成された昆虫的社会は個体の変容と進化を断念し、作り上げた外殻の内部でのみ生存できるような存在にすぎないのではないだろうか。
たしかに一方で昆虫はこの世界で繁栄を極めている存在だと考えることもできる。確認されている生物種の半数以上が昆虫で占められていると言われるほど多様に発展し、地球のあらゆる場所に棲息するに至っているからだ。だが同時にそれは種や集団を維持するためのエコシステムであり、個の存在は種のために消費される資源であるにすぎない(天敵であるオオスズメバチを集団で包み込み、蒸し殺すことで巣を守るニホンミツバチの行動を思い出そう)。世代交代によって進む変異・適応・放散を通じて種としての変化を実現するため、それ自体が変化することのない個体はごく短い寿命で消費されていくのだ。拙稿から引用しよう。
言い換えれば、単一個体としての昆虫とは緩やかな死の過程にすぎず、一切の「生命への飛躍」(élan vital)を含まないということになるのではないだろうか。/この言葉を生み出したアンリ・ベルクソンが、人間性の本質を創造的進化(L’évolution créatrice)に、予測も付かないような飛躍を帯びた創造的活動に求めていることを思い出そう(Henri-Louis Bergson, L’evolution creatrice, Felix Alcan, 1907(合田正人・松井久(訳)『創造的進化』(筑摩書房、2010年))。個体としての変化可能性を持ち、環境変化への適応能力を維持するという脊椎動物的なエコシステム──もちろんその代償として、薄い皮膚に覆われただけの外面はさまざまな危険によってたやすく傷つけられてしまうわけだが──をこれと対置することが許されるなら、そのような可傷性に裏付けられた変化可能性にこそ我々の──現代の社会を生きる人類の未来はあると、なお言うべきだろう。
──大屋前掲
そしてここでの問題は、個体の変容可能性を選び取った脊椎動物の脆弱な皮膚もまた、個体の生存を維持する上での問題点になるということだろう。外殻はそのような危険を排除するために硬く、攻性でなくてはならない。だが強力であればあるほどそれは変容への枷となり、現状を固定する圧力として機能するだろう。その一方で、変化を拒絶し永遠の静寂ないし停滞に留まるという選択肢を、草薙素子が一貫して拒否してきたことを想起しよう。最新作である『攻殻機動隊 SAC_2045』のラストもその一例だと考えることができるだろうし、タチコマたちの機能や可能性を制限するのではなく彼らが「反乱」に至る状況をシミュレートし対応を想定しておくという漫画版のエピソードも、ゆらぎによる変容を内包した動的平衡への志向を物語っているように思われる。生存を守るための境界線である外殻と、環境からの影響を受け進化し新たな存在へと変容していくためのゆらぎという二つの側面の矛盾を、草薙素子という人物は一身で体現しているのである。
1991年、士郎正宗による《攻殻機動隊》単行本の刊行から3ヶ月を待たずに、作中にも登場するソビエト連邦は崩壊した。世界は「歴史の終わり」を見たという楽観的な意見は、だが澎湃と沸き起こる民族紛争と宗教対立のなかで姿を消し、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件によってとどめを刺されたというべきだろう。それ自体が大規模テロという戦争と犯罪の境界にある事件であるだけでなく、実行母体であるアルカイダも従来の過激派と異なり明確な組織を持たず、指導者であるオサマ・ビン=ラディンなどがネット上で発するメッセージに共鳴した人々が自主的・自発的にアルカイダを名乗ってテロ行動に及ぶような──警察官僚・松本光弘はそれを「勝手にアルカイダ」と描写していたが(松本光弘『グローバル・ジハード』(講談社、2008年))──群体的ななにかであるという点で境界的であり、その後にアメリカが行なったアフガニスタン侵攻もまた、「個別的または集団的な固有の自衛権の行使」(the excercise of its inherent right of individual and collective self-defence)という名目のもとに行なわれた「戦争ではないなにか」であった(大屋雄裕「戦争と平和と法の黄昏」山元一(編)『憲法の基礎理論〔講座 立憲主義と憲法学 第1巻〕』(信山社、2022年)第9章))。
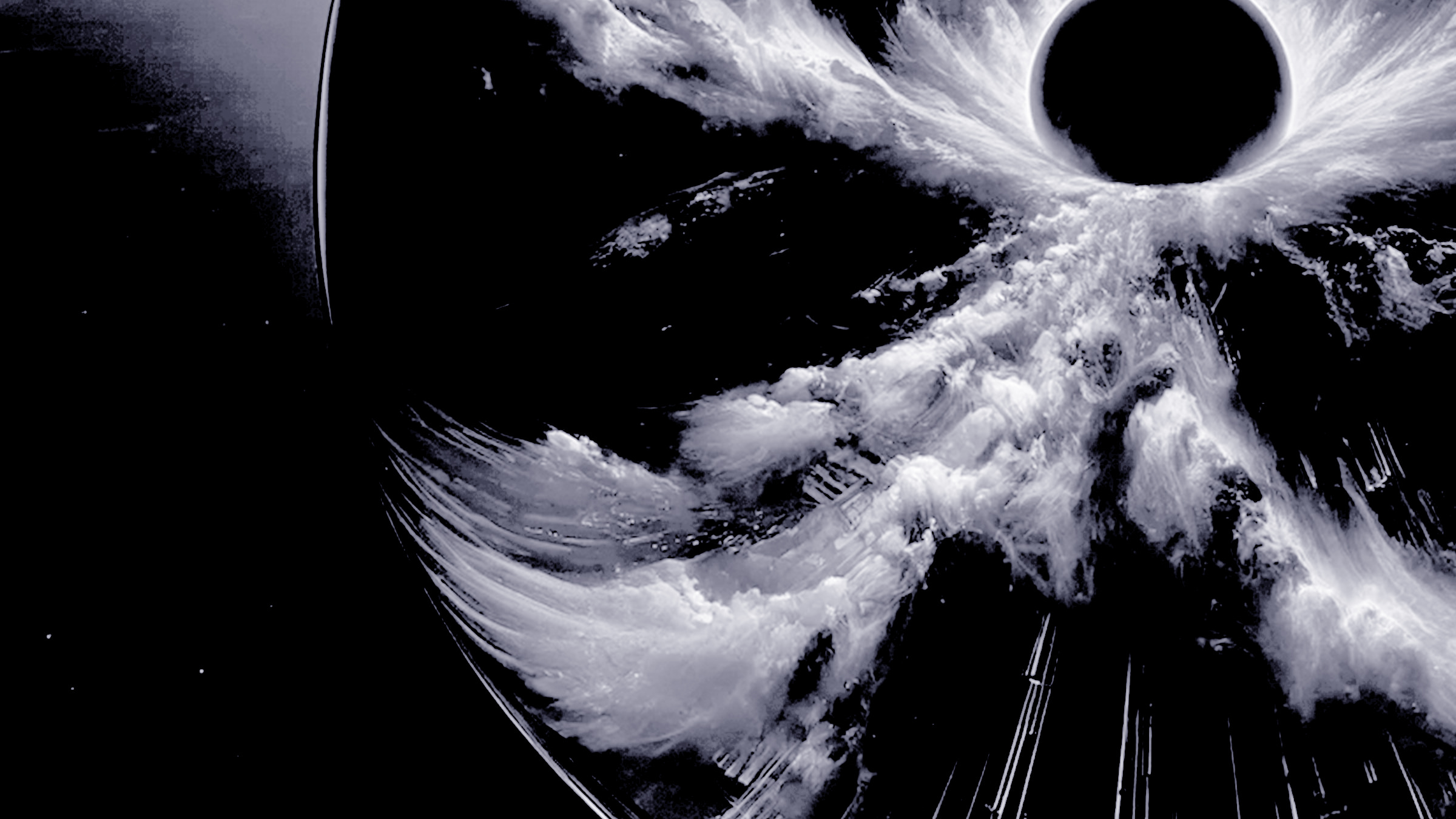
あるいはそれを、古典としてのあるべき運命だと受け止めるべきかもしれない──最近になってマンガを読み出した若者の目には『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズがありきたりの決まり文句(クリシェ)に満ちた作品に見えるという話を聞いて驚愕したことを思い出す(もちろん『ジョジョ』の側がそのような決まり文句を創造してきたのだ!)。だが通常の古典と異なるのは、《攻殻機動隊》の世界とストーリーがいまだ完結したものではなく、未来への変容に開かれているということだろう。ゆらぎは危機であり、同時に個体の変容とそれを通じた社会の進化の可能性を開くものでもある。さらなる境界線とゆらぎに向けて、《攻殻機動隊》の世界は新たな変容を繰り返していくだろう。次のストーリーは、どのようなゆらぎの物語へと我々を連れて行くのだろうか。
我々は摩擦のないなめらかな氷の上に迷い出たのだ。そこでは、条件はある意味で理想的なのだが、しかし我々はまさにそのために先に進むこともできないのである。我々は前へ進みたい。そのためには摩擦が必要だ。ざらざらした大地へ戻れ!
──Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, trans. G.E.M. Anscombe, Blackwell, 1953(黒崎宏(訳・解説)『哲学的探究 第1部』(産業図書、1994年)(訳文は変更している))

