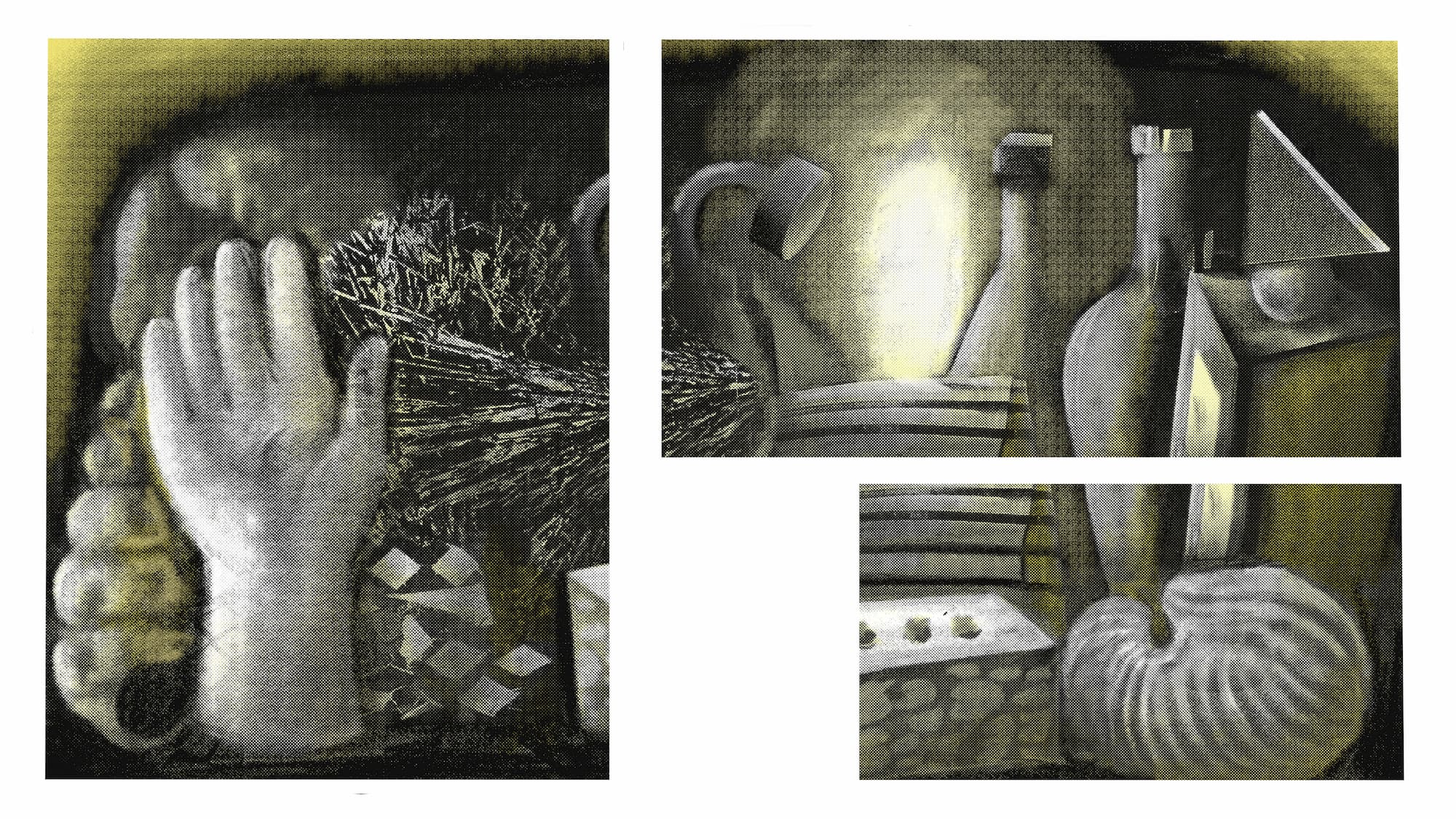
牢記物店──過去と、身体と出会い直すための
図版_小林紗織[Saori Kobayashi]フェミニズムとクィア、旅、アート、ケア、タロット、魔女、教育、言語、身体、日記……緻密に、けれど飛躍を伴って様々なイシューを自在に行き来する書き手、山﨑燈里。有機的な思考の連なりは読んでいて心地よく、でもときに大きな謎を読み手に投げかける。《攻殻機動隊》シリーズがはらんでいる様々な問いと、この著者を掛け合わせたとき、何が起こるのか。
自分の身体に数多くあるホクロを採譜して作曲し、さらにはその楽譜をタトゥーにすることによって身体に戻していく試み。この楽譜のタトゥーに関するストーリーから始まる燈里の論考は、体が傷つき治ること、しかしそこに体験や感情の気配が残ってゆくことを見つける。
一方、草薙素子の身体に傷や体験は残らない。義体化によって多かれ少なかれ身体を奪われている公安9課のメンバーの中でも、脳核以外のすべてがツルツルの義体である素子は傷つかず、このことは素子に自分の存在にまつわる根本的な不安や疑問をもたらしている。傷の、経験の記録されない身体のどこにゴーストは宿っているのだろうか。
20代の大半を台湾で過ごした燈里は、街中でたくさんの「牢記物店」に出会ったという。前の持ち主の痕跡や気配が記録されたものがひっそりと置かれる骨董品店。素子が子ども時代の義体と出くわし、過去の記憶をたどったように、燈里もある日本人女性による詩集と出会い、共鳴する。身体の外にも記憶装置があり、過去と現在は呼吸するように結びついたり、離れたりする。
経験の刻まれた身体で生きていくことと、それすらままならぬ草薙素子。潜水する素子は、海底で自分の中の何を不安定な海の中へ放ち、何を確かめているのか。
目次
楽譜としての身体、彫刻としての人間
米田恵子(1912-1992)は、アマチュアの作曲家、そして詩人として、実験的で挑発的な音楽と詩の制作を生涯行った。代表作として、1943年から1945年のあいだに、ベートーベンの全32曲のピアノソナタから1154のドミソの長三和音を抽出し再編成した特異な楽譜を制作した。しかし、米田は組織に所属せず、また女であったことから当時正当に評価されず、近年になって音楽と文学両方の分野において作品の分析と再評価が進んでいる*1。そんな米田恵子を記念する国際作曲コンクールがあった*2。条件は、米田のようにドミソの3音のみを用いて作曲すること。使える楽器はチューバとピアノ、ソプラノの声音であること。2022年、タロット占いをして知り合った方からその作曲コンクールの存在を教えてもらい、楽譜を書いて応募したら、審査を通過して米田賞を受賞した*3。私は作曲について何も知らない。これが最初で最後の作曲になった。この楽譜はその後、東京と京都の演奏会でチューバの坂本光太さんに演奏していただいた。観客は戸惑っていたと思う。なぜなら私が制作した楽譜はタトゥーとして全身に入っているからだ。私は体にホクロが66個ある。黒丸であるホクロに線を足すと音符の形になる。ホクロを音符、皮膚を譜面と見なし、全身のホクロを用いた作曲をした。ホクロを線でつなぎ合わせ、ドローイングスコアとしてタトゥーで彫り込んでいる。
楽譜であるからにはもちろん音が鳴る。演奏会では下着で舞台に立ち、体に書き込まれたタトゥーの音符をゆっくり順に指で指し示す。左の頬から始めて、首、左腕、背中、左脚、と下りていって、また右脚、右腕、首、右頬と上がってくる。私の指に合わせて坂本さんが譜読みしチューバを吹く。それと同時に、パーカッションの八木友花里さんがバスドラをブラシで擦ったりゴムで弾いたりして、私が指し示す部分の皮膚の感触を表現したこともあった。鏡に肌を映すことで自分で譜読みし、ピアノで弾いてみることもある。ホクロ音楽と呼んでいる。演奏中はなんだか馬鹿馬鹿しくて自分でも笑ってしまう。
タトゥーはインクの侵襲によって肌に残る傷痕だ。ニードルで肌を浅く傷つけ、そこにインクを流す。傷が治る過程でインクが肌に取り込まれる。それは人体には生体内の恒常性を保持しようとする働きが本来備わっているからだ。体が痛みを取り込み、その回復の過程を示す証がタトゥーになる。抽象的な意味では、私たちの体には目に見えないタトゥーが入っているのかもしれない。日々私たちの体には様々な体験や感情が通り抜ける。それらを忠実に覚えていることは不可能だが、完全に忘れることもない。友人のカレン・ピットニーは、人は流動的な彫刻であると言った。素材を彫って彫刻をつくるように、私たちにもあらゆる経験が彫り込まれ、そのたびに回復し、いまのひととなりができている。1回1回の彫りはあまりに些細なもので、まるで柔らかな雨水の滴りが岩を穿つような力と速度だろう。しかし、結晶質石灰岩のように、時間をかけて水が岩に溝状の痕を残し、岩全体を変容させることは可能だ。その痕は、時間が経過しても過去の経験の影響がいまも残っていることを示す。その痕は、時間が経過しても過去の経験の影響がいまも残っていることを示す。私たちは生きている限り変わり続ける、未完成の彫刻だ。
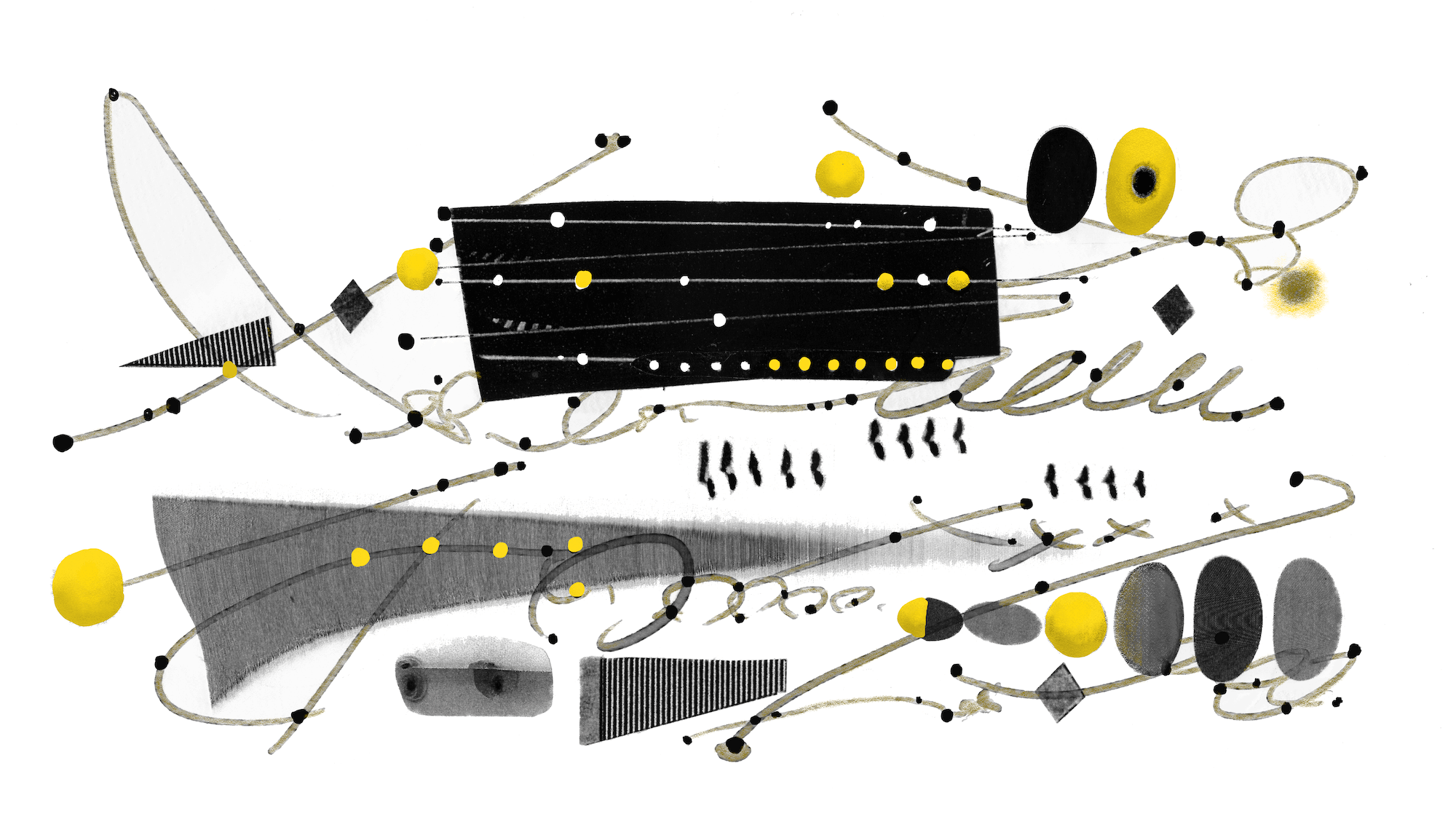
ツルツルの義体の中にゴーストは宿るか
1989年に出版された漫画『攻殻機動隊』は、2029年以降の近未来を描いた。その高度に発達した未来社会では、神経系からインターネットに直接アクセスできる「電脳化」や、肉体をサイボーグに置き換える「義体化」の技術が飛躍的に発展し、一般に普及している。主人公の草薙素子(以下、少佐)は、電脳殻に覆われた中枢神経系を除き全身をサイボーグ化する「完全義体化」を果たした。彼女は内務省/首相直属の防諜機関/攻性組織、公安9課の現場指揮官でありハッカーである。義体制御能力の高い少佐は、体を見事に制御し、技術の進化を生かして突出した戦闘能力を有す。しかし、生身である脳核だけが制御と機械への統合を回避し、疑問を生む。1995年に劇場公開された押井守監督による映画版『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』では、少佐は「私は存在するのか」「何を根拠に自分を信じるべきか」と自問し続けている。彼女は元々の肉体のほぼすべてを子どものころに失っており、脳の存在も目で見て確信することができない。電脳はハッキングされることがあり、疑似現実や偽物の記憶を現実世界の中に見てしまうことで 、認知やアイデンティティ、記憶が他者によって書き換えられる事態が発生している。少佐は自身が関わる事件で電脳のハッキングを目の当たりにし、自意識やアイデンティティに対して不安定な感覚をもつ。肉体の身体的な機能のほぼすべてを機械が侵襲したとき、「私」は「模擬人格」ではないと証明できるのか。体が肉体から義体、古い義体から新しい義体へと変わっても、「私」は同一なのか。そもそも「私」は初めから一貫して存在し続けているのか。少佐は迷いを同僚のバトーに吐露する。バトーは、少佐はチタンの頭蓋骨の中にオリジナルの脳核があり、周囲から人間扱いされているがゆえに、存在すると返すが、彼女は納得できない。私はその少佐の揺れに惹かれた。
《攻殻機動隊》には、バトー含め電脳化し、体を一部サイボーグ化したメンバーがいるが、誰も自己同一性を巡る疑問をもっていないようだ。この違いは、少佐が完全義体化を果たしているだけでなく、女性型サイボーグであることに起因しているのではないだろうか。男性のメンバーは異なる体型、年齢、顔をもっているにもかかわらず、完全な義体である少佐のそれらは均一な量産品である。映画の中で女性のマネキンが複数回出てくるが、少佐の外見もまるでマネキンのように完全な形状と質を保つ。設定の40代後半には見えない。哲学者のビョンチョル・ハンは、著作Saving beautyの中で、現代を特徴づけるのは「ツルツル(smooth)」だとし、その例としてジェフ・クーンズの彫刻、iPhone、ブラジリアンワックス脱毛を挙げている。私たちはどうしてツルツルに惹きつけられるのか。それは単なる審美的な象徴を超えて、一般的な社会の責務、つまり今日の「ポジティビティの社会」を反映しているという*4。ツルツルは傷つかない。よってそれは免疫がなく、抵抗もしない。あらゆる形態の「ネガティビティ」は排除される。少佐の体もツルツルで傷ひとつない。戦闘で体が損傷しても、何度でも新しい義体に取り替え、修復できる。痛みを感じることもないのだろう。しかし、その生存には、国家しか負担できない高価で最新技術のメンテナンスがつねに必要になる。公安9課の人々の体は兵器として規格化され、国家の管理下にある。例えば、酒を飲んでも体内の化学プラントが数十秒でアルコールを分解し、いつでも仕事の戦闘体制に入れるように設計されている。戦闘において道具として機能しない場合、義体の「バグ」と見なされ排除の対象となる。退職するには義体と記憶の一部を政府に「返さないといけない」ことからも、体やそれを司る意思と主体性は権力機関に所属していることがわかる。それによって行動が制約されたり、過去の記憶が消去されたり、自分の体のあり方が選択できない。
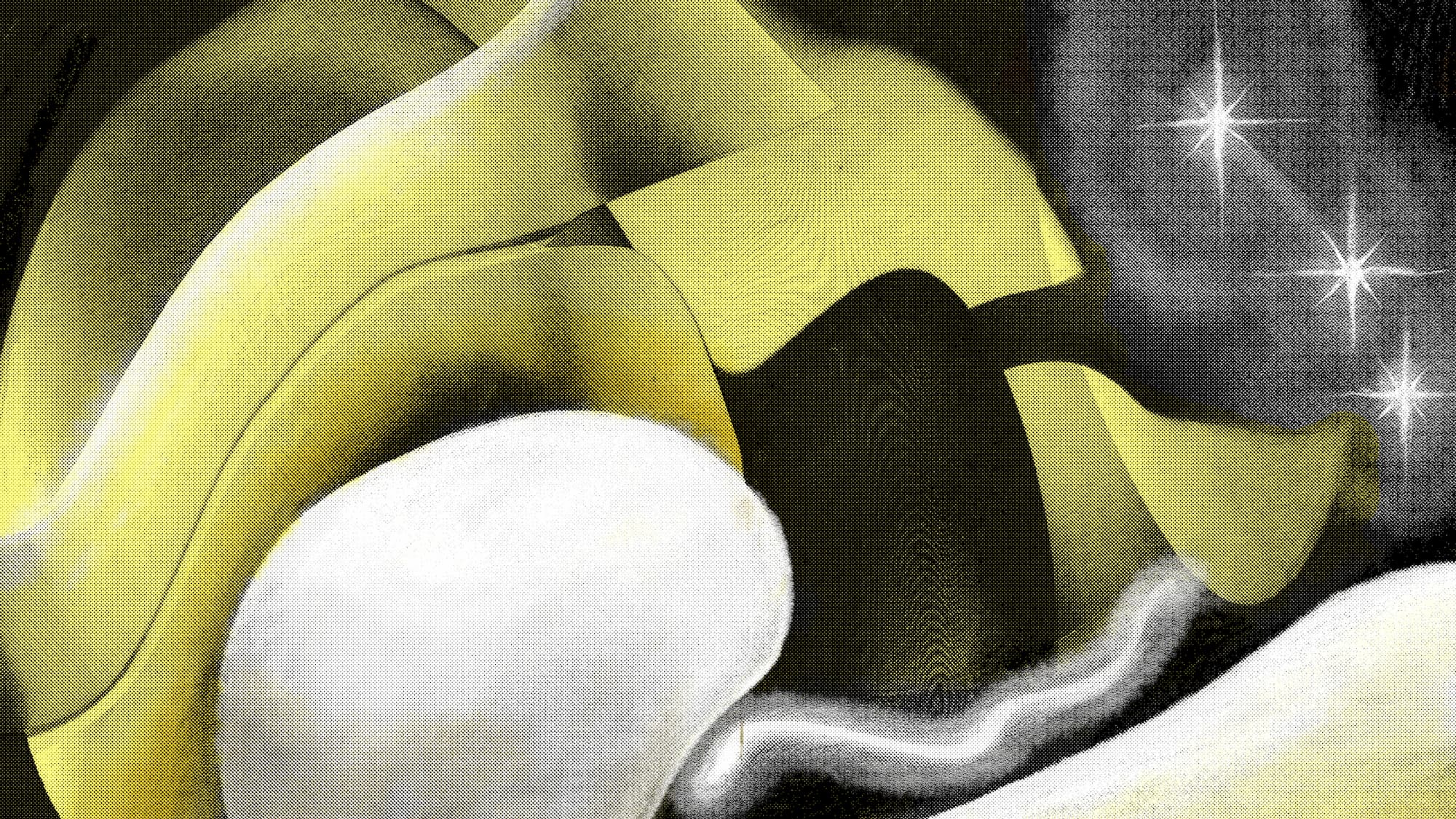
アニメ版『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』の「顔 MAKE UP」というエピソードでは、スナックで「ママ」と呼ばれる女が次のように語る。「ゴーストって脳核の中じゃなくて皮膚、とくにその顔に刻まれた皺に宿るんじゃないかって。その造顔作家の先生は戦場で負傷した兵士のために新しい顔をつくっていたらしいんだけど、あるとき顔の傷の深さがその兵士の心の傷の深さと同じなんだって気づいたそうよ」。「ゴースト」は《攻殻機動隊》の世界で一般に広く共有されている概念であるが、たしかな説明がなく、曖昧で包括的だ。ゴーストとは自我や意識、霊性を指し、人格と深く関わっている。少佐は明確な根拠を伴わない直感を「ゴーストの囁き」と呼び、信じ従い、ときにそれが事件の解決に繋がることもある。自分のゴーストを信じることは、少佐にとっては擬似人格ではない自分の存在の確認になっている。そのゴーストが皮膚の皺に、もしかしたらホクロに、あるいは傷痕に宿るのだとしたら。そのようなものが決して残らない少佐の体のどこから、ゴーストは囁きかけてくるのだろう。
商品、そして兵器としてのツルツルの義体であっても、少佐は体に「ネガティビティ」を感じ、自分の存在に疑問をもつ。《攻殻機動隊》のほかのメンバーは、自ら選択して超人的なサイボーグに体を強化しているが、少佐は違う。子どものころ、航空機事故による重度の怪我により肉体を喪失し、生き残るために止むを得ず全身義体化した経緯がある。その身体的痛みを伴う侵襲の記憶を取り戻すエピソードとして、「草迷宮 Affection」がある。ある日、少佐が勤務中に偶然小道の階段に入ると、上からゴムボールが落ちてくる。少佐はそのボールを追って、また何かの意思を感じて、「牢記物店」という骨董品屋にたどり着く。そこでは電脳がつながらず、外部との連絡やネットが絶たれた「バグ」状態になる。牢記物店は思い出の品を預かっておく場所、つまり記憶の外部装置の保管場所であった。彼女はその中に自分の子ども時代の義体を見つける。牢記物店に少佐の義体を預けた男が残していった、義体にまつわる記憶を店主が少佐に伝えることで、初期の義体への統合に苦しんだ少佐の過去が明かされる。情報ネットが高度化した近未来にもかかわらず、牢記物店では記憶の保存手法は物質的でアナログだ。人は記憶を携えた物質を牢記物店に託し、その物語を店主に言葉で伝え、店主が誰かに語り継ぐ。牢記物店は導かれた人間しかたどり着くことができない。ツルツル化に抗う少佐の体の記憶は、権力から独立して牢記物店にひっそりと保管され、ほかの物語と共に堆積している。
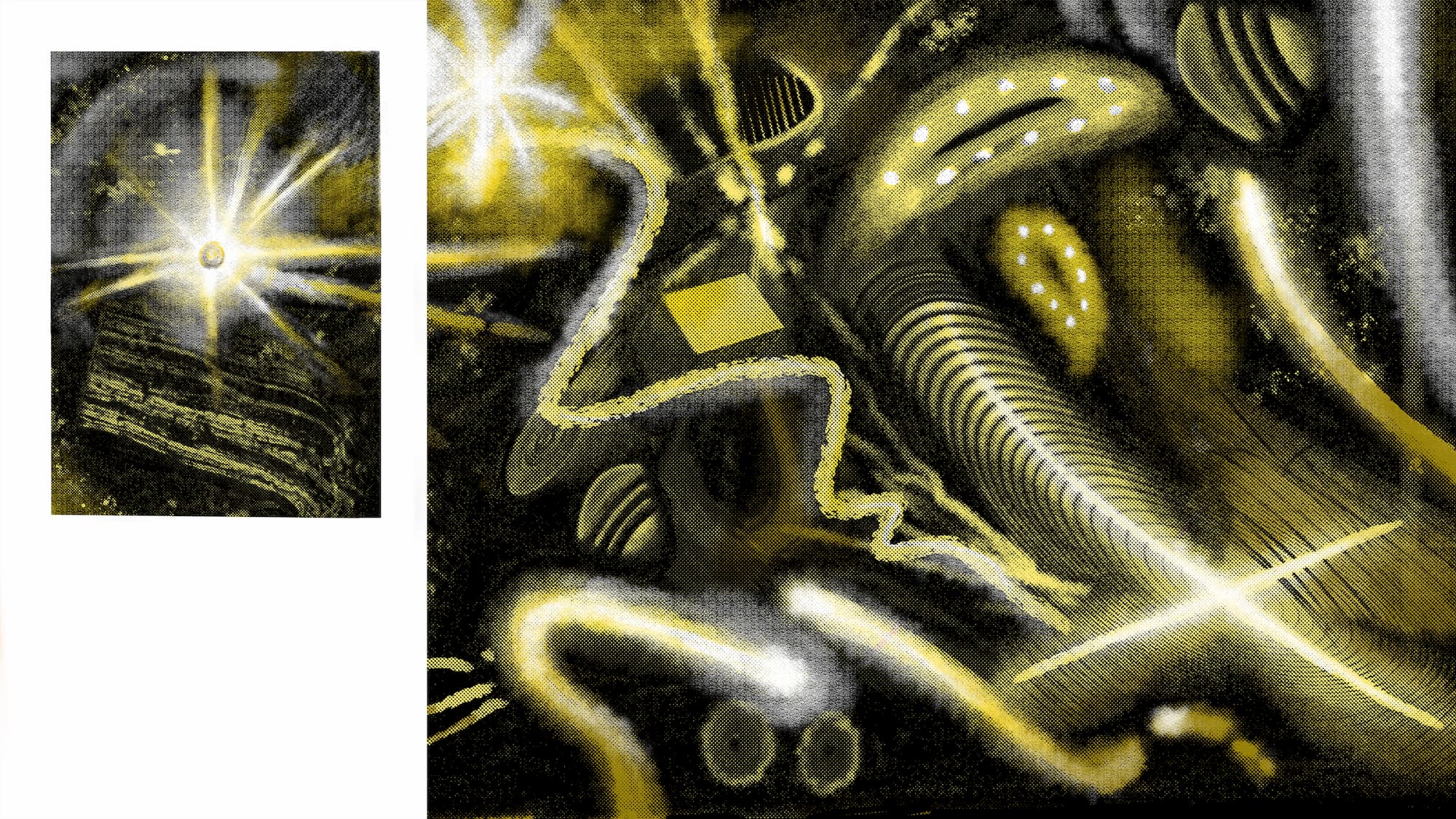
路地裏で、そして海底で彷徨う素子
自分に対して、世界に対して問いをもつ。簡単な答えに飛びつくことなく問いを抱えたまま、偶然性にドアを開き、彷徨うとき、不意にボールが落とされることがある。そして牢記物店に招かれる。私は20代の半分以上を台北で過ごした。台湾は不思議な空間が迷宮のようにつながり合っている。そこに足を踏み入れたことにさえ気付かず、出口がどこかわからないまま、夢と現実、歴史と現在、公と私、台湾華語と英語と日本語を行き来していた。その過程で台湾のどの都市でも牢記物店に行き着いた。そこには個人が思い出の品を譲りに訪れる。それらはクリーニングを経たあと、安価で売り出される。几帳面に並んだ一つひとつにもとの持ち主の気配が残っており、店主がその物語を知っていた。いきなり小道で出くわした牢記物店には二度とたどり着けないこともあった。
タロットカード、貝殻、花瓶、小物入れ、アクセサリー、椅子。台湾の牢記物店で多くのガラクタを掘り出して収集する中で、1995年に青山かつ子という詩人が出した『さよなら三角』の古本を見つけた*5。ネット検索に引っかからない、絶版になったこの本を、誰かが昔日本から持ってきて台北に置いていったのだろうか。詩集のページを捲ると、詩はどれもこれも不気味で不吉で後味が悪い。蛇や虫や血や沼のモチーフが繰り返し登場する。詩の語り手である「私」は、丈夫な糸で男の口を縫い合わせたり、男の手の水かきに鋏を入れたり、男を洗濯機で回してその皺を布団叩きで伸ばしたりしている。女が日常的に家事で使う道具を用いて、男の抑圧に身体的に逆らい、本来の自分の声と力を取り戻そうとしているのだと解釈した。詩集は透写紙に包まれていて、まるで本の皮膚のように見えた。その透写紙を剥がして自分の肌に当てると、ホクロだけがぼんやりと黒く透けた。古い紙の染みが私のホクロに重なった。この透写紙のように、私の皮膚も体の表面を包み、守り、その結果、歳を取るにつれホクロが増えていく。ホクロは時間の経過と老いを示し、つまり肌に残る記憶であり、唯一無二で、体の証となる。この古本を買い、帰宅後、透写紙に自分の全身のホクロを写し取ってみた。私のホクロは自分の皮膚から本の皮膚へと移された。私が私であることのいまの記憶の一部を青山かつ子に重ねるかたちで外部化できたのかもしれない。この試みはのちにホクロの音符となり、楽譜として私の体に再び入ることになった。
私たちの皮膚には記憶が彫り込まれ、その痕跡がいまの姿をつくる。少佐には痕跡をたどれる皮膚がなくなっても、権力から離れた牢記物店で義体に皮膚の記憶が預けられている。皮膚の拡張だ。牢記物店で子ども時代の義体と対面した少佐は、義体化したばかりのころ、手先が細やかに動かせず、折り紙で鶴を折れなかった記憶が蘇る。一度できるようになると、私たちはそれが習得されたものであることを忘れてしまう。子ども時代の義体との再会を通して、少佐は当時の怪我の痛み、肉体を失った感覚、義体の指先の違和を感じただろう。昔の体が「もうない」という実感が過去の時間を意識させ、手元には豊かな喪失の感覚が残る。少佐は自分の存在のありかやその真偽性に固執する必要はないのではないか。牢記物店への出入り口である小道で、少佐は文字通りボールを手放していた。体を義体に侵襲させても、「オリジナル」の肉体から変化があっても、記憶の真正性を疑ったり、忘却を恐れるのではなく、過去を手放すこと。思い出は子ども時代の義体や店主の語りにいったん固定されることで、人間の有限性を超越して、他者に共有し手放すことが可能になる。ただし、それは永遠に固定されるわけではない。再び彷徨うとき、きっとボールは落とされる。牢記物店に戻り過去に立ち返るたび、過去は現在と結びついていまの中に生きる。現在のツルツルの体と過去の皮膚の喪失感、その狭間に少佐のゴーストは宿るのかもしれない。
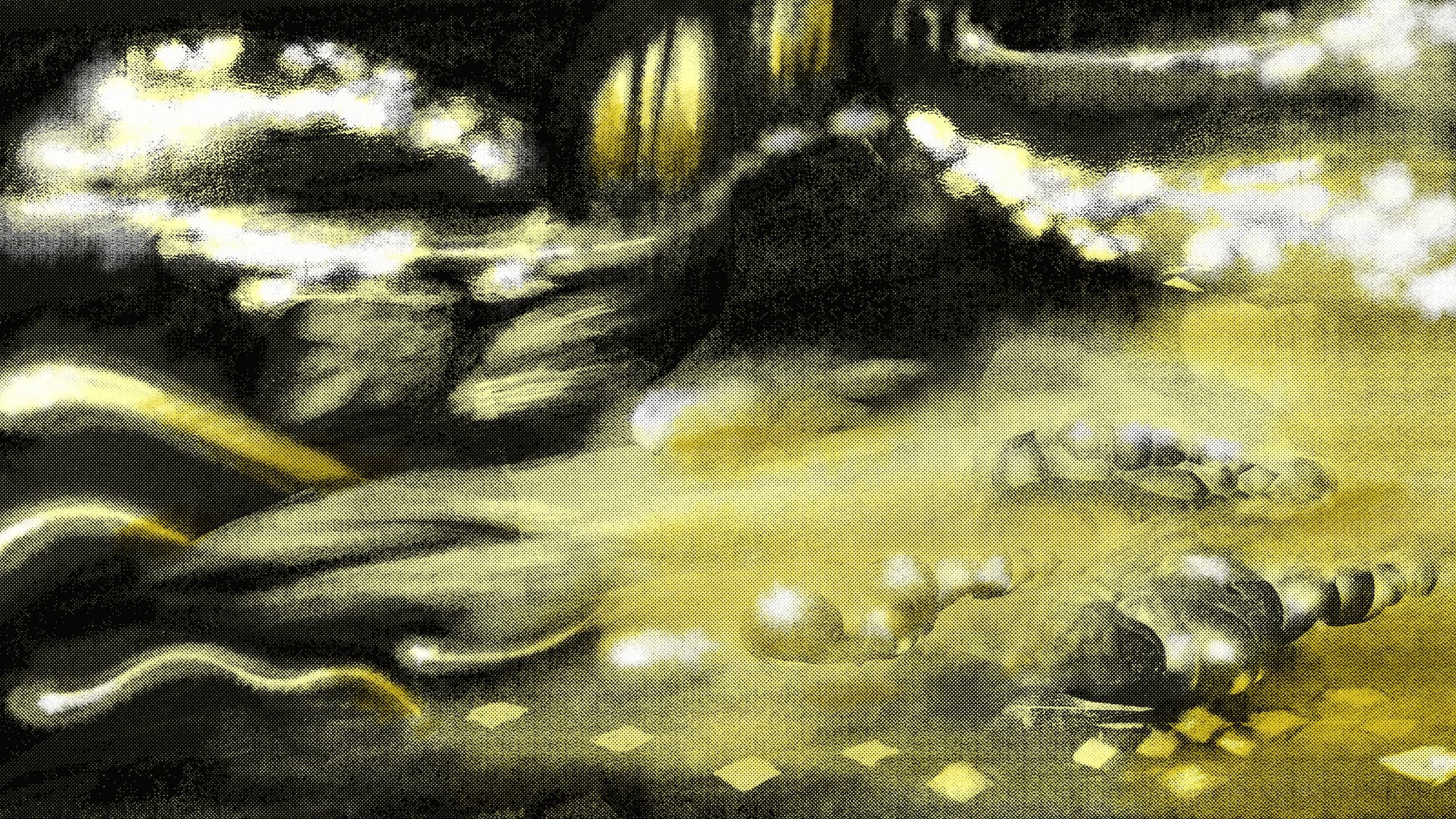
人間は不完全な体をもっている。だから無機質で劣化しない体に憧れる。もしも病や怪我、老い、死を遠ざけられたら。テクノロジーを用いて体の未来を思いのままにする幻想を抱く。《攻殻機動隊》が描くテクノロジーは、電脳化と義体化による一見強化した体や確実な未来を実現しているようだが、少佐の葛藤がSFの世界と私たちの体をつなぎ、テクノロジーの矛盾を暴く。テクノロジーへの幻想は、体から過去を切り離すことで、痛みごと痕跡を消そうとする楽観主義であり、その先にあるのは体を管理し消費する権威主義だ。テクノロジーは、まるで透明な水を管理するプールのように、体の未知を既知にすべく情報化して制御しようとする。一方、少佐は私たちを暗い海へと引き込む。映画版で少佐が非番中に海へ潜り、ゴーストの囁きを聞くシーンが《攻殻機動隊》シリーズで一番好きだ。体がサイボーグである少佐は、フローターが作動しないことがあれば海の底で死ぬ。沈む体で死のリスクを負ってまで、プールではなく海に定期的に潜る理由をバトーに聞かれ、少佐は次のように答える。「恐れ、不安、孤独、闇、それからもしかしたら希望。海面へ浮かび上がる時、いままでとは違う自分になれるんじゃないか」。そして少佐のゴーストが新約聖書の一節を囁く。「今我ら鏡もて見るごとく見るところ朧なり」。体の計算や予測には限界がある。体には、傷つき回復し変わっていく力が内在している。その過程で記憶が刻み込まれた体は、一人ひとり異なっている。その差異から生まれる多様性、そして継続的な変容によって、私たちは後天的に柔軟に環境に適応することができる。体は朧げにしか見ることができない。それでいい。私たちの体は本質的に神秘を抱えていて、その神秘性から生まれる自他の体への畏敬と隔たりが権威主義への力強い抵抗と解放になる。海に深く潜る少佐は、暗闇の中に自我を彷徨わせ、不確かさと変化に開かれている。
[註]
*1
右記動画、48分53秒より。「「米田恵子(1912-1992)の作品と生涯について」 Théâtre Musical Tokyo (TMT)」Kota Sakamoto、2019年
https://www.youtube.com/watch?v=3COK1UFsAhY&t=2933s
*2
「KYICC 2021 Committee「第一回 米田恵子国際作曲コンクール」 OPEN SITE 6|公募プログラム【パフォーマンス部門】」トーキョーアーツアンドスペース、2021年
https://tokyoartsandspace.jp/archive/exhibition/2021/20211211-7071.html
*3
「KYICC 2021 Committee「第一回 米田恵子国際作曲コンクール」」Tokyo Arts and Space、2021年
https://www.youtube.com/watch?v=vn-PD48ivh8
*4
Byung-Chul Han, “Saving Beauty.” trans. Daniel Steuer, Polity, 2017
*5
青山かつ子『さよなら三角』詩学社、1995年
山﨑燈里
やまさき・あかり/1992年生まれ、茨城県出身在住。翻訳者、作曲家。ジェンダー・セクシュアリティ、アクティビズムをテーマにエッセイや取材記事を書く。また、コミュニティ・オーガナイザーとして、本とDJとゲストのトークを交えたクィアパーティ、「こどくにおどるクィアの集い」を都内で定期開催中。

